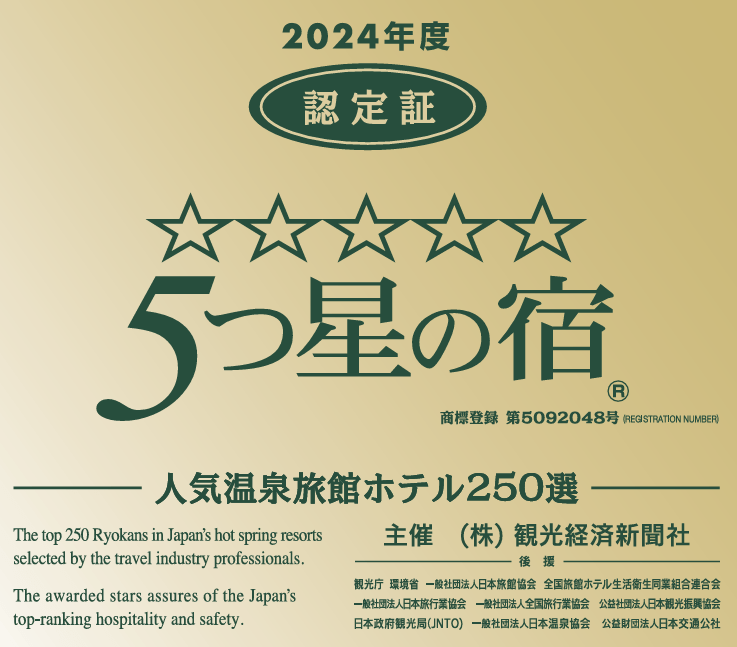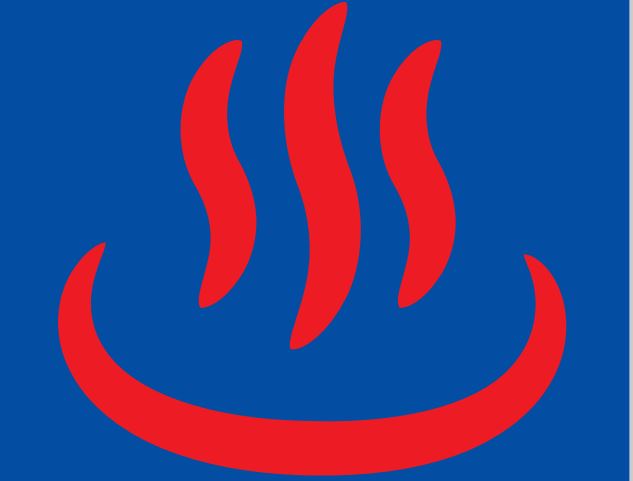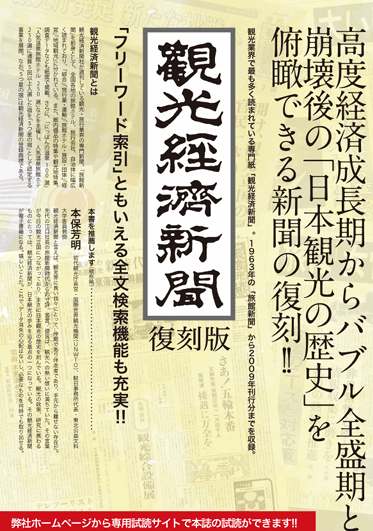還暦を迎えると急激に医療機関にお世話になる機会が増えた。そして医師とのやり取りをする際にいつ頃からか、すぐ目の前で会話をしているのになぜか距離を感じることがある。
筆者の母親の話で恐縮だが、米寿になっても1人で暮らしていた。ご多分に漏れず医療機関には頻繁にお世話になっていたが、耳が遠い(悪い)せいか聞き直すことが多く、医師からは付き添いか家族と来るように言われていた。
ただ母親の話では「先生はパソコンの画面ばかり見て話すので、何を言っているのかがよく聞き取れない。それと年寄りだから説明するのを諦めているのかもしれない」と診察のたびに落ち込んでいた。この時は母親の言っていることを実感できなかったが、今の自分にはその気持ちがよく分かる。
ある日その母親がうれしそうに話してくれたことがあった。それは湿疹でかゆみが治まらず、皮膚科でお世話になった時のことである。その医師は診察時に母親の顔を見ながら、「今回は塗り薬を出そうと思いますが、背中に塗ってもらえるご家族はいらっしゃいますか?」と聞いてくれ、そして「もしお1人なら少し効き目は落ちますが飲み薬を出しましょう!」と言ってくれたそうだ。
母親にとってはその医師が自分の顔を見ながら丁寧にゆっくりと話をしてくれたこと、付き添いがいなくても1人の患者として認識してくれたこと、そして何より自分の日常生活にまで思いを巡らせ寄り添ってくれたことがすごくうれしかったようだ。
この話を聞いた時に改めて思ったのは、医療関係者は日々たくさんの患者さんから話を聞くことになる。そしてうまく内容が理解できない人、よく聞き取れない人がいたとしても、医療は専門知識を要するサービス業だということである。
「医は仁術」「ヒポクラテスの誓い」ということばを耳にしたことはあるが、その精神には共通して「人を救う志、人を思いやる想像力」を内包しているように思う。
診察を経て、この医師は母親にとってとても魅力的で頼れる存在となり、そしてまた次もこの医師に診てもらいたいと感じたに違いない。
(帝京大学経済学部観光経営学科教授 宮﨑弘基)