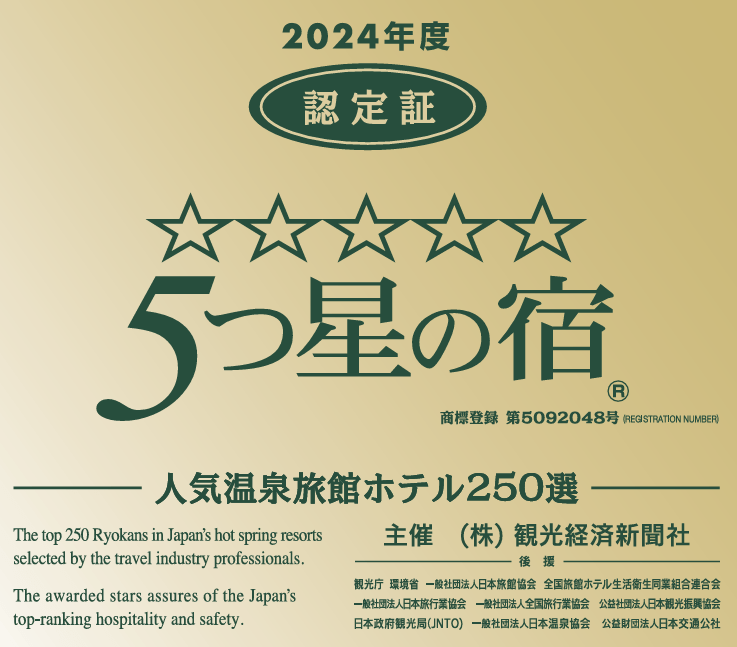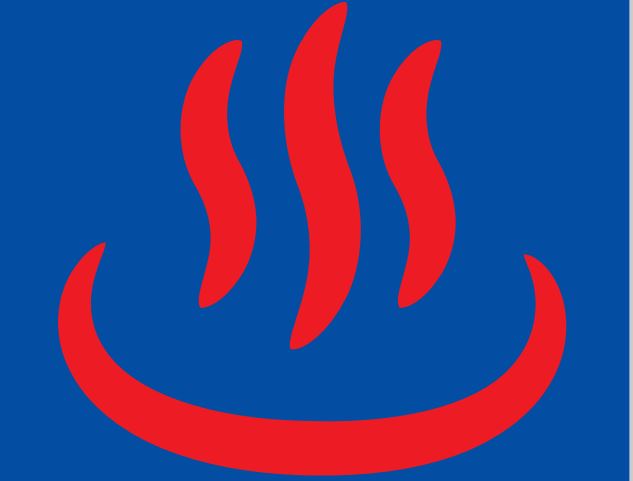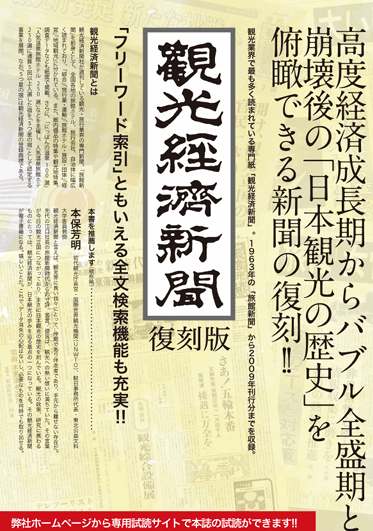竹内氏
先日、ハッシュドビーフを作った…と思っていたら、妹から素朴なギモンが飛んで来た。コレって、ハヤシライスじゃないの?…というワケで、「ナポリタン」「ドリア」などに続き、「ニッポン生まれの洋食」シリーズ第4弾として「ハヤシライス」をお届けする。
確かに、どちらも薄切りの牛肉を赤茶色っぽいソースで煮込んでいて、見た目はそっくり。困った時の「広辞苑」。調べると、ハッシュドビーフは「薄切りの牛肉と玉ねぎを炒め、トマト・ソースやドミグラス・ソースなどで煮込んだ料理」で、ハヤシライスは同様な文言の後、「飯の上にかけた洋風料理」とあった。
そこで今度は「調理用語辞典」でも確認したところ、前者はほぼ同じ。ハヤシライスは「細かく切った牛肉とタマネギを炒めて塩、こしょうし、ブラウンソースで煮込んで飯に添えたもの。ハヤシはhash(肉などを細かく刻む意)がなまったもので、正式にはハッシュドビーフアンドライスという。わが国独特の洋風料理である」とあった。
ルウを作っているメーカーなら違いが分かるだろうと調べてみると、ハウス食品さんもグリコさんも、諸説あるが明確な違いはない、と公式サイトで述べている。ただ、両社とも一般的に、ハッシュドビーフの方はドミグラスソースがベースの大人向け、ハヤシライスはトマトベースでやや甘めの子供向けの味、という認識のようだ。
ザックリ納得したつもりだったが、次のギモンが。…そういえば確か、ハヤシライスって東京日本橋の「丸善」が発祥じゃなかったっけ? ハッシュがなまったんじゃなくて、ハヤシさんが作ったんじゃ…?
ってことで、振り出しに戻って調べ直す。丸善は幕末から医者として活躍していた早矢仕有的(はやしゆうてき)氏が、明治2年に創業した洋書輸入販売店。同氏が勤務医時代、患者に滋養をつけさせるため、まだ珍しかった牛肉と野菜を煮て食べさせたとか、丸善で丁稚の少年たちに食べさせたともいわれているそう。ただ、ドミグラスソースが日本に入って来たのは明治20年代以降。だから当時はみそやしょうゆを使っていたとか、その後、トマトベースを経てドミグラスベースになったとも考えられている。
ハヤシライスのルウ、古くは明治40年ごろ、「固形ハヤシライスの種」なる物があったようだ。時を経てハウス食品が粉末タイプの「ハヤシライスの素」を発売したのが昭和9年、さらに同社が平成元年に「ハッシュドビーフ」という名称でルウを発売してから、この名が台頭してきたとか。案外最近のことだったのだ。
筆者はソース緩めが好きなので、ポッテリしがちなルウは使わない。具材をバターで炒めるとき、ほんの少し小麦粉をまぶせば十分だ。赤ワインをドバドバ入れて、缶詰のドミグラスソースとブイヨンのキューブ、時間があればカラメルソース、なければ黒糖でコクを出せば、超ベリウマなハヤシソースの出来上がり♪ ぜひお試しあれ!
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。