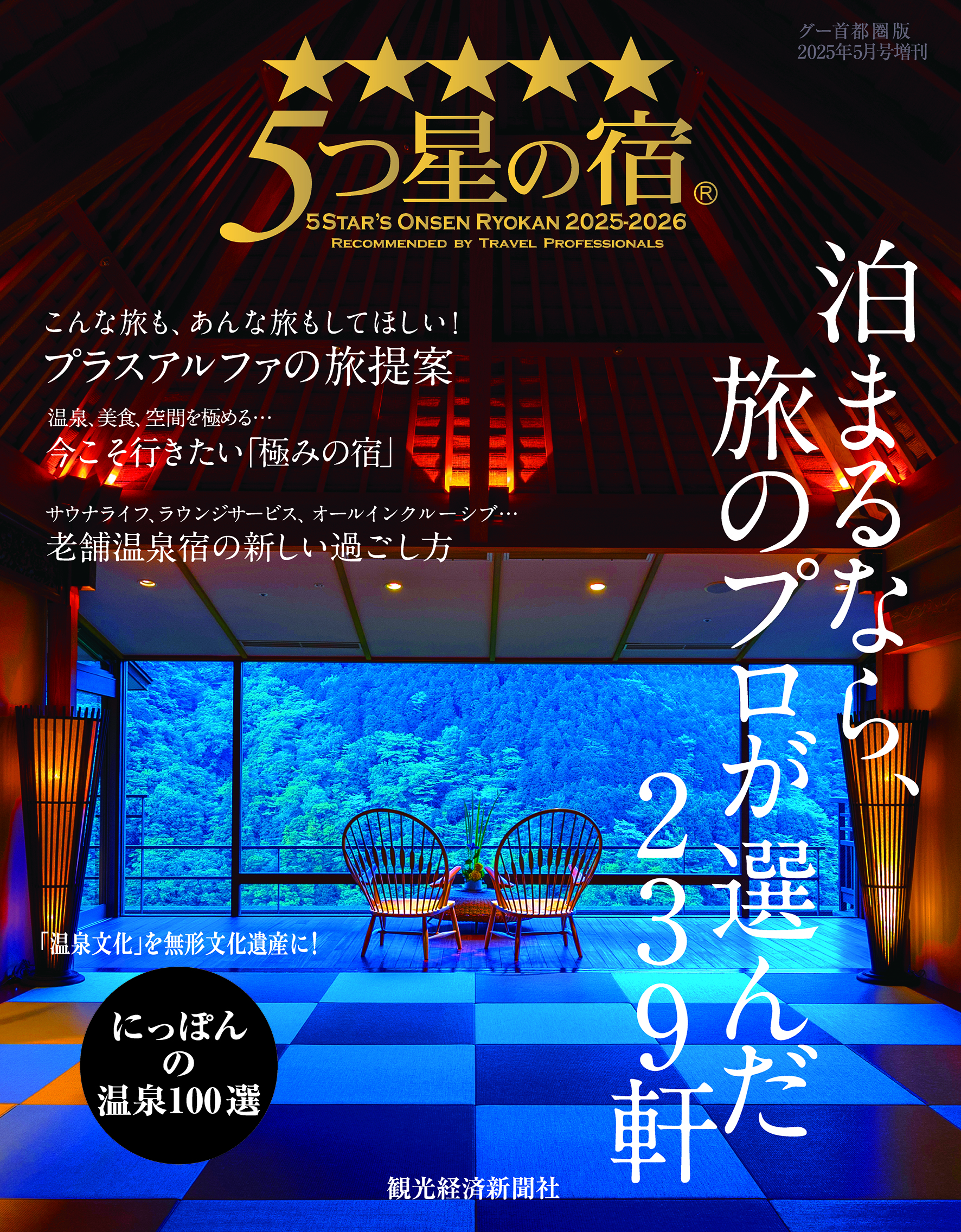前号で、厚生労働省が推奨する成人の野菜摂取の目標量が1日350グラム以上と述べた。生野菜だと両手3杯分、ゆで野菜なら片手3杯分くらいの量だと。ソレって、すごい量だ。例えば通常サイズのレタス1玉が約300~400グラムだから、1日1人1玉食べなきゃいけないワケだ。そこで登場するお助けマンこそ、淡色野菜!
淡色野菜の代表選手といえば、キャベツ・白菜・もやし・レタスなど。キャベツは豚カツの付け合わせの千切りなど生でも食すが、ポトフやロールキャベツみたいな煮込み料理にも合う。白菜は漬物以外、生食より鍋など火が通っているイメージ。もやしも炒め物が王道。レタスだって、オイスターソースでサッと炒めるとムチャうまい。淡色野菜は、加熱するとおいしいモノが多いのだ。
加熱するとカサが減ってたくさん食べられるから、1日350グラムを達成するには、淡色野菜が必須というワケ。野菜をゆでると、水溶性のビタミンCやビタミンB群、カリウムなどが流れ出てしまうといわれるが、加熱によって軟らかくなり食べやすく、しかもタップリ食べられるから、プラマイゼロともいわれる。
加熱によるメリットは、ほかにもある。唐突だが、植物って動物のように骨がないのに、ナゼしっかり立っていられるのだろう? 答えは、強固な細胞壁があるから。野菜もその固い細胞壁に栄養素が閉じ込められている状態で、この壁が栄養の吸収を阻害しているという。コイツをブチ破るには、加熱か破砕しかないらしい。つまり、火を通すかミキサーにかけるなどすれば、栄養素の吸収率が上がるそうだ。だから、スープやみそ汁の具として、またはポタージュスープなどにして野菜を食せば、汁に溶け出したビタミンCなどの栄養素も含め、効率良く吸収できるのだ。
淡色野菜に話を戻そう。レンコンやゴボウなど、淡色野菜には食物繊維が豊富なモノが多い。コレは、熱に左右されないのがありがたい。ご存じの通り、食物繊維は腸内環境を整え、悪玉コレステロールを低下させる働きがある。また、レンコンやカリフラワーはカリウムの含有量も豊富。高血圧予防やむくみ改善に役立つ。
芋類を野菜とするかしないかは、分類方法にもよるが、根菜類として野菜の一種と考える場合が多い。現在淡色野菜のことを「その他の野菜」と呼ぶらしいので、その仲間に入るだろう。里芋・長芋・ジャガイモなどは、カリウムの含有量が多い上、ビタミンCも豊富。しかも、でんぷんが熱から守ってくれるので、加熱しても栄養素が壊れにくい。
淡色野菜だって緑黄色野菜に負けちゃあいない、というのが今号のテーマだったが、結局甲乙つけ難い。それより、われわれ日本人は旬の野菜をさまざまな調理法で食せるから幸せだ。おひたし、酢の物など和食だけでなく、ポトフやラタトゥイユ、チンジャオロースなど、各国の料理を楽しめるのだから♪ 寒くなってきたから、明日はおでんにして、温かい大根をいただこう!
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。