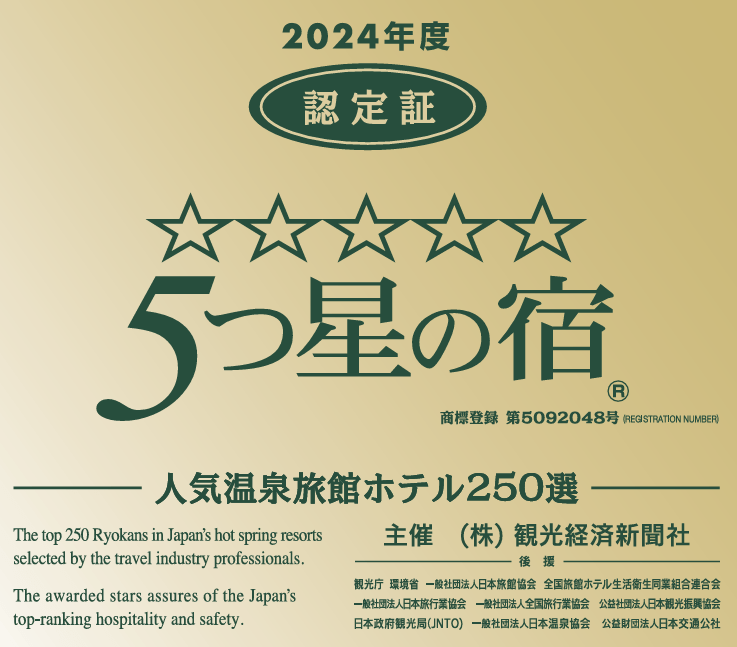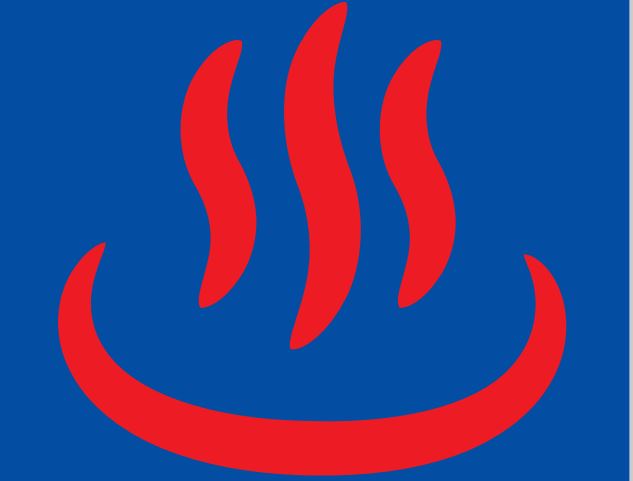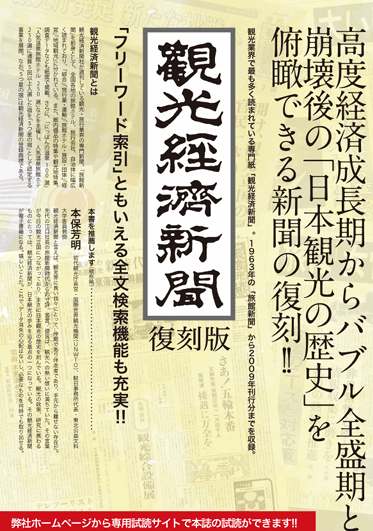火、水、土、風、鳥、と言われても、何のことやら想像がつかないかもしれない。死者を葬る方法である。私はスポーツ人類学という学問分野を専らとしてきたが、古代エジプトや古代中国のミイラと接して、人間の尊厳さを学ぶようになった。
コロナ禍は、わが国の葬儀のあり方までも変え、圧倒的に「家族葬」が増え、一般的になりつつある。わが国の法律は、火葬と土葬を認めているが、水葬、風葬、鳥葬は想定していない。遺体の扱い方は、宗教と風土に支配されていて、なぜか興味をもつようになった。紀元前6世紀のペルシャ(現在のイラン)で始まったゾロアスター教(拝火教)は、鳥葬である。タカが数羽で骨と髪の毛だけを残して食べ去る。鳥の力を借りて霊魂が天空を回って帰ってくる不滅説、チベットの密教も鳥葬を行う。詳細に紙幅がないので記述できないが、大きな鳥がいるからこそできる鳥葬だ。
風葬は、アフガニスタンのヌーリスタン地方、パキスタンのチトラル地方のカフリスタンで古くからの特殊な民族宗教のもとで行われていた。文化勲章を受章された洋画家であられる絹谷幸二画伯のお宅を訪問した折、応接間のサイドボードが風葬のひつぎだとすぐに分かった。アフリカの物らしいが、どこの国のものかは知らないとおっしゃった。素晴らしい芸術的な幾何学模様の彫刻にうっとりとさせられた。だいたいヒイラギ科の硬い木でひつぎを作り、その中に遺体を入れる。遺体は腐って、その汁がひつぎの4本足を伝わって大地に戻る。やはり骨と髪の毛だけが残る。私はアフガンの骨董(こっとう)屋で二つのひつぎを魅力的なので購入して持ち帰った。
水葬はインドのヒンズー教、半焼きの遺体がガンジス河を流れるように消える。カーストによって異なるにつけ、無常な人生の有為転変からの解放を求めたのであろうか。その昔、日本人も航海中に死去した人の遺体を麻や木綿の厚地の布に包み、重りをつけて水底に沈めて葬った。これも水葬である。マルセイユ(フランス)に行った折、日本人の古い墓地に参った。水葬された人たちの死んだ証としての墓地だが、花が供えられていた。
さて、遺体の扱い方を長々と記述してきた理由は、今夏の異常な気候で死去された人たちの遺体を、あまりにも多すぎて火葬に日数がかかったからに他ならない。コロナ禍の際も、なかなか火葬できず、社会問題となった。あの東日本大震災の時も、遺体が多くて仮の埋葬をするしかなかった。各地の火葬場は、災害を予想して大きな施設となっていないため、大災害が起こるとパンクする。その例は淡路・阪神大震災の時も、近辺の火葬場はパンクした。火葬場に積み上げられたひつぎを見て、人間の命のはかなさを感じるしかなかった。
大規模災害時に、被災自治体が犠牲者を火葬する能力が限界を超えることを経験した私たちは、周辺自治体の火葬場を利用することを考えておく必要がある。そこで、厚生労働省は、「広域火葬計画」を47都道府県全てで策定した。100年前の関東大震災でも多くの遺体の処理に困ったのである。広域的な火葬体制の構築が焦眉の急でもあった。でなければ、東日本大震災のごとく火葬が追いつかず、困り果てた。県外での火葬、仮埋葬、または土葬したりして遺体を扱うしかなかった。
自治体によるネットワークの基礎ができたとはいえ、火葬場の整備や遺体搬送車の体制づくりも重要である。各自治体は連絡調整を行い、突発的な災害を想定しておかねばならない。厚生労働省も「広域火葬計画」の策定だけではなく、当然ながら予算的措置を講じておくべきである。災害が起これば、犠牲者が出ると決めつけておき、死者の尊厳を守り通す覚悟が政府と自治体に求められる。私はスポーツ人類学者として、世界各地の死後の扱われ方を学んできた。どんな方法で見送ろうとも、人々は丁重に遺体を扱い哀悼の誠を捧げていた。これだけは共通で、人間の死を尊崇の念で悲しんでいた。遺体を物として粗末に扱ってはならぬ。