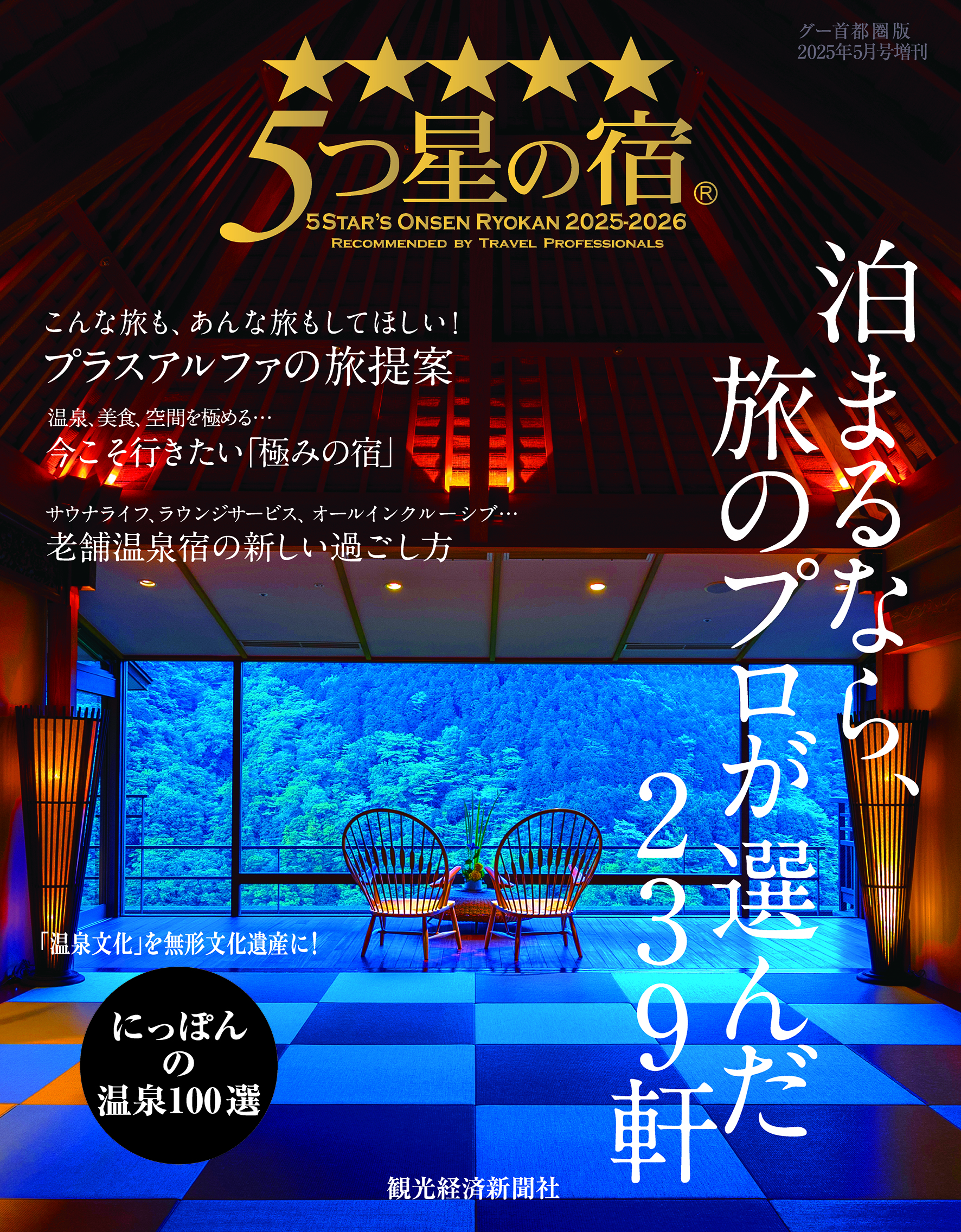そのような経緯から、「第二の市場」では、楽天トラベルや高速バスドットコムのような予約サイト(OTA)、夜行バス比較なびなどの比較サイト(メタサーチ)が大きな存在感を持つ。
これら路線は比較的長距離であるため夜行便が中心だが、夜行便では大学生など若年層が中心でウェブ予約の比率が大きく、かつ、このようなサイトが中心となり市場を開拓したので、乗客はバス事業者ではなく各サイトのリピーターとなっている。
乗客はこれらのサイトで、停留所(都内で言えば、やはり新宿と東京駅の人気が高い)や車両グレード(座席の広さやトイレの有無など)、そして運賃を比較し、自分に合った商品を選ぶ。旅館・ホテルでも同じ傾向があるが、それに輪をかけて、乗客は毎回異なる事業者、商品を選択しているように見える。
帰省需要に代表されるように、同一区間を年に何度も利用する乗客がほとんどだが、予約サイトにとってはリピーターでも、各事業者側から見ると必ずしもそうとは限らない。それどころか、各社の発着が集中する「バスタ新宿」などのターミナルで、予約サイト名は覚えているが、実際に乗車する事業者名や便名が分からず右往左往する乗客も見かける。
楽天トラベルの高速バス予約事業参入(05年末)以来、倍々ゲームの勢いで成長した「第二の市場」だが、現在では飽和状態に達している。その間に、多くの貸切バス事業者らがこの市場に参入した。あまりに大きなポテンシャルを掘り起こし漏れていた分、成長が容易な「ブルー・オーシャン」に見えたが、わずか数年間で、差異化が困難で乗客の厳しい比較検討の目にさらされる「レッド・オーシャン」に変わってしまったのである。
少なくない事業者が、レベニュー・マネジメントの趣旨を正しく理解しないまま、目先の乗車率確保のため極端な割引運賃を提示し、低価格競争に陥ってしまっている。一方、その中でも顧客囲い込みに成功し、収益性を向上させている事業者もわずかながら存在する。両者の違いを分析すると、この市場での勝ち方のヒントが見つかるはずである。
(高速バスマーケティング研究所代表)