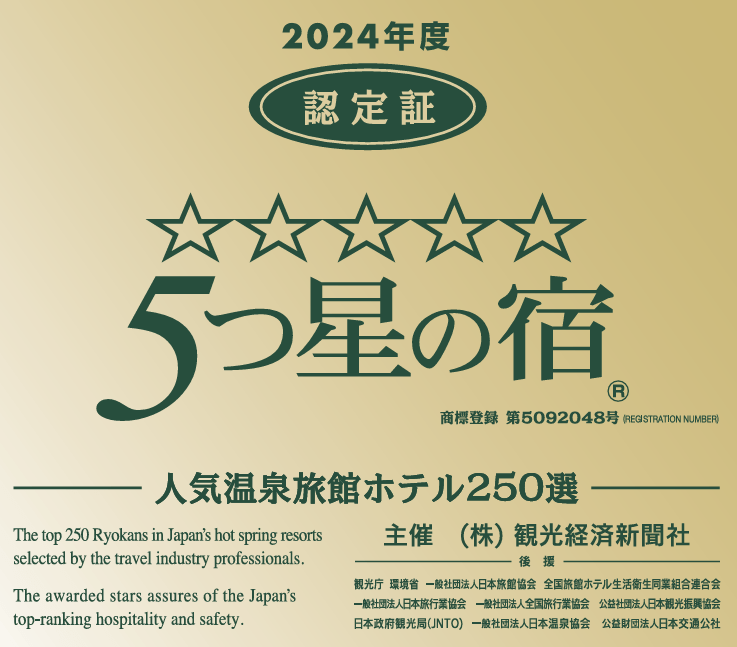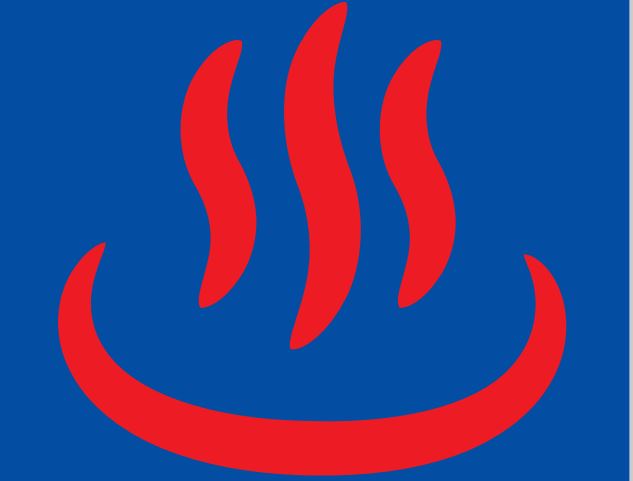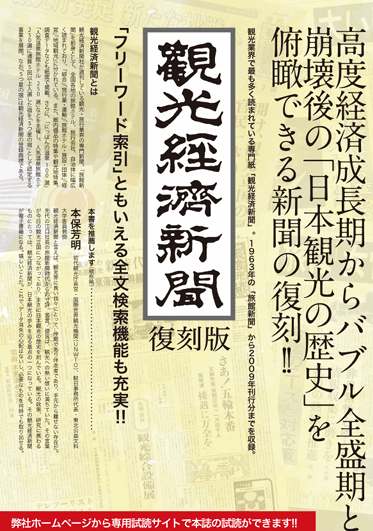小欄は、世がコロナ禍に突入して間もなくの2020年3月に急きょ、「新型コロナウイルスへの経営対応」というテーマに切り替えた。よもやこれほどの長期間に及ぶとは、その時思ってもみなかったが、気が付けばそれからすでに52回を数えることになった。正直なところ、いい加減でテーマタイトルを変えたいと自分でも思っているが、コロナ禍が収束し切っていないフェーズで、まだこの看板を下ろすわけにもいかない。
本テーマは、「新型コロナウイルスへの経営対応」↓「『…頼みの経営』から抜け出す」↓「そのために行うべき七つの『原理原則』」↓その一つ「品質の向上」↓「料理の品質」という流れで書いている。
さて、前回は料理の「提供される状態」―いわば出口の品質に意を注ぐことの大切さについて述べた。今回はその対極―つまり入り口となる「献立の設計」について考える。問題としたいのは満腹感だ。
提供する料理のうち、魚の骨などを除く「食べられるもの」全部の重さを「可食重量」と呼ぶ。旅館などの会席料理では、しばしばこれが1・3~1・5キロほどになる。食べ物のおよそ8割が水分とすると、量としてもほぼそのまま1・3~1・5リットルぐらいと捉えてよかろう。一方で胃袋の容量は、日本人の成人男性で平均約1・4リットル、女性で約1・3リットル、最大膨張時で2リットルぐらいだそうだ。かくして胃は、ほぼパンパンに膨らんだ風船のようになる。
近ごろでは、「量で勝負」のような料理の打ち出し方は影を潜め、品数も少なくなる傾向にあるが、それでも食事終盤のころには「もうお腹いっぱい、食べられない」ということがしばしばある。
ところが…原価もたっぷり掛かっているであろう肉料理などは、一般に終盤近くに組み込まれている場合が多い。一番の「ご馳走(ちそう)」が、もはやお腹に入らないという、なんとも皮肉なことになってしまう。
脳の満腹感をつかさどる「満腹中枢」は、食事開始後15~20分で刺激されるそうなので、だいたいそのころから空腹感は一段落してくる。コース料理なら2~3品目あたりだろうか。つまりそれ以後は、カロリーとしての食を求める生理はひとまず収まる。
「空腹にまずいものなし」と言う。食べ物を「おいしい」と感じる度合いは、空腹感と「正の相関(一方が高まるほど他方も高まるような関係)」にあるのだ。逆に言えば、満腹感が高まるにつれて「おいしさ」は減衰していく。
旅館商品の品質は、最終的にお客さまの満足感によって測られる。どんなにがんばって良いものを出したつもりでも、お客さまに「おいしい」と感じてもらわなければ意味がない。
取り上げたのは満腹感という物差しだけだが、とりあえず言えるのは、まず料理全体の量、さらにその構成=出す順番に見直す余地がありそうだ、ということである。そのような観点でもう一度吟味しよう。序盤でおいしさを印象づけられるか、主役級とする品の「出番」が適切か、終盤に重たいものが集中しないか…。
書き出した献立表や、料理を並べて見るだけでは、料理構成の良し悪しは判断できない。しかるべき時間をかけて食べてみることが、「料理品質の入り口」を管理する重要なプロセスだ。
(リョケン代表取締役社長)