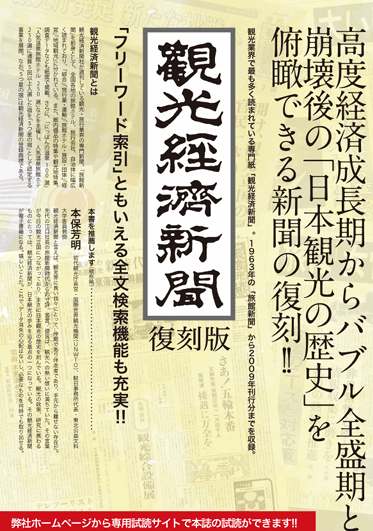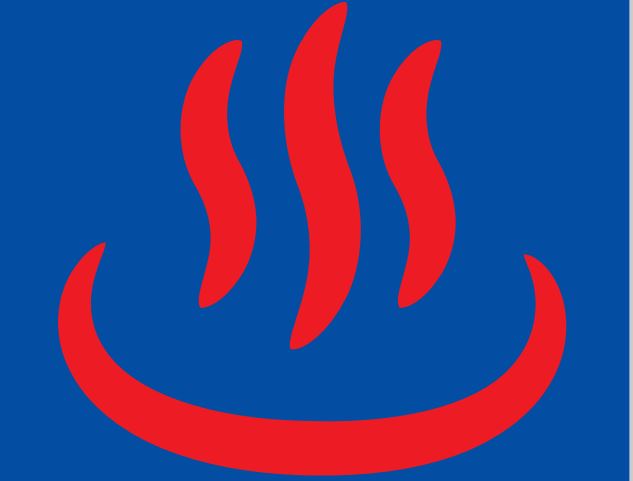山中教授
コロナ禍で、宿泊産業・料飲産業は大きな打撃を受けている。ホテルにおけるバイキング=ブフェスタイルも、一時は存続の危機に直面した。この変革を中心に、新たな価値創造について考えたい。
バイキングという言葉が「食べ放題」の代名詞となって久しいが、この言葉は、もともと帝国ホテルが、1958(昭和33)年にデンマークから料理人を招いてオープンしたブフェレストラン「インペリアルバイキング」に由来する。名称は社内応募で決まったのであるが、当時上映されていた映画『バイキング』の豪快な食事シーンにヒントを得たという。バイキングという言葉にブフェの意味はないが、このネーミングは、ブフェスタイルの浸透に大きな役割を果たしたと言える。当初「好きな料理を好きなだけ選べる」という全く新しいビジネスモデルは、現場で強い抵抗にあった。プロ意識から、「お客様自身に料理を盛りつけさせて、テーブルに運ばせるとは何事だ」と考えたのだ。しかし、「インペリアルバイキング」は話題となり、大人気を博すようになった。
それ以来、街の飲食店では焼肉やしゃぶしゃぶ、ケーキ、サラダバーなどの単品バイキングが広まっていった。ホテルのブフェレストランでは国交樹立の周年記念などをきっかけに、各国大使館や本国の農務省の依頼でその国の料理や文化を紹介するフェアが開催されて、海外の食文化発信の一翼を担うようになった。しかし朝食バイキングは、全く別の進化を遂げていく。観光目的で宿泊する宿泊客の朝食の楽しみとして、シティ、リゾート、ビジネスホテルを問わずバイキングが定番になっていったのである。さらに旅館にも広がっていき、地元名産の食材を使ったメニューを工夫する宿泊施設も現れた。
しかしコロナ禍で、バイキングスタイルは窮地に立たされた。実はバイキングの受難はこれが初めてではない。近年では2017年、惣菜店のポテトサラダを食べた女児がO-157に感染して死亡、惣菜を取り分けるトングが感染源とされた。しかしこの時には、ホテルは衛生管理を強化、すなわちトングを消毒して、頻繁に交換することで、難局を乗り切った。
現在、帝国ホテル東京では、社員から募ったコロナ禍対応のアイデアをきっかけに、新たなスタイルを打ち出している。席数を100席に半減させ、オーダーバイキングを導入したのである。注文は、ゲストが自らタブレットで行う。ブフェ台を一部残し、調理の様子はライブモニターで楽しめる。プロジェクトメンバーの山下圭子支配人は、2021年2月、日本ホテル協会主催の「ホテルウーマンフォーラム」に登壇し、『コロナ禍によって生まれた新たなバイキングが、調理とサービスの垣根を取り払った』と語った。オーダーバイキングへの転換で、調理スタッフもゲストに料理を届けるようになり、それまで調理台を挟んで会話していたゲストと対面することになった。ゲストとスタッフの価値共創が実現したのである。
また品川プリンスホテルの「パプナ」はバイキングをエンターテイメントに変えた画期的なブフェレストランとして知られるが、席数を270席と約3割減に抑え、ワゴンサービスに切り替えた。
かたや朝食バイキングでは、コロナ禍に対応し、料理を小皿に分けたり、利用客にトングや手袋などを提供した上で、料理卓が密にならないよう工夫している場合が多い。その例として、東京ステーションホテルの「アトリウム」を挙げたい。同ホテルではトングを廃止し、全ての料理を小皿で提供しているが、料理が彩りよく盛りつけられた数々のガラス容器が燦然と輝き、華やかなディスプレイとなっている。
その「アトリウム」で2021年4月、旅行作家の山口由美氏が主催するイベントが開かれた。ステージは透明のパティションで仕切られ、完璧な対策を取っていた。しかし驚いたのはイベント後の館内見学のときだった。それまで料理をサーブしていたレストランのスタッフが先頭に立ったのである。館内見学は、通常宿泊系のスタッフが行うものだが、聞けば、コロナ以前からランチの団体のゲストに頼まれるうちに、自然と案内するようになったという。笑顔と張りのある声、気の利いたトーク、藤崎総支配人の肝煎りで、社内コンテストも開催されているとのことだった。
さまざまなことがきっかけとなり、新たな価値が創造されることがある。コロナ禍で生まれたサービスで、コロナ後も残っていくものも少なくないのではないだろうか。事実、オーダーバイキング、ワゴンサービスや小皿での料理の提供は、いずれもフードロスを減らし、SDGsに貢献する副次的効果を上げている。コロナの夜が明けたら、インバウンド再来を願って、観光地のホテルや旅館が朝食バイキングを核に、海外の姉妹都市などとのコラボレーションによるフードフェアを地域全体で開催してはどうだろうか。そんなことを思わせてくれた、ホテルレストランのバイキング=ブフェ再生への挑戦に喝采を贈りたい。

山中教授