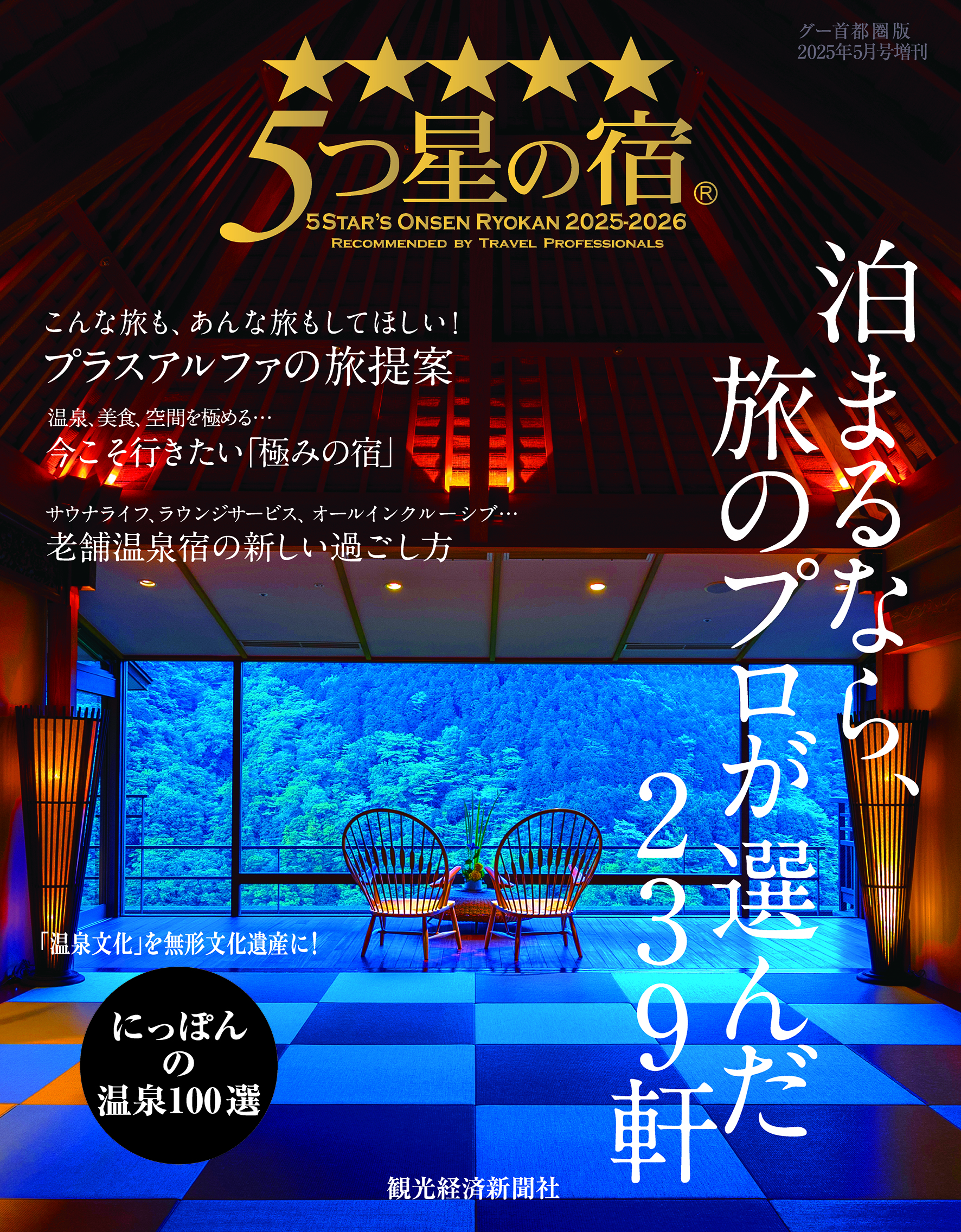小田急トラベル社長 小柳 淳氏
電鉄系旅行会社の役割
私たちは「地場産業」 地域社会とは共存共栄
──都心に9カ所、小田急沿線に20カ所の店頭型店舗と団体営業店舗を展開している。箱根方面の販売比率はどのくらいか。
「総取扱額の内訳は国内旅行が60%、海外旅行が20%、小田急電鉄の乗車券類の受託販売が20%。国内旅行のうち25%が箱根・伊豆方面の旅行商品だ」
──高級住宅街で有名な成城の旅行センターには、富裕層の顧客が多いのか。
「土地柄、クルーズなどの高額商品や海外旅行はよく売れる。実は、当社が企画、実施する地域発着のバス旅に参加される方も多い」
──地域に密着している。
「全国展開している旅行会社ではないので、宿の経営者の方々とは『お互いに地場産業ですね』という会話をよくする。団体営業も沿線地域密着で、幼稚園の遠足なども手がけている」
──小田急グループはバス会社、宿泊施設も数多く経営している。
「小田急グル—プはハード部門が多いが、その中で私たちトラベルは旅行の企画、販売というソフトを担当している」
───小田急トラベル協定旅館連盟の組織はどのようになっているのか。
「箱根は箱根湯本、宮ノ下、強羅、仙石原、芦ノ湖の5地区に分かれている。伊豆も伊東、伊豆東、伊豆南、伊豆西、伊豆中の5地区。さらに湯河原地区、熱海地区がある。全12地区の施設総数は約200軒。各地区に会長がいて、総会は地区ごとに行っている。箱根の5地区に限っては全山連絡会という組織を置いている」
──4月に箱根湯本駅の中に企画仕入れセンターを開いた。
「15年位前にコスト削減の一環で現地の仕入れ拠点を閉鎖し、以来、東京・代々木の本社で商品造成をしていた。私たちは地場産業であるのに地元との距離感が出てしまっていた。そこで4月11日に箱根伊豆企画仕入れセンター『小田急旅ひろば』を箱根湯本駅構内に開設した。一般顧客向けの箱根湯本営業所とは別のスペースを確保。箱根・伊豆担当も増員した。旅館ホテルとフェイスツーフェイスで相談、打ち合わせをし、商品造成まで行う場所だ。当方から各宿に出向くのが基本だが、近所なので先方が気軽に立ち寄っていただくことができる」
「理屈理念やマーケティングの難しい話も数多あるが、『観光』は本質的には人と人とのつながりと信頼感で成り立っていると思う。特に私たちは地場産業なので、景気が悪いからこの地域からは撤退、などという選択肢はありえない。箱根、伊豆で生きていくしかない。そういう思いも込めて小田急旅ひろばと名付けた。人と人が集い、よりよい商品を作っていく基地としたい」
──ネット販売の展開は。
「一般的に、ネット販売の旅行商品には速い、安いという特徴がある。確かに安さも重要だが、全てではない。価格競争に陥ると、擦れっ枯らしの商品になってしまう危険性がある。ネットでも店頭でも中身の伴った、適正価格の旅行商品を企画、販売していく」
──ネット販売の実績は。
「12年度実績で言うと年間取扱額206億円のうち7億円がネット販売だった。前年比で9%伸びた」
──インバウンド客誘致への小田急グループの取り組みは。
「箱根には富士山の見える風景、芦ノ湖、そして温泉がそろっている。東京からも近く、訪日外客にアピールしやすい。99年、私は小田急電鉄の課長として新宿駅構内に『小田急外国人旅行センター』を開いた。またグループ内連携をとるため、09年に『小田急インバウンド協議会』を設立した。小田急電鉄のデータでは台湾、香港、韓国からが常に多い。最近はタイ、シンガポール、マレーシアからが伸びている」
──小田急トラベルの役割とは。
「沿線地域の方々に良質な旅行サービスを提供すること、箱根を商品化して売ること、ロマンスカーを商品化して販売すること、の三つだ」
「一過性の儲けや、叩き売りには走らない。これが電鉄系中堅旅行会社の良いところだと思う。地場産業なので地域社会とは共存共栄だ。地域が発展しないと我々も輝けない」
【こやなぎ・じゅん】
81年、小田急電鉄入社。05年旅客サービス部長、08年執行役員CSR・広報部長。12年6月、小田急トラベル社長・小田急箱根ホールディングス取締役に就任。他に、08年1月、YOKOSO JAPAN大使(現VISIT JAPAN大使)就任。09年5月、小田急インバウンド協議会設立。54歳。