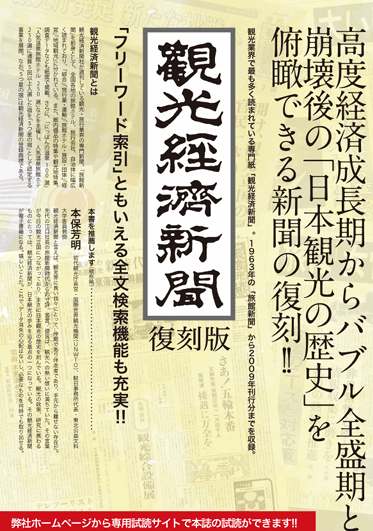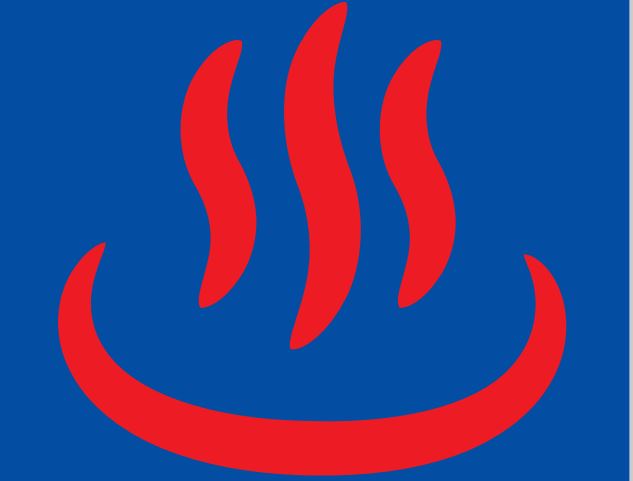工学的発想でサービスを組み立てると、いかに手間をかけずに生産性を上げていくかに発想が偏りがちになる。「省労力」し「最適化」、あるいは「自動化」することがサービスの向上につながるという論理だ。
回転寿司の「くら寿司」は、サービス産業生産性協議会による2016年度顧客満足度調査のレストランチェーン分野で1位を獲得した。4大添加物を一切使用せず、1時間に3600貫を握るのは自慢の「寿司ロボット」だ。皿にかぶせるフードには回っている時間を管理するICタグを埋め込み、設定時間を経過した寿司は即座に廃棄するという徹底ぶりだ。
「料理は作り立てがおいしい」という考え方にのっとれば、たとえ機械が作ったものであっても、調理後、すぐに提供されれば、それは「おいしい料理」ということになる。
だが本当に、外食における「おいしい料理」とは、衛生的で味が均一で整ってさえいればよいのだろうか。たとえ、回転寿司のような日常の延長であっても、そこには外で食事をするという非日常的演出が求められる。
確かに「くら寿司」では、非日常を感じさせる斬新なアイデアが随所に仕掛けられている。注文はタッチパネルで行い、注文した皿が近づくと音と画像で通知される。客が、店員と接することはない。そして、究極の工学的発想が、同社自慢の特許取得「皿カウンター水回収システム」だ。
レーンとテーブルの間に設けられたステンレス製の投入口に空の皿を流し込むと、皿は水に流されながら洗い場まで運ばれ洗浄される。皿を投入するごとに枚数がデジタル表示され、5皿投入するたびにゲームが始まり当たればガチャ玉がもらえる。
後学のために「くら寿司」に足を運んだが、皿を流し入れる音や注文品が到着する音、そして、子どもがガチャ玉をあてようと躍起になる騒ぎ声に正直、軽いめまいを覚えた。
五穀豊穣の神を祀る日本人は食べ物を大切なものとして扱い、それらを使った料理を、感謝を込めていただく。それが食事である。よって、感謝の込め方として、器の扱い方や箸使いといった日本独自の作法が存在するのだ。言うまでもなく回転寿司の皿も「容器」ではなく「食器」である。
外食だからこそ身に着くマナーや常識があるはずだ。業務上の省力化や自動化がサービス産業の課題であることは確かだが、食事中の客に空の器を投げ入れさせるシステムは、日本の食事の作法や文化を根幹から揺るがしかねない危険性を孕んでいるとも言えよう。
工学的発想は有益ではあるが、日本のもてなしは文化的背景なくしては成立しないことも忘れてはならない。