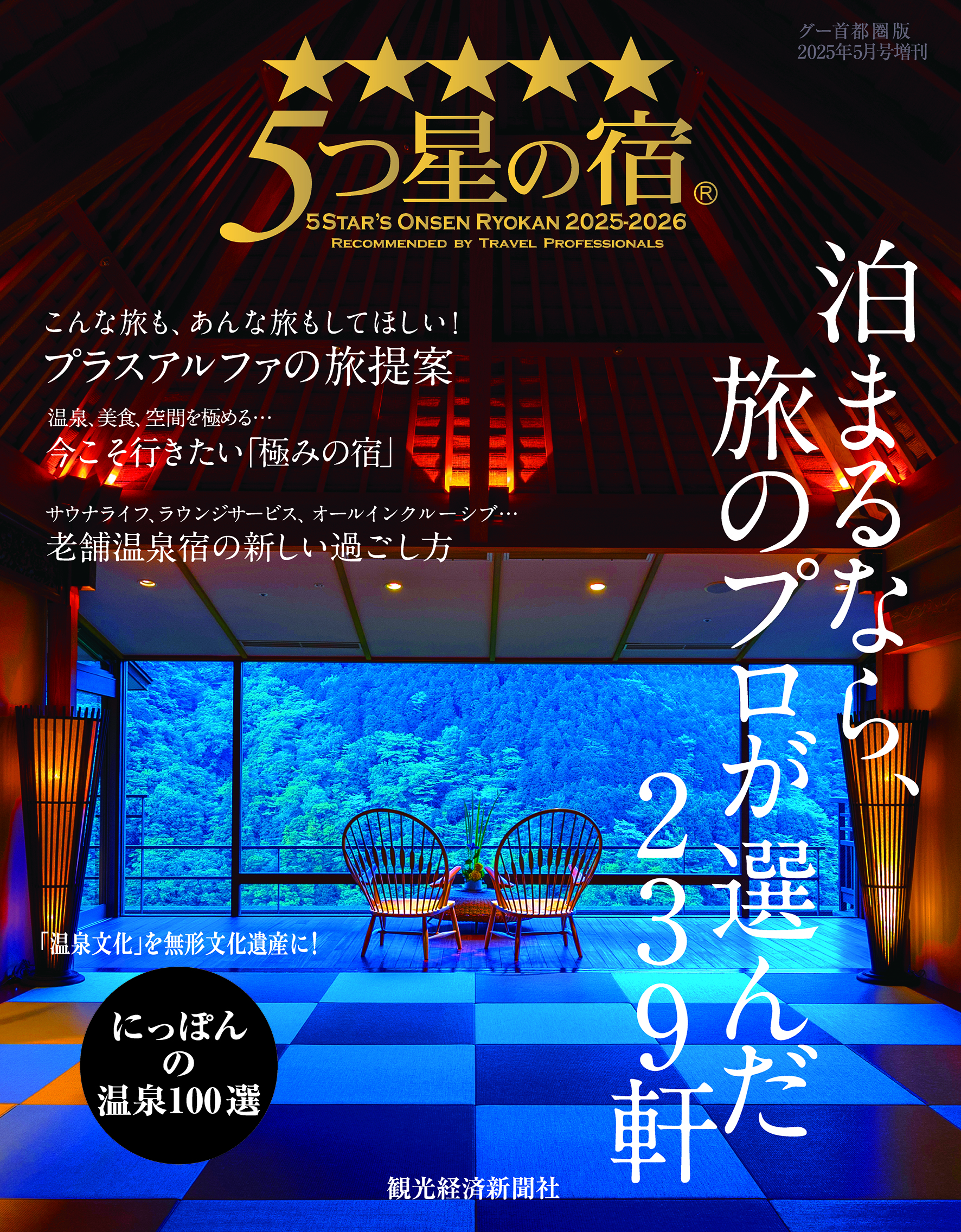橘田氏
すそ野を広げ、環境構築を
地方創生を図る手法の一つとして「サイクルツーリズム」に関わる取り組みが各地で以前にも増して注目されている。これとエコ、健康志向、そしてSDGsといった環境関連のワードがシナジーとなって加速させ、一層の盛り上がりを見せている。
サイクルツーリズムとは、旅のスタイルが多様なのと同様に多種多様で、▽自転車に乗る▽レースやイベントに参加する▽大会を観戦する▽旅行先で観光の道具にする―など、旅行者目線からでも自転車が主目的か、観光の道具かによって大きく違う。
これら旅行者のニーズを受け、地域の観光資源を生かし、▽サイクリングルートを設定▽サイクリングイベントを実施▽交通利便性を生かし、国際大会を誘致▽駅や観光地にサイクルステーションやレンタサイクルを設置▽駐輪場設置―など、さまざまな取り組みが行われ、また、専用列車や専用バスを運行し、サイクリングツアーを企画するなど、自転車の健康的でエコなイメージもあって各地でこうした取り組みが実施されたり、計画されたりしている。
これらが複合的に絡みあって構成されている総称がサイクルツーリズムだと言ってよいのではないか。ここでのターゲットは国内が主だが、見逃せないのが訪日旅行者、すでに一部地域では動きが見られるが、彼らのサイクルツーリズムへの興味・関心は想像以上だ。こうした動きを見越した「しまなみ海道」「琵琶湖」「霞ヶ浦」「宇都宮」「さいたま」などは自転車の街としてブランディングに結果を出していると言える。
こうした中、国土交通省は自転車活用推進法に基づき「自転車を通じて優れた観光資源を有機的に連携するサイクルツーリズムを推進し、地域創成を図るためナショナル・サイクルルート創設」を発表、現在6ルートが認定され、「今後拡大していく」(自転車活用推進本部)としている。
とはいえ、全国的に自転車を取り巻く環境はまだまだ多くの課題がある。そうした課題を地域が官民一体となり解決に取り組み、地元の理解を得て推進することが地方創生には欠かせない。
ナショナル・サイクルルートに限らず、今後サイクルツーリズムの取り組みはより活発になるだろう。そこで大事なのはハードルを一機に上げすぎないこと、官民一体で、地域の理解・協力を得ながらサイクルツーリズムの裾野を拡げられるような取り組みと環境を構築していくことが肝要ではないだろうか。地方創生に向けた取り組みでサイクルツーリズムの持つポテンシャルは高い。

橘田氏