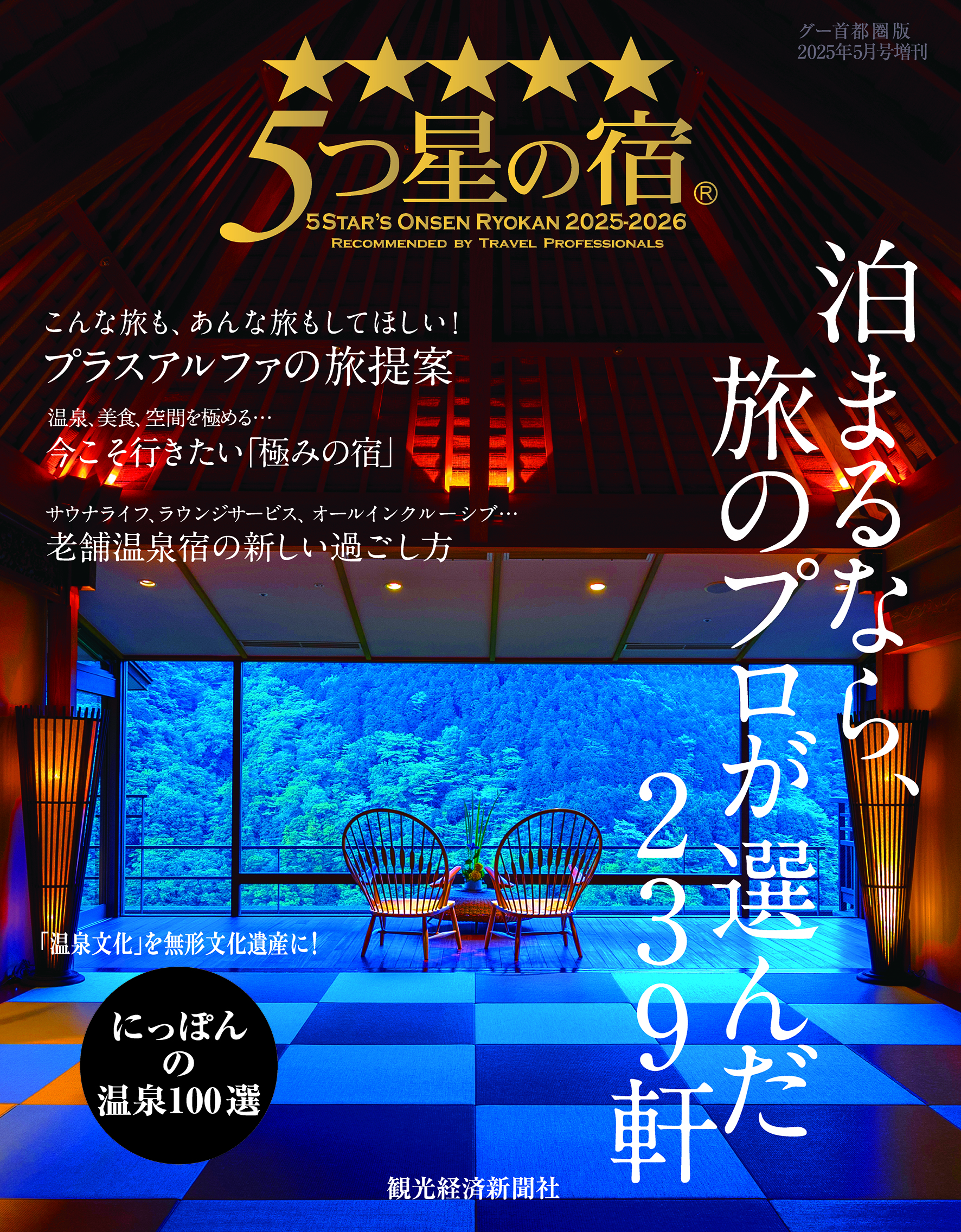タヒチ観光局 最高経営責任者(CEO)ジャン‐マーク・モスラン氏
レスポンシブルツーリズム標榜 孤島は保護と同義語
――日本ではオーバーツーリズム対策が急務となっている。フランス領ポリネシアのタヒチではサステナブルツーリズムにどのように取り組んでいるのか。
「コロナ・パンデミックを経て、仏領ポリネシア政府の観光政策は、インクルーシブでサステナブルな開発へと方向転換した。ツーリズム開発では、地元住民を最重要視し、経済的な利益は均等に分配されなければならない。また、ツーリズム消費と提供されるサービスは、仏領ポリネシアの環境規範を順守するものでなければならない、というものだ」
「具体的には、電力の75%を2030年までに再生可能エネルギーにすること、22年1月から実施している使い捨てプラスチック袋の禁止、クルージングにおける乗客数700人以下のローカル船の優遇などだ。特に、観光に関して量より質を重視するボラボラ島では、島に入港できるクルーズ船の数を制限している。22年1月時点で、入港できる船を最大乗客数1200人までとし、乗客定員が3500人以上のクルーズ船は、給油や補給などの目的でしか寄港できないことになっている」
――タヒチが標榜(ひょうぼう)する「レスポンシブルツーリズム」とは何か。
「『レスポンシブルツーリズム』では、人々が生活し、訪問するための良い環境を創造することを目的とし、観光活動の影響に対する責任を負う必要性を重視している。また『インクルーシブツーリズム』とは、観光産業におけるさまざまな当事者間の連携やコンタクトを促進し、民間セクターと当事者、あるいは当事者間のパートナーシップを形成するアプローチのこと。地域経済を活性化し、地域社会の参加を促すものだ」
――タヒチ全体の経済規模と観光産業の占める割合は。
「タヒチは、五つの列島とそれに連なる118の島々で構成されている。500万平方キロメートルの面積に28万3147人の人々が暮らす。失業率は9%に過ぎない。22年のGDPは、前年比6.3%増の60億米ドルだ」
「観光産業はタヒチのGDPの12%を占めている。就業者数全体の16%に当たる1万1千人が、直接雇用で観光産業に従事している。また、推計で3万3千人が観光関連収入で生計を立てている」
――タヒチを訪れる観光客の国別構成は。
「2007年から19年まで、1位米国、2位フランス、3位日本だった。19年のインバウンド観光客総数は23万6642人。コロナ禍で、20年7万7017人、21年8万2546人と落ち込んだが、22年は21万8750人まで回復した。23年は22万5千人と予測している」
――日本人観光客の回復状況は。
「23年1~9月の累計で389人。全体の0.2%で14位となっている。1位の米国は、8万3317人で全体の42.6%、2位のフランスは、6万337人で同30.9%だ」
――日本市場の特徴をどのように分析しているか。
「コロナ禍の18年時点での分析になるが、観光客全体の平均滞在日数が16日間なのに対して、日本人は7日間。1人当たりの現地消費額は、全体が2650米ドルで、日本は2425米ドル。つまり日本人観光客は1日当たりの現地消費額が平均値の倍以上となっている」
――航空座席供給数、ホテル客室数の制約に環境配慮などが加わると受け入れ可能な観光客数は限られてくる。
「コロナ禍を経て、私たちのハンディキャップは逆に私たちの強みになった。孤島という地理条件は今や保護と同義語。タヒチの島々を訪れる費用を考えると、タヒチは理想的な『スローツーリズム』の目的地ではないだろうか。大勢の観光客でごったがえす場所から遠く離れ、旅行者は本質を再発見することができる」

ジャン‐マーク・モスラン ニューカレドニア島出身。仏ニースのエコール・ホテリエ・ド・ニース(ホテル・ケータリング・ツーリズム・マネジメントの学校)を卒業後、欧州、アフリカ各所でシェラトンホテルの開業に従事。フィジーでのリゾート経営に転じ、31歳でシャングリ・ラの総支配人に就任。その後タヒチに渡り、ビーチコマー・インターコンチネンタルを手がける。2017年5月、「ニューカレドニア観光開発」の立ち上げに招集され、3年間ニューカレドニア観光局をけん引。20年5月、新型コロナのパンデミックのピークを機にタヒチに戻りタヒチ観光局のCEOに就任。仏領ポリネシアの持続可能な観光委員会のメンバーとして、持続可能な観光戦略の行動計画を推進している。エア・タヒチ・ヌイ取締役も兼務。
【聞き手・kankokeizai.com編集長 江口英一】