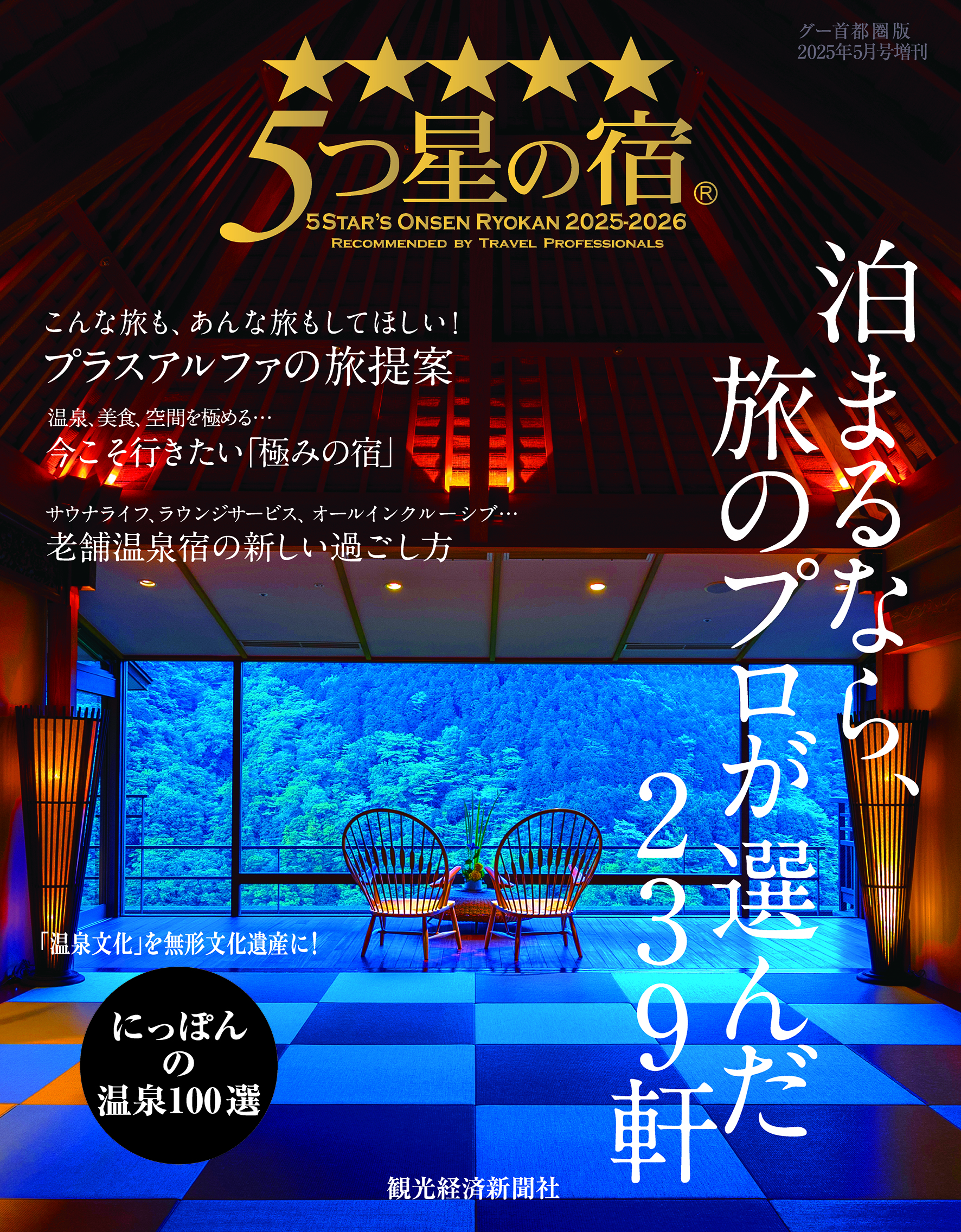来年6月の「民泊新法」(住宅宿泊事業法)施行に先駆けて、国家戦略特区内での民泊、いわゆる「特区民泊」に取り組んでいる自治体がある。その第1号が東京都大田区だ。昨年1月に始まったその取り組み。現在どうなっているのか。
日本の首都東京の玄関口、羽田空港を擁する大田区では、外国人旅行客の増加に伴う宿泊施設不足の解消や、滞在客の増加による地域経済の活性化を狙いに、「国家戦略特別区域法の旅館業法の特例」を活用。旅館業法の適用を受けず、区が定める条例で住宅を宿泊業に活用できる特区民泊事業(正式名称=大田区国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)を昨年1月29日にスタートさせた。
大田区生活衛生課によると、現在、特区民泊施設に認定されているのは45件、225室(10月末日時点)。施設は戸建てが8、その他がマンションなどの共同住宅だ。
民泊施設は月2、3件のペースで増えているが、「事前に相談があった数に比べると、若干少ない印象」と大田区生活衛生課の三井英司課長。特区民泊に関する法律が制定された2013年12月以降、旅館業法施行令で簡易宿所営業の要件が緩和されたり、民泊新法整備の動きが活発になってきたりしたため「様子を見ようという事業者が増えたのかもしれない」と同課は分析する。
ただ、「民泊新法の整備が一段落したことで、特区民泊についてもこれからいろいろと動きが出てくるかもしれない」と期待する。
なお、同区の特区民泊は区域計画により、旅館・ホテルと同様、住居専用地域では行えない。区民の安寧な生活を守るためで、変更の予定は現時点ではないという。
同区の特区民泊への滞在者数は内閣府の集計で合計1129人、うち外国人は755人となっている(6月末時点)。区では数などの調査はしていないが「外国人が観光やビジネス、あるいは親族が来日する時に利用しているという話を聞く。日本人も出張や就職活動、在外邦人の一時帰国の際に利用しているという話を聞いている」という。
2年弱の特区民泊事業の成果については「民泊はここ2、3年、違法民泊の問題もあり悪いイメージが先行していた。ただ、これまで大きなトラブルもなく事業が進められている。大田区が前例を作るわけなので、そこでトラブルが多ければ、やはり民泊は駄目だとなってしまう。しっかりとルールを作り、運営をすればそれほど問題はないことがある程度実証されたのが大きい」と強調する。
区民から寄せられた苦情は「夜中に話し声がする」「外で騒いでいる」という数件。いずれも民泊施設の管理会社に連絡をするなどして、問題を解決している。ごみ出しのトラブルはこれまで発生していない。
取り組みの課題については「民泊の最低利用日数」を挙げる。区条例では6泊7日以上としており、1泊2日などの短期滞在はできないことになっている。国家戦略特別区域法施行令で、特区民泊の利用期間を「(6泊)7日から(9泊)10日までの範囲内において自治体の条例で定める期間以上」としていたからだ。
ただ、昨年10月31日に同施行令の一部が改正。利用期間の「(6泊)7日から」が「(2泊)3日から」に緩和された。
これを受けて大阪府など他の国家戦略特区は、利用期間を2泊3日以上に設定。大田区は現状の6泊7日以上を変えていないが、「参入しやすい、利用しやすい制度にする必要はあるだろう」と、条例の改正に含みを持たせている(後に2泊3日への短縮の意向を発表)。
社会問題となっているヤミ民泊。区ではどれだけ把握をしているのだろうか。
同課によると、特区民泊を始めた昨年1月から今年10月までに26件のヤミ民泊に関する摘発や苦情が来ている。「場所が特定できているところについては指導を行い、23件は辞めてもらった」と同課。課では仲介サイトから物件が削除されているところまで確認をしている。
残りは物件の所有者が外国人などで、いまだ連絡がつかないケースがある。「今後、取り締まりを強化しなければならない」と同課。
既存の旅館・ホテルとの関係はどうか。「民泊事業者が旅館・ホテル事業者と連携をして、民泊利用者の現地での本人確認や、鍵の受け渡しを旅館・ホテルにお願いしているケースがある」。
ルールに基づいた特区民泊事業について、既存の旅館・ホテルや旅館・ホテル組合も理解をしているとの認識だ。
来年6月15日の施行が決まった民泊新法。既に特区民泊を推進する大田区の対応はどうか。
「(新法に対応する)制限条例を何らかの形で設けたいとの意思はある。特区民泊の実績も踏まえてどのような対応をするか、今後検討することになるだろう」としている。