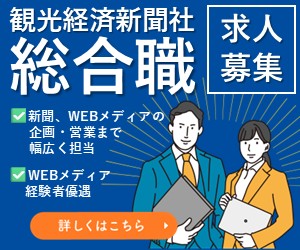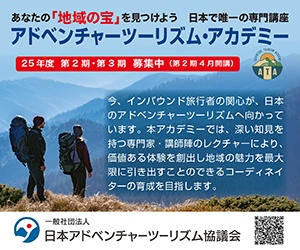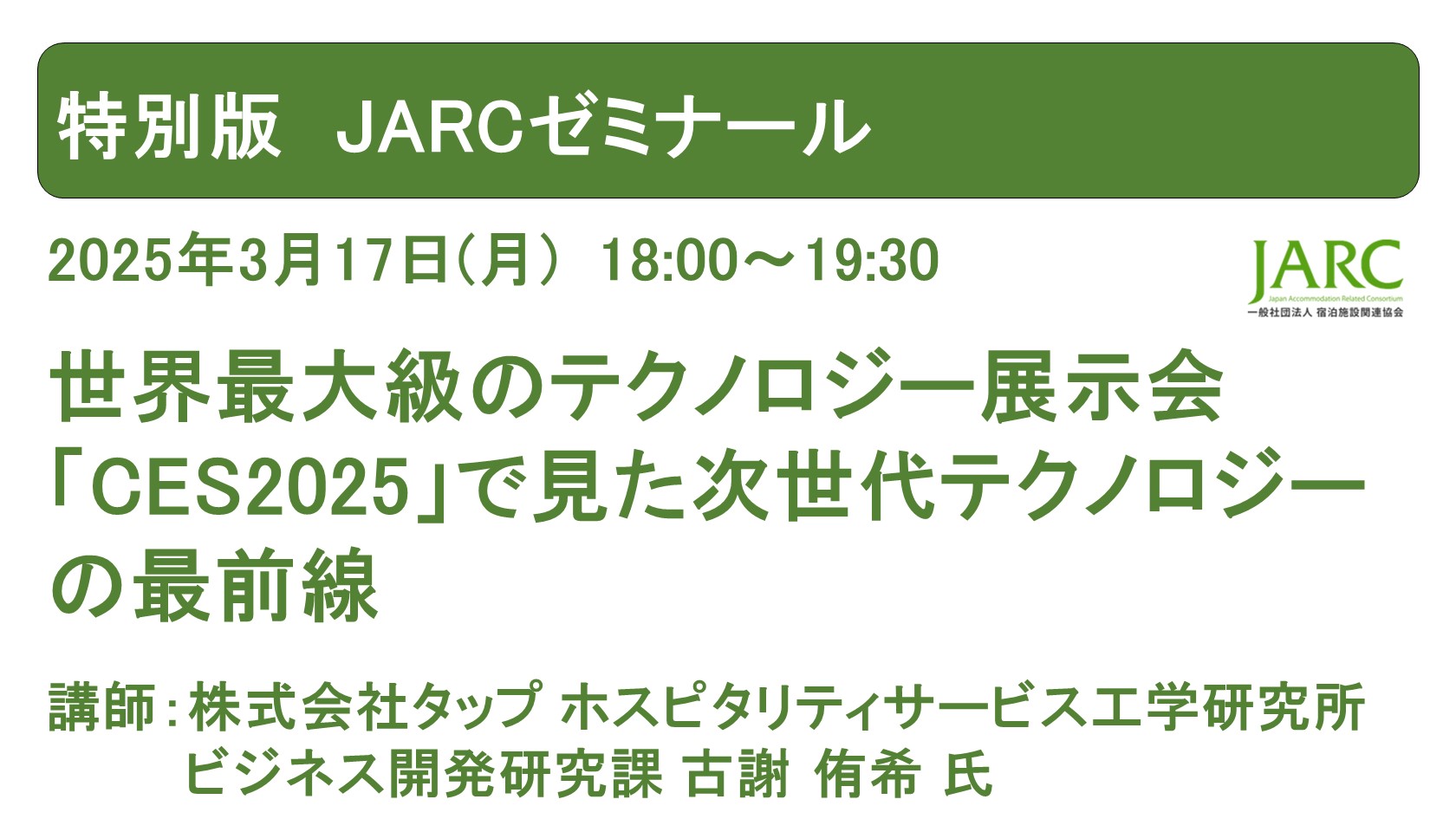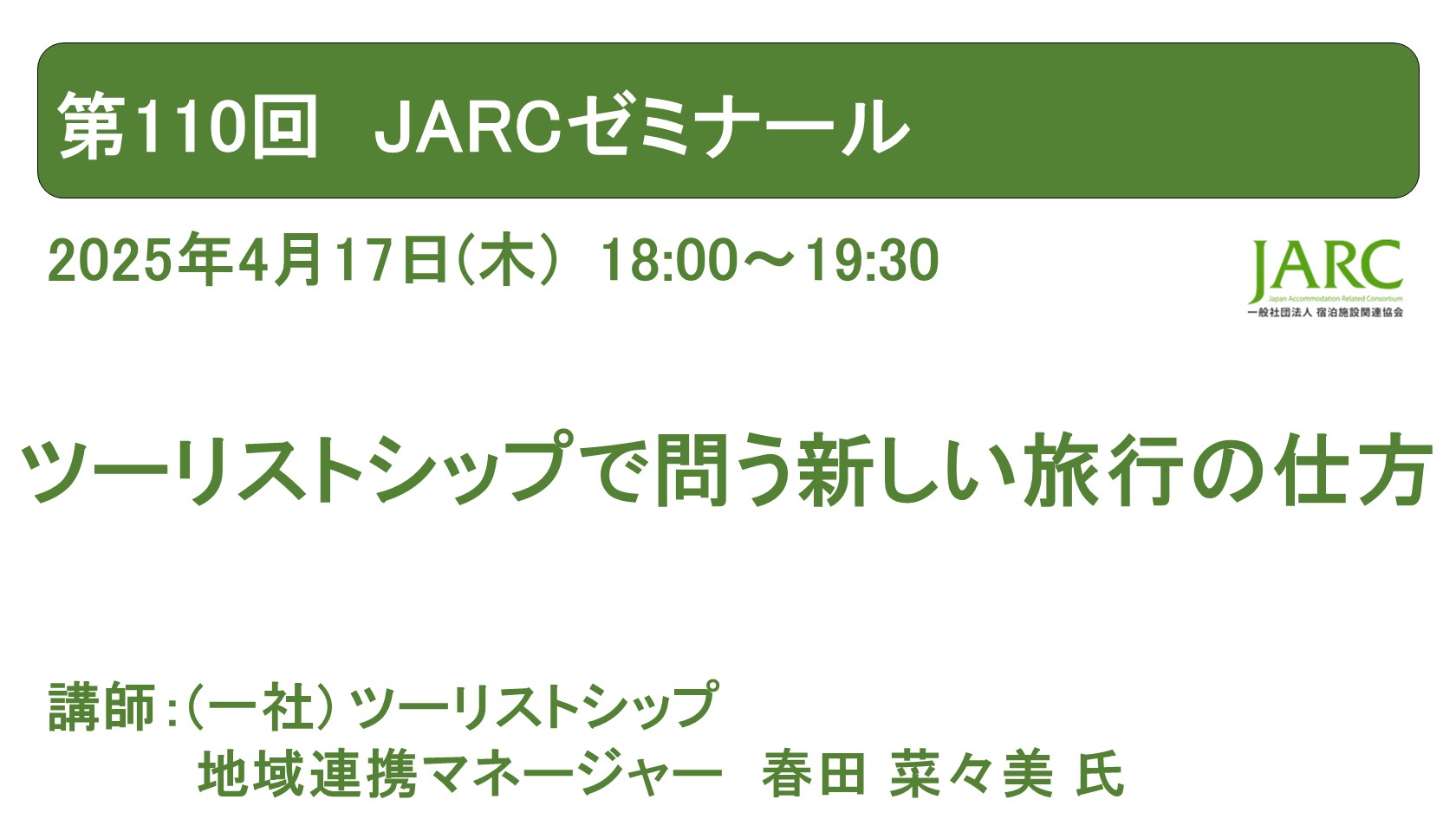旅館の定義を考えるセミナー(1月14日)
公益財団法人日本交通公社(JTBF)に事務局を置く「温泉まちづくり研究会」(宮﨑光彦会長・道後御湯)は、「旅館(RYOKAN)とは何か、旅館の定義について考える」と題したセミナーを東京都内で開催した。ハード、ソフトにおける旅館とホテルの違いがあいまいになり、古民家泊や民泊など多様な宿泊施設が登場する中、旅館はどのような宿泊施設なのか。旅館の世界への発信、次世代への継承を課題として、旅館経営者や観光有識者が議論した。
定義なく、世界にどう発信
旅館とホテルは、主な構造、設備が和式か洋式かという分類がされてきたが、2018年の旅館業法改正で営業種別はなくなり、「旅館・ホテル営業」に統合された。法改正以前から、宿泊施設におけるトレンドやニーズは多様化しており、旅館、ホテルをハード、ソフトで区別することは難しくなっていた。
セミナーの進行役を務めた東洋大学国際観光学部准教授の内田彩氏は、「かつては和か洋かだったが、旅館も、ホテルも時代とともに変わった。旅館をどのように捉え、発信するのかが非常に見えにくくなった。旅館を商品として考えたとき、旅行者のニーズはさまざまな意味で多様化し、市場も細分化していく中、やはり何らかの消費者に伝わるカテゴリーというのは必要だろう。今、旅館とは何なのか、改めて議論を深める必要がある」と問題提起した。

内田氏
国連世界観光機関駐日事務所代表、初代観光庁長官の本保芳明氏は「問題に思うのは、これだけインバウンドが増えてきているのに旅館が利用されていないこと。外国人旅行者に利用されなければ、いずれ日本文化における旅館の重要性は維持できなくなるのではないか」と指摘した。
 会員向け記事です。
会員向け記事です。