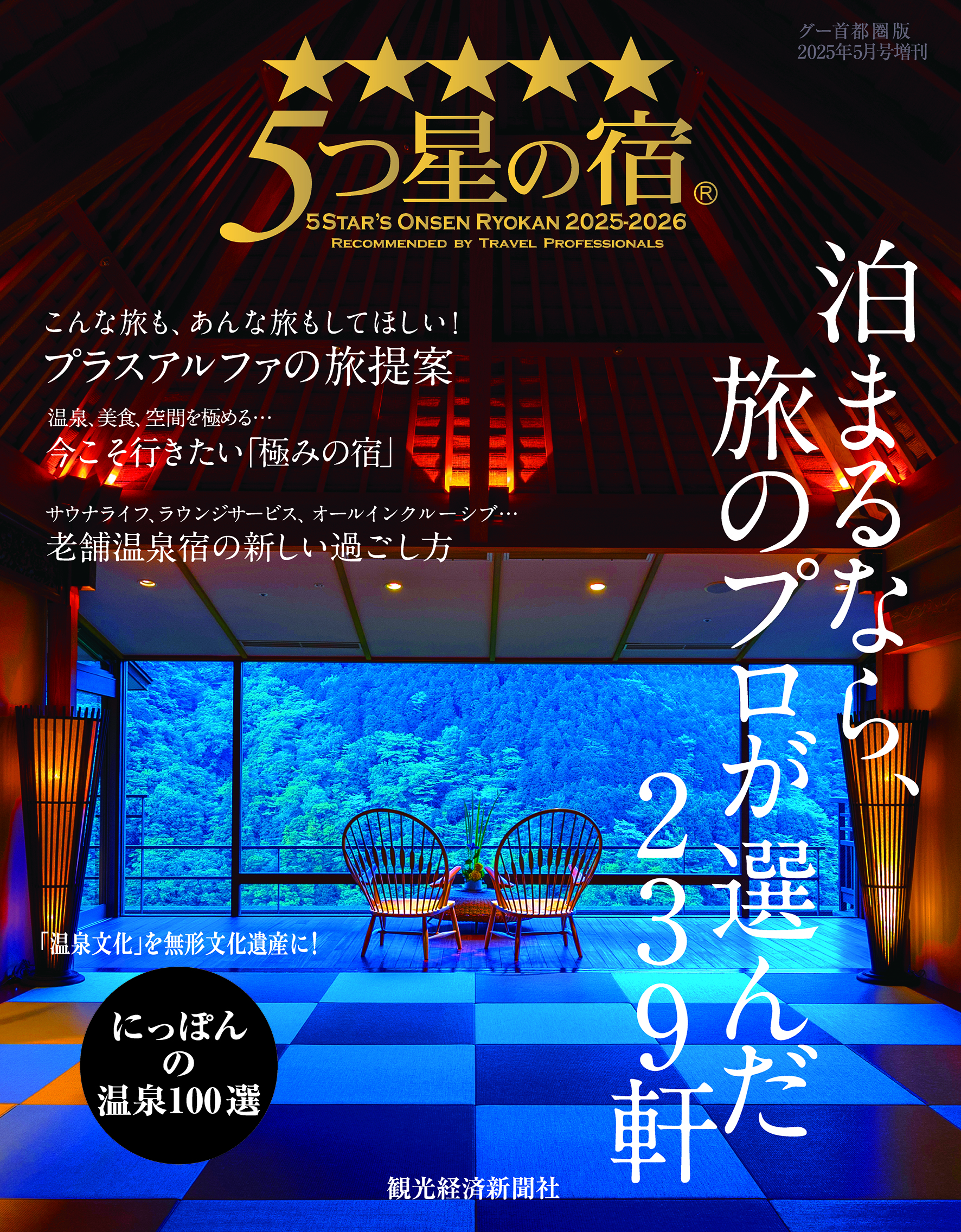日本には餅、団子、煎餅、饅頭(まんじゅう)、羊羹(ようかん)などいろいろな和菓子が数多くある。たいていは特別な道具や器具など使わずに手で作られる。
なかでも饅頭は餡(あん)を小麦粉生地で包み手で丸めて蒸すだけだから菓子の中で最も早く作られ、最も多く売られている。和菓子の始まりともいわれている。
元々は中国の肉入りの饅頭(まんとう)で、室町時代、留学僧と一緒に日本に渡来し奈良に住んだ林淨因(りんじょういん)によって小豆餡入りの饅頭が作られたといわれる。
その林浄因を菓祖として祭る奈良市の林(りん)神社(漢國(かんごう)神社境内)では、毎年、命日の4月19日に全国の菓子店から多くの菓子が奉納され、多数の菓子関係者が参列して、宮司の祝詞奏上を皮切りに恭しく「饅頭まつり」が執り行われる。
日本に帰化した林淨因の子息が一時、三河国(愛知県)鳳来寺町塩瀬村に居を構えたゆかりで、姓を塩瀬と名乗り、以降、代々が上品な味わいの薯蕷(じょよう)饅頭「志ほせ饅頭」(東京都中央区)を今に伝え続けている。
そんな由緒を踏まえて、奈良の中心街で創業320年余の老舗の千代乃舎竹村が、新たな風味を加えて「奈良饅頭」を製造販売。饅頭発祥の歴史を伝えている。
小豆の黒餡入りの饅頭の皮には「林」、インゲン豆入りの白餡の皮には「鹿」の愛らしい焼印が押してある。香ばしい皮としっとりの餡が調和して実においしい。
繁華街の東向商店街にある同店は、和三盆糖、吉野本葛、寒梅粉で作る短冊型の干菓子「青丹よし」で知られる名店だが、数年前発売のバターを使った洋風饅頭の「さるさわの月」も評判がいい。
奈良で饅頭といえば、江戸時代後期創業の萬々堂通則の「ぶと饅頭」も代表する菓子。「ぶと」とは春日大社の御祭礼にお供えする神饌(しんせん)のことで、米粉をこねた皮でこし餡をくるんでコーン油で揚げた唐菓子。表面に砂糖をまぶした、いわば餡ドーナツである。店は猿沢の池の西側、アーケードの餅飯殿(もちいどの)商店街にある。
ぶと饅頭が神に供える饅頭なら、法隆寺のある斑鳩町が本店の奈良祥楽(しょうがく)の「らほつ饅頭」は、大仏の頭の巻髪の名を付けたかりんと饅頭。外はカリッ、中はしっとりのこし餡、つぶ餡、抹茶餡などいろいろある、奈良ならではの饅頭である。
(紀行作家)
【メモ】「奈良饅頭」=千代乃舎竹村(0742・22・2325)、1箱6個入税込み1300円(取り寄せ可)

饅頭の始祖「奈良饅頭」

饅頭の神祭る「林神社」

(観光経済新聞2025年4月14日号掲載コラム)