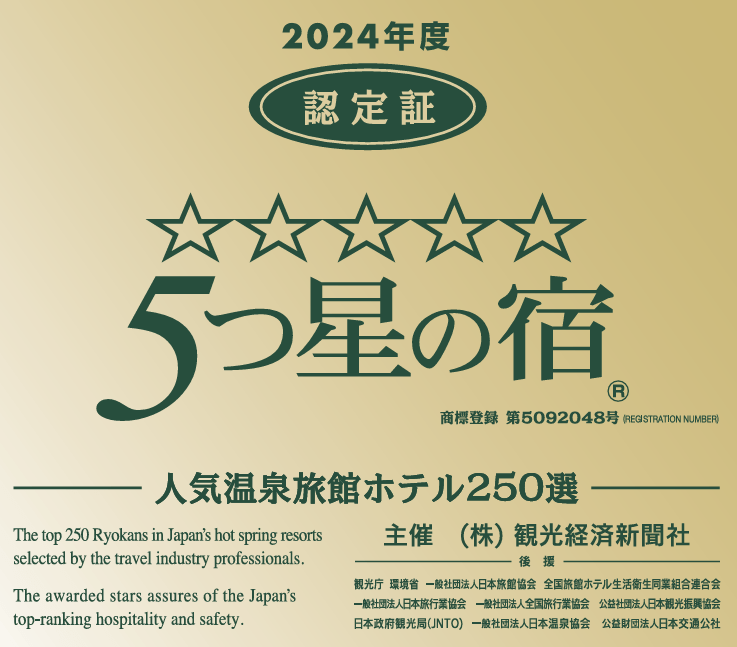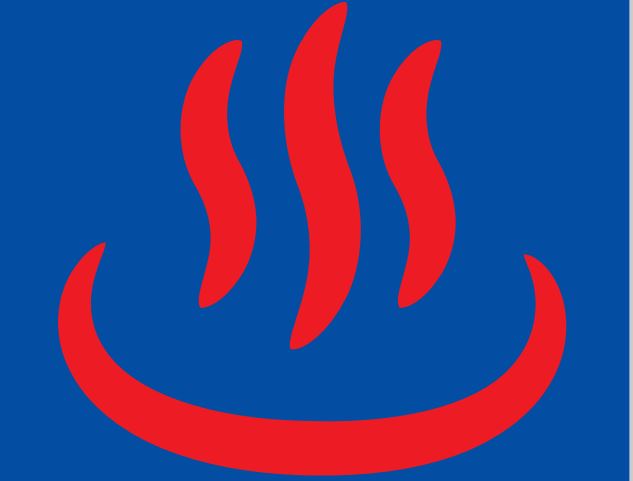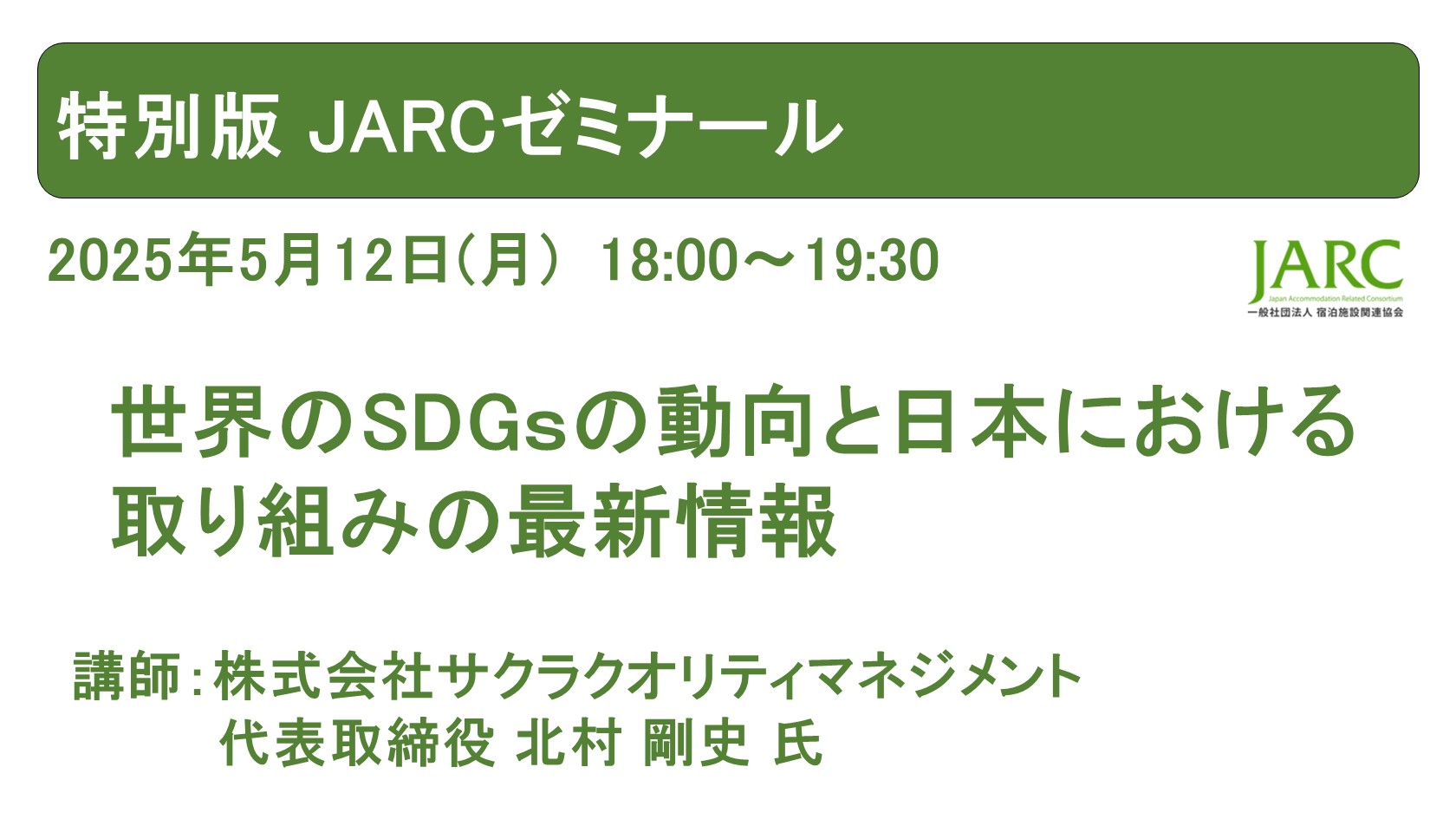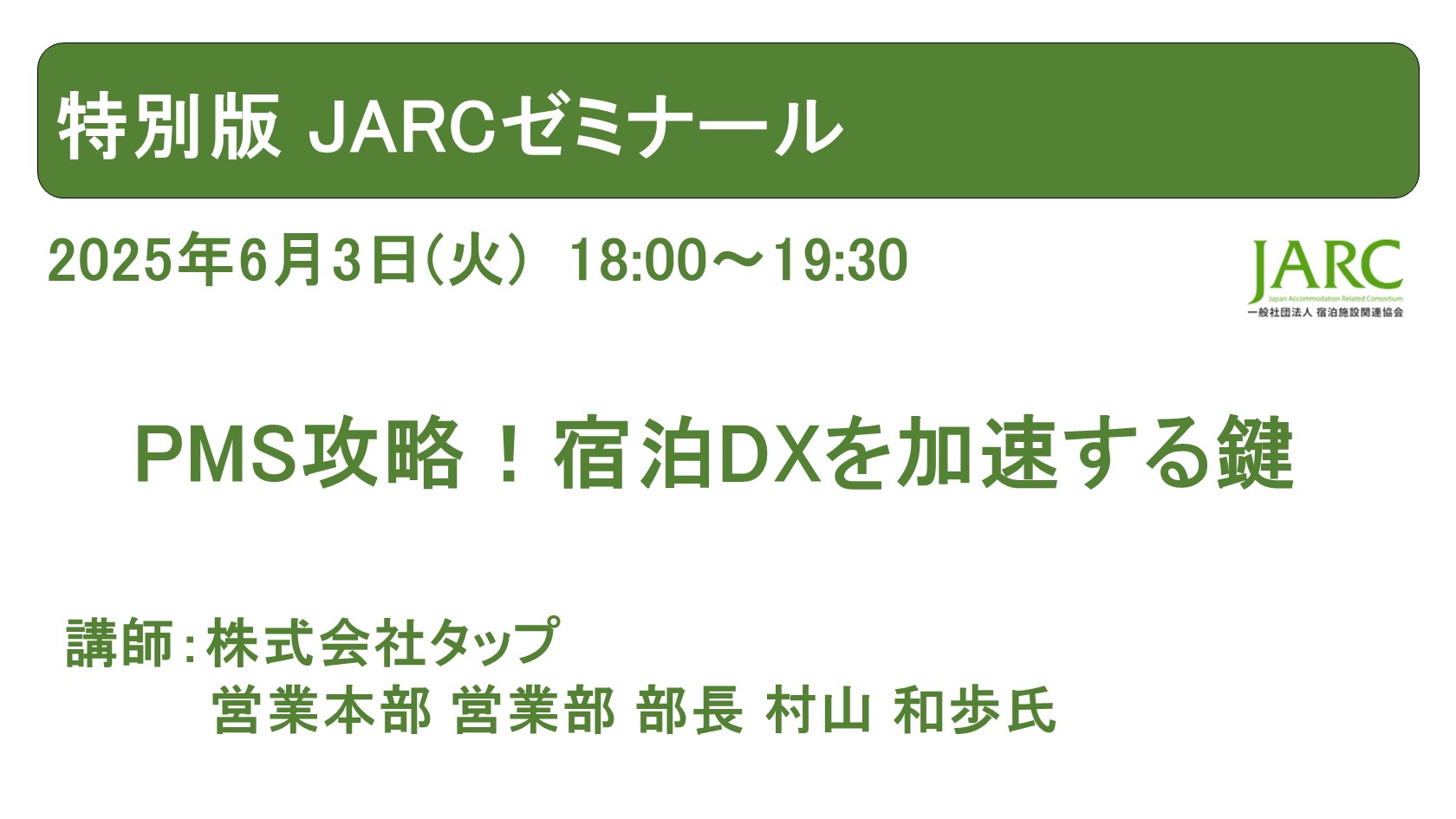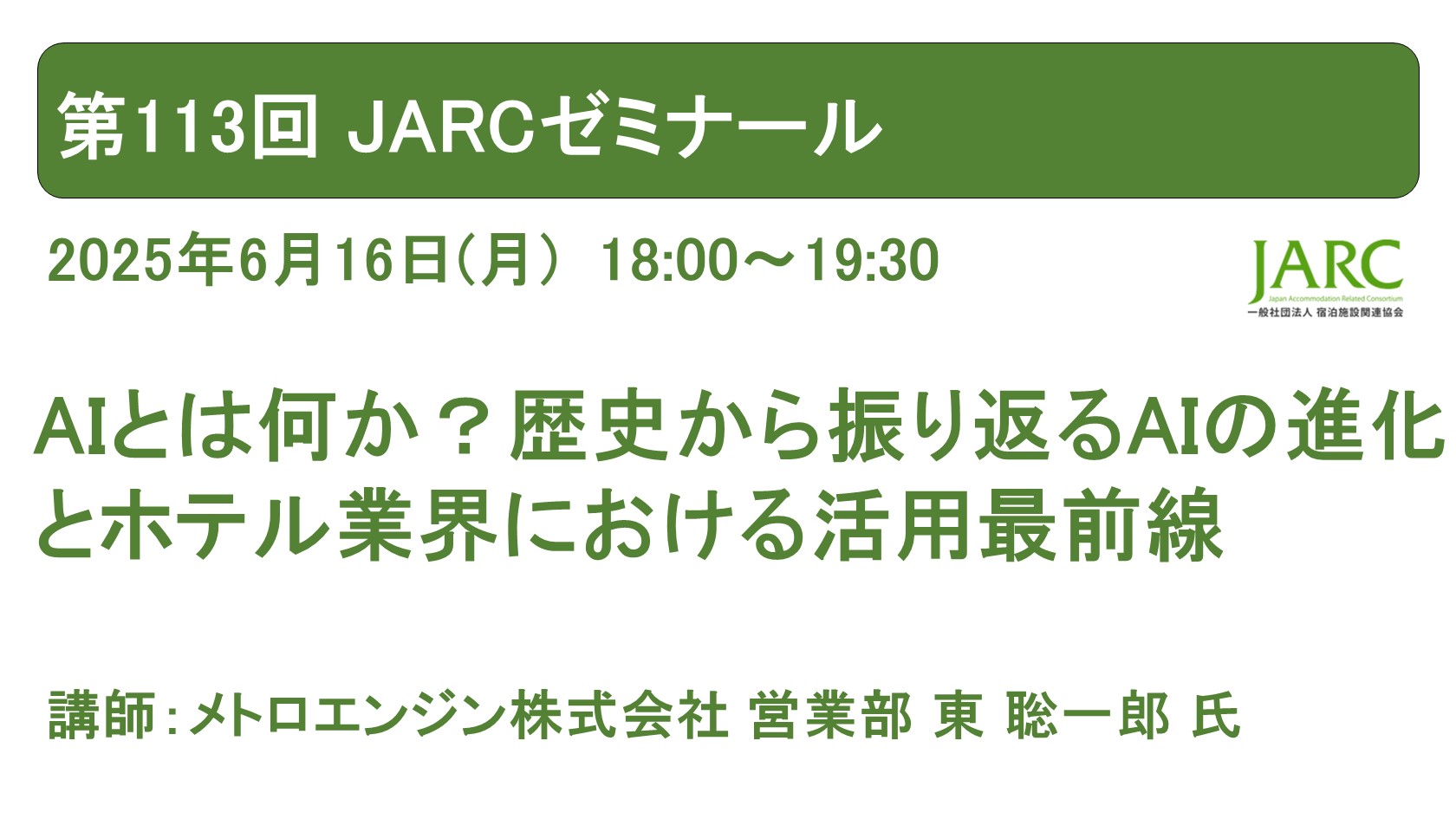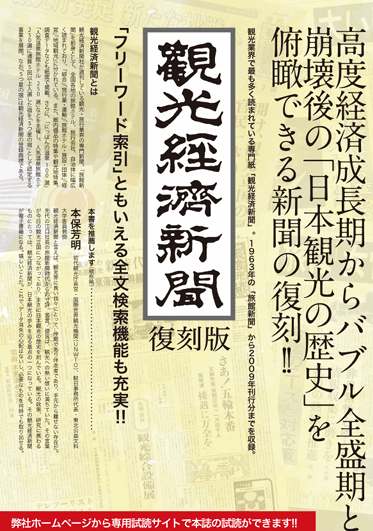観光政策において計画や立案は常に花形として、世間からの注目を浴びている。しかし、評価する段階になった途端に、世間からの注目度は格段に下がってしまう。この立案と評価をめぐる認識のギャップが、日本における観光政策推進のボトルネックとなってきている。
観光政策における評価の重要性は、ここ数年さまざまな議論や成果が出てきている。観光地域づくり法人(DMO)をめぐって、観光庁がKPI(重要業績評価指標)やKGI(重要目標達成指標)をはじめとする評価指標を相次いで導入してきている。評価指標の導入は、これまで個人の「勘と経験」や「成功体験」によって彩られてきた日本の観光政策を、明確なエビデンスに基づいた、一貫した基準のなかで推進することを試みるものである。
しかし、観光の現場では評価指標の導入をめぐって、さまざまな壁にもぶち当たっている。必ずしも潤沢な予算や専門人材を抱えているわけではない地域観光の現場では、政策評価に多くの資源をつぎ込むことのインセンティブは決して高くない。それどころか、評価そのものに意義を見いだすことができずに、形骸化や廃止といった顛末(てんまつ)になることは、決して珍しいことではない。
しかしより重要な点として、そもそも観光政策評価とは、誰のために行われるものであろうか。それは、観光客のためであり、観光産業のためであり、地域住民のためである。しかし、観光とは社会のさまざまなステークホルダーが関わるがゆえに、誰に対して説明を行うかによって、評価に関わるデータの収集・分析・公表の仕方は、常に多様で異なったものになるはずである。
それゆえ、観光政策評価をめぐる「迷走」の背後には、政策評価における説明責任の対象と所在について、議論されてきたようで実はされてこなかった実態が横たわるのではないか。裏を返すと、この根元的な問いに対する回答を明確にすることが、観光政策評価を推進していく第一歩になるのかもしれない。
(高崎経済大学地域政策学部准教授 安田慎)
※連載「シニアマイスター経営の知恵」は今回で最終回となります。

(2025年2月17日号連載コラム)