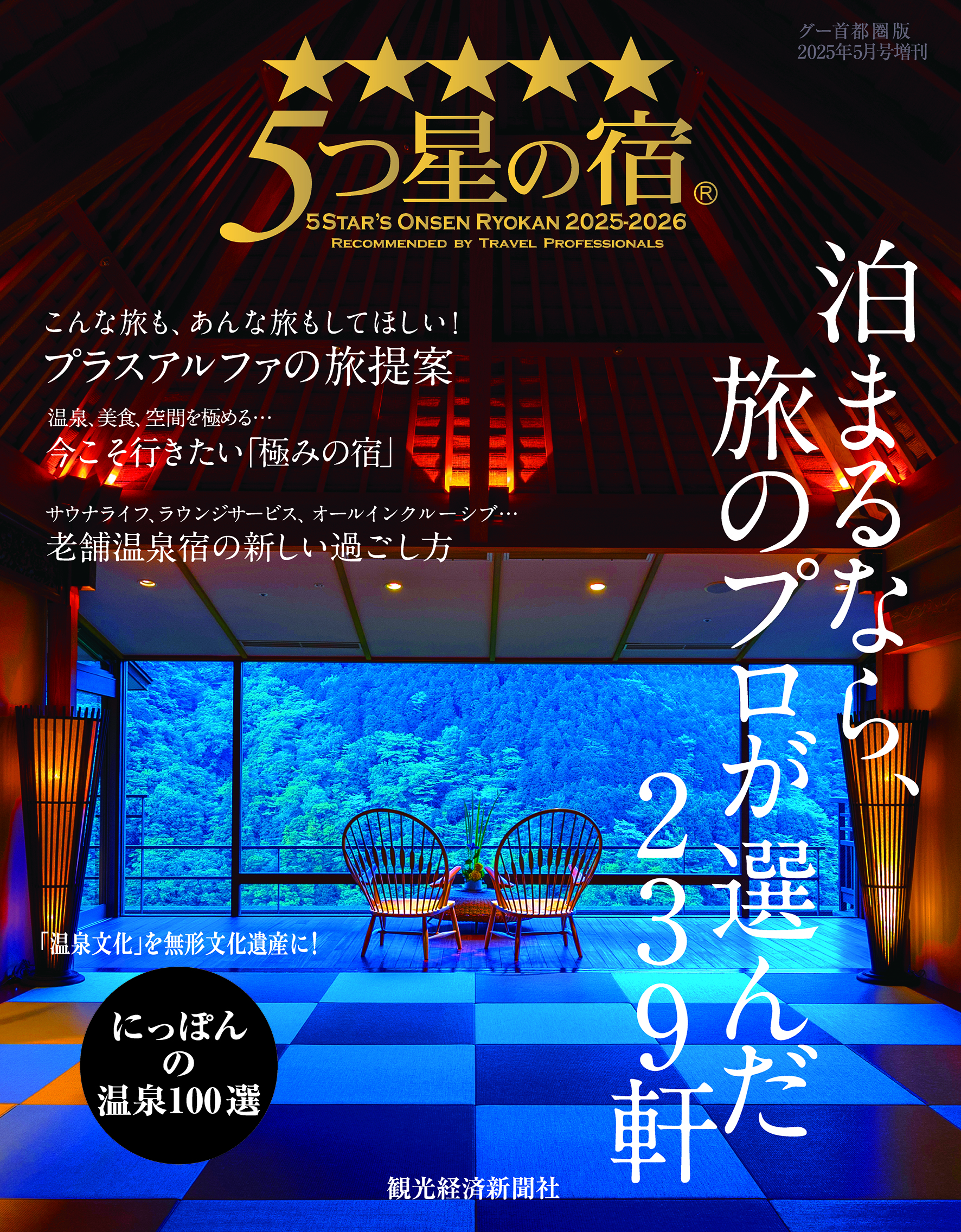東日本大震災から14年がたった。その被災地で広大な面積を消失する山林火災が発生した。
津波で海岸の低地の家屋が流失したことの教訓から、山麓の高台へと移り住んだ家屋が山火事で消失するという予想だにしなかった皮肉な結果となった。難しい選択である。一刻も早い被災地の復旧・復興を願っている。
東京都心では羽田空港行きの京急は相変わらず朝から満員である。インバウンドが多いが日本人も多くなった。7日は羽田空港から広島空港へ飛んだ。機材はいつもはB6だが、その日は定員が130人以上多いB7―200で、その9割程度が埋まっていた。スーツ姿とは違う服装の人が多い。旅行客も動き出している。
その広島市内も大きなスーツケースを抱きかかえて路面電車に乗り込む外国人が目に付く。ホテル代も大都市の例のごとく日本人には高い。しかし、今日まで低額で競争していた宿泊業は、人材の確保に苦慮している。人件費の増は免れないことから、現状の価格は適正価格ともいえる。旅行費増を乗り越えるには、可処分所得を増やすことだ。
その上で、客とり合戦の様相である。コロナ後の今日、過去のデータや傾向にとらわれていてはマーケットを見誤るかもしれない。旅行会社の企画商品も定番コースだけでは飽きられてしまう。旅人は知らないところへ行きたい志向がある。
旅行会社は新しいデスティネーションとコンテンツを開発しなければならない。しかし、旅行会社側に現地踏査をし、新しい企画商品づくりをする人材が不足していることもあり、ままならない。
つまりは、観光客を誘致したいと思う地域側で大いに企画提案をすべきということである。来てほしいと思う気持ちだけで、お客の思いに心が至らなかったり、安くしたり、過剰なサービスをしたりするだけなどは長続きせず、慎まなければならない。
「旅人に感動を与えられるか」。このキーワード1点で勝負すべきである。そのための手法は何か。人は体験から自信と誇りを獲得する。人は人との交流から刺激や元気をもらう。中には、その体験が生涯の趣味となったり、生き方を変えたり、人生を左右させる出来事となる。体験・交流こそ最大最高のキラーコンテンツである。
お客にとっての費用対効果が求められている。旅は消費や浪費ではない。それは、満足感、充実感、達成感や、知的欲求を充たすもので、金額では計れない。旅人の心に残る、心を高めるものに他ならない。
9日、全国ほんもの体験ネットワーク・全国教育民泊協会総会を瀬戸内海の完全離島広島県大崎上島町で、北海道から沖縄までの130人が参加し開催した。教育民泊の受け入れ家庭数をコロナ前までに回復させるための課題と方法について熱い議論が交わされ、成功裏に閉会した。コロナ後の地域観光の新しい時代を創造する年にしたいものである。

(観光経済新聞25年3月17日号掲載コラム)