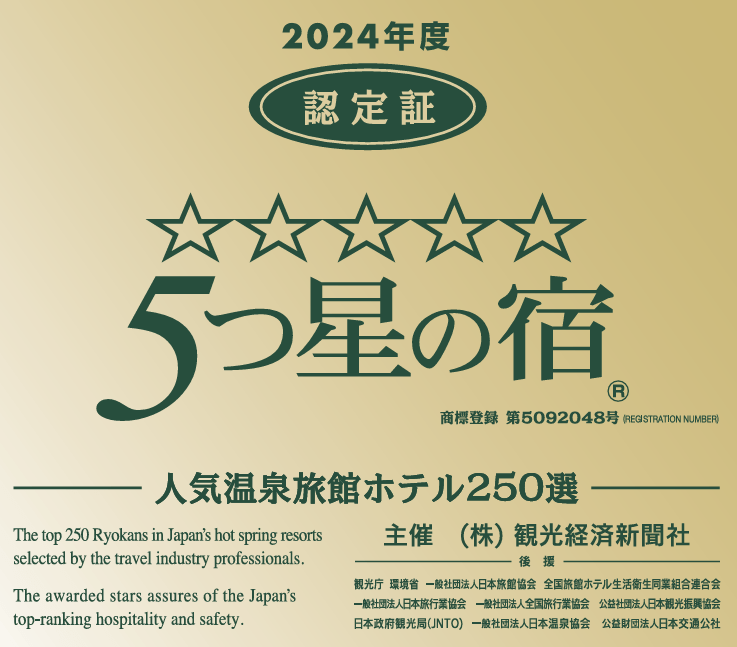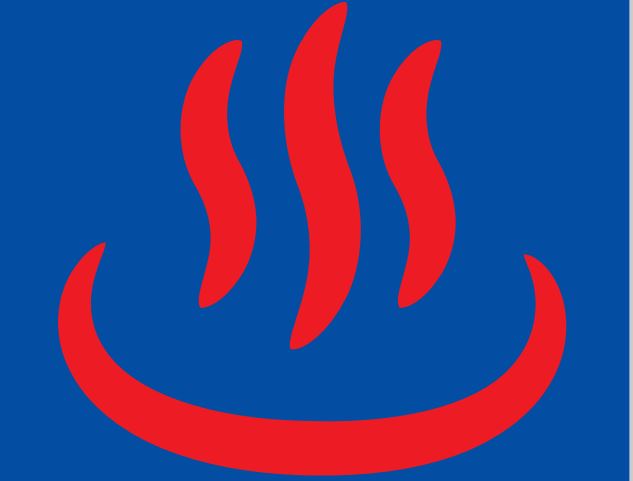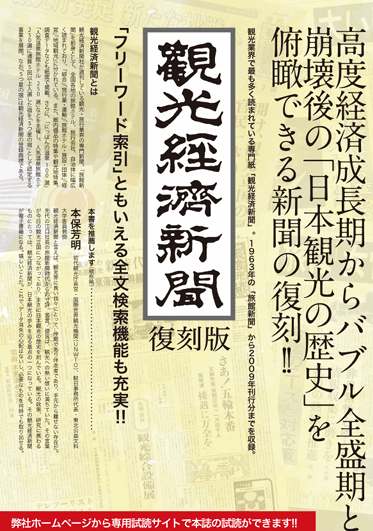最初は何で目に留まったのか明確な記憶がないのだが、一目見て忘れられなくなってしまった浮世絵がある。歌川広重の「東都名所高輪廿六夜待遊興之図」である。好きな浮世絵師の一人、広重の作品というのもあったが、登場人物たちのワクワク感が伝わってくるような、楽し気な雰囲気にとても引かれた。
彼らがウキウキしていたのは、それが特別な日だから。旧暦7月26日の夜の月の光は、阿弥陀三尊(阿弥陀如来・観音菩薩・勢至菩薩)の化現であり、それを拝むとご利益があると信仰されていた。人々は月が見える見晴らしの良い所に集まった。当初はただひたすら祈っていたようだが、徐々にお祭りのようなにぎわいになっていったらしい。月が出るのを待ちながら、飲んだり食べたりして、待つ時間を楽しんだ。そう、ここでは誰もが「食」を楽しんでいたのだ。
そこになくてはならないのが屋台である。同作品が描かれた天保年間には、多種多様な屋台が存在したという。この絵に登場する屋台も、お汁粉屋、だんご屋、二八そば屋、てんぷら屋、イカ焼き屋、すし屋、水菓子屋などさまざま。現代のお祭りの屋台に、引けを取らないラインアップだ。
江戸時代、ナゼこれだけ屋台文化が発達したのだろう? そのヒントは「火事とけんかは江戸の華」という言葉。気が短い江戸っ子は、けんかっ早いとされていた。そして、江戸の町は木造家屋が密集し、火事が起こりやすく、延焼しやすい環境でもあった。だから焼け出される人も多く、庶民にとって恐ろしいものであったという。故に、火消の活躍はヒーローのように「華々しい」と表現されたのだろう。
それが屋台とどう関係するのか?と言われそうだが、実は大ありだ。最も被害が大きかった、明暦3年に起きた「明暦の大火」では、外堀の内側の江戸市中はほぼ全域が焦土と化し、江戸城も本丸や二の丸、天守まで焼失。死者は10万人を超えたといわれる。
この大火をキッカケに、幕府は都市整備に注力。大名屋敷や旗本・御家人の武家屋敷、寺社を移転させ、その跡地を、防火帯の役割を持ち延焼を遮断する「火除地」という空き地や広小路とした。こういった場所に人々が集うようになり、盛り場に発展したといわれる。その主役こそが屋台だったのだ。火除地に常設の建造物は建てられないため、肩で担げる屋台や、移動は大変だが、一応可動式の「床店」などが商売をするのにピッタリだった。
加えて需要もあった。大火の復興のため、江戸の町には他の地域から職人が集まり、農村からの出稼ぎ労働者も流入した。参勤交代で江戸に来る武士もいた。現代でいう単身赴任の男性が多かったのだ。彼らにとって、まきで火を起こして自炊するより、外食の方が効率が良い。肉体労働者は一度にお腹いっぱい食べるより、こまめに間食する方が動きやすい。「屋台めし」は、こうしたニーズに合致したのだ。他にもある屋台流行の要因、続きは次号で!
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。