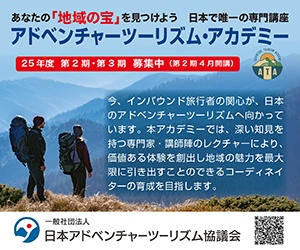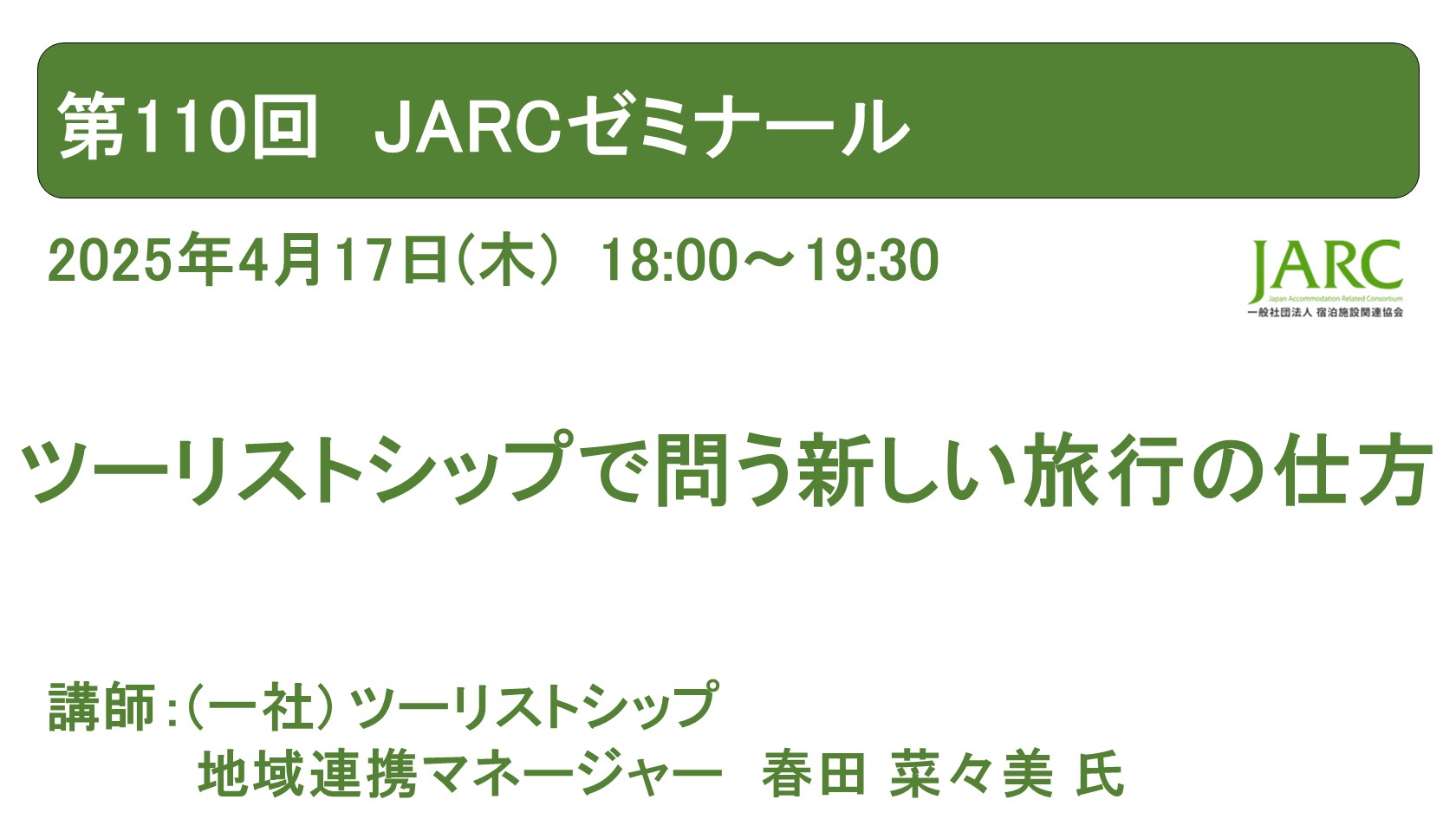コロナ禍で借りた運転資金。そしてここ数年ブームのようになった、高付加価値化による設備投資に係る設備資金の借入。国の後押しもあり、各金融機関も積極的に融資を行いました。
これらにより借入の口数が、いっきに増えたお宿は多いのではないでしょうか。中でも中小規模のお宿においては、客室が工事期間中一部クローズになったところもあり、単純に工事代金だけでなく、客室数の減少による機会損失分が、そのまま収益減につながったケースが見られます。
このことは当然資金繰りに影響を及ぼし、一時的な資金減に対処するための、運転資金の新たな借入がセットで実行された事例がありました。
さて口数がここ数年で増えたということは、その分単純に借入返済額や支払利息も増えます。これらの借入返済状況について、お宿の経営者であるあなたは、どのように対処していますでしょうか。
金融機関から提示される口別「借入返済のご案内」は、経営者自ら目を通す場合もあるでしょう。
しかしお宿の規模が大きくなるにつれて、経理担当者のところで止まってしまいます。だから普段はその存在を意識することはあまりないのかもしれません。
さて支払利息は税務上損金算入されますので、損益計算書の営業外費用(支払利息・割引料)に計上されます。だから毎月の試算表をみれば、その金額や推移は一目瞭然です。
一方借入金返済額はどうかというと、これは経費ではないので損益計算書には計上されません。貸借対照表の月次差額を間接的に計算するか、預金通帳を見て、今月はいくら返済したかということで確認しなければなりません。
お金が出ていくのだから、返済も支払利息も一緒だろうと言いたいところですが、会計の理論では全く違うということになります。借入金返済額は金額が多いにもかかわらず、陰に隠れてしまっているのです。
そこでお勧めなのは、口別の借入金返済額および支払利息を月別に時系列化した一覧表を作成し、表に引っ張り出すことです。お宿で作成するか、もしくは金融機関の担当者に作成を依頼するという手もあります。
ではなぜこの表をわざわざ作成するのか。
一つは年間の借入金返済総額と支払利息の総額がそれぞれ明確になります。
もう一つはいつの時点で返済額がいくら減るのかが分かります。
これを資金繰り見込み表に反映させることにより、数カ月後の資金の状況が見えてきます。
また、返済原資の様子もここで注目しましょう。どういうことかというと返済原資は減価償却額+税引き後利益の金額です。この金額が年間返済額を上回っていれば、通常の営業活動の結果得られた中で、返済が可能だという理屈です。
一方この数値がマイナスだとしたら、このマイナス分が足りませんので、蓄えている現預金からの持ち出しによるか、新たな短期運転資金の借入により補填(ほてん)しなければならなくなります。
だからこのことを踏まえ、次年度経営計画において、収益弁済ができることを踏まえた目標利益額を設定する根拠となります。
税引き後利益は、借入金返済、内部留保、決算賞与、新たな積極的経費のための資金について、それぞれ具体的な金額を盛り込むのが大事なポイントですが、借入金返済一覧表はその根拠の一部を担う大事な資料なのです。
失敗の法則その46
借入金の口数が多くなり、返済金額の把握ができなくなっている。
その結果、いつの間にか資金繰りが厳しくなった。
だから、借入金返済一覧表を作成し、計画的に返済財源を確保していこう。
https://www.ryokan-clinic.com/

(観光経済新聞2025年3月31日号掲載コラム)