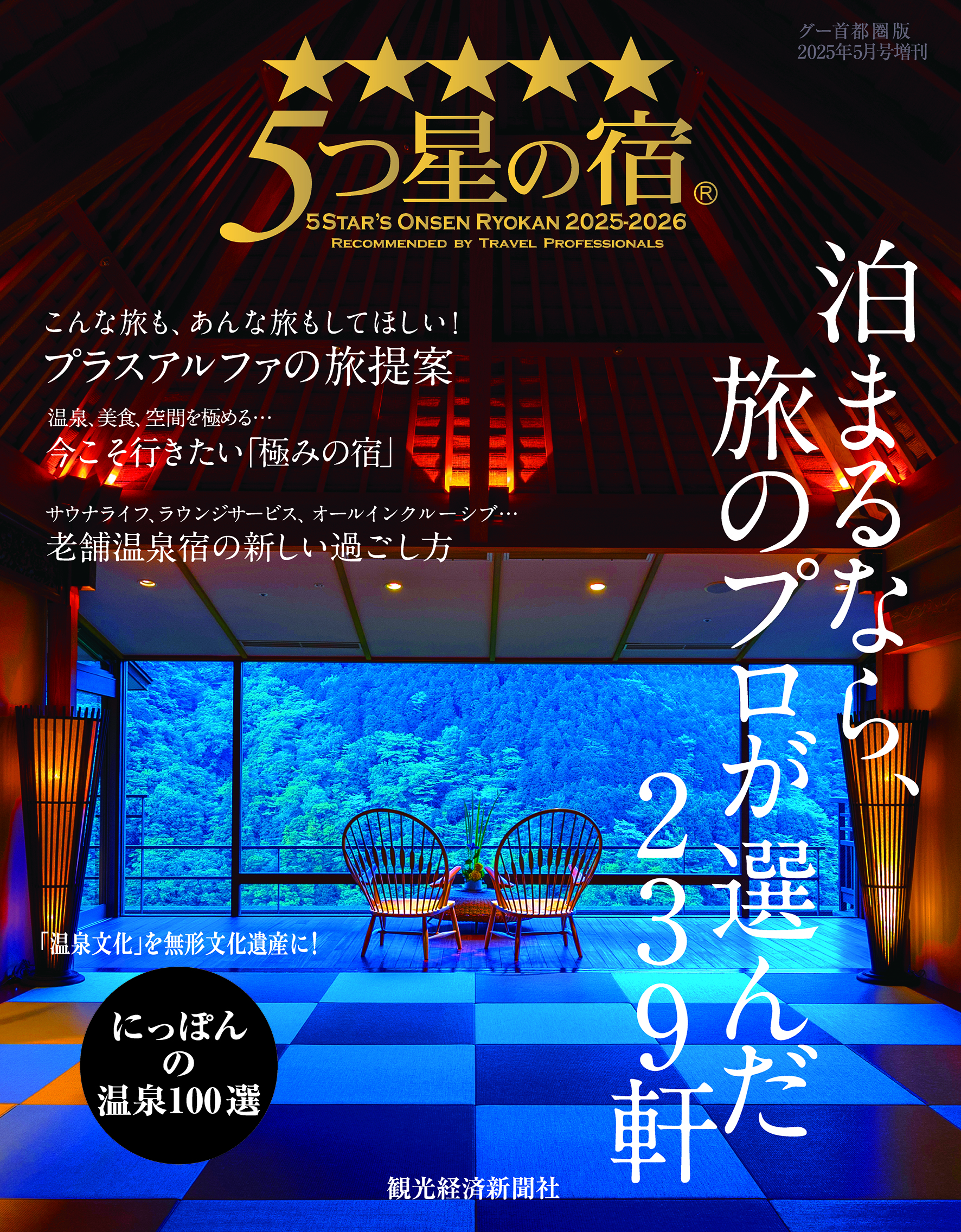観光関連コンサルタントの某氏は、旅館に「こだわりの和食コース」を求める宿泊客は一部に過ぎず、今後は、旅館に会席料理を求めるような客は減少していくと予測する。
その理由として、企業・団体による接待や会食の機会の減少や、冠婚葬祭の簡略化によって会席料理に触れる機会が失われてきたことを挙げる。さらに、和食コースになじみのない両親のもとで育つ子供たちは、それらに接する機会がないため、「本格的な和食料理に縁遠くなっている家庭」が増えていると指摘する。
その結果、このような家庭で育った人たちが旅行で宿泊先を選ぶ際は、「収入や宿泊予算に関係なく、カジュアルな各国料理や外部のレストランを好むため、本格的な日本料理を提供する旅館・ホテルは敬遠される傾向にある」と断ずる。
本当に、そうなのだろうか。日常で会席料理に触れる機会がないことが「旅館での宿泊を敬遠する」理由とは考えにくい。むしろ、日常で触れる機会がないからこそ旅館が和食文化を体験し学ぶ場となるのではなかろうか。
一方、交通業界に詳しい某アナリストは、テレビの情報番組で旅館の宿泊料金について問われると「泊食分離は世界の常識」とし、旅館の1泊2食の料金形態は、世界の実情にそぐわないと言い放つ。海外では、ホテルの宿泊料金は素泊まり、もしくは1泊朝食が主流で、夕食はホテル以外の地元のレストランで、その土地のものを使った料理を食べるのが一般的だという。よって日本の旅館でも、泊食分離を取り入れ、食事の選択肢を増やすことが望ましいと説く。
だが、実のところ、都市部ならともかく、よほど有名な温泉観光地でない限り、料理のカテゴリーにせよ、価格帯や営業時間帯にせよ旅館の宿泊客が満足するような夕食を常時、提供できる飲食店はほとんどない。
果たして、本当に、温泉観光地の旅館が、世界基準と言われる泊食分離の料金体系に合わせる必要があるのだろうか。
そもそも日本独自の宿泊形態である旅館と西欧に倣ったホテルでは、文化的側面も営業形態も異なる。長きにわたり日本の風習や文化を受け継いできた旅館には、それらを次の世代へと伝承していく使命と責任がある。特に、1泊2食の要である旅館の夕食(会席料理)を安易に手放してしまうことは、旅館文化存続の危機をも招きかねない。
また、旅館の夕食が提供しているのは、会席料理に託された食文化だけではない。
たとえば、すべての宿泊客が、同じコスチューム(民族衣装)、いわゆる「浴衣」に着替えて食事を楽しむ光景は、世界的にも類を見ない特異な文化的事象、風習と言っても過言ではない。
温泉文化をユネスコ無形文化遺産に登録する動きがあるが、和食が同文化遺産に登録された決め手のひとつに、雑煮の存在があったという。年があけた元日に、日本国民全員が、一斉に同じもの(雑煮)を食べる風習と、同じ雑煮でもその具材やだしの味が地域によって異なるというユニークさが評価されたらしい。
翻って、1泊2食で提供される旅館の夕食も同様、民族衣装に着替えて食事をする光景は、まさに日本固有の温泉文化、旅館文化と言える。世界基準に拘泥することなく1泊2食の滞在スタイルの課題を真摯(しんし)に検討し、ブラッシュアップしていくことが重要だろう。
福島 規子(ふくしま・のりこ)九州国際大学教授・博士(観光学)、オフィスヴァルト・サービスコンサルタント。

(観光経済新聞2025年4月14日号掲載コラム)