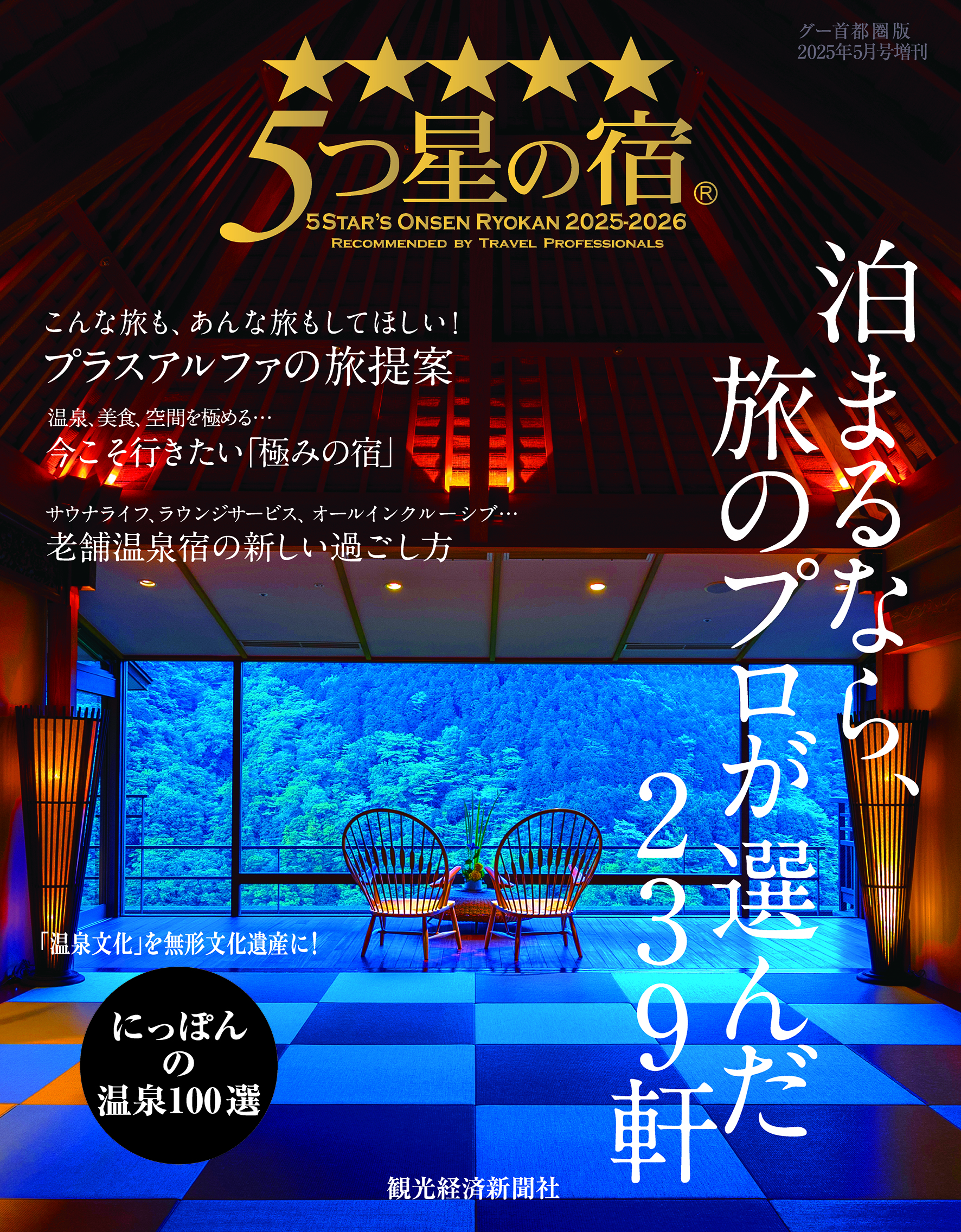戦後、日本家屋は西洋化していき、今では全室畳の家というのは珍しいほどです。そのため、和室に慣れていない人が多く、旅館ホテルで働く若い人たちも和室での作法に戸惑うことが多いようです。
和室の基礎
和室には西洋建築にない独特の様式があります。それは部屋の造りであったり、もてなしの位置であったり、あるいは立ち居振る舞いであったりします。まず最初に和室の基本から学びましょう。
●床の間
日本建築の歴史の中でも、特に大切にされてきたのが「床の間」です。これは和室の中でも最も上座に位置するところです。床飾りといって、掛け軸や生け花、香炉などを飾り、お客さまをもてなす場所です。その意味を知らない外国人の中には、バッグや荷物の置き場所と勘違いする人がいます。床の間は上座ですから、そのような物を置くことはできません。
・掛け軸
書や日本画が描かれ、表装された物で、床の間に飾ります。季節感のある行事にちなんだ物が選ばれます。掛け軸は掛けっぱなしにする物ではなく、朝掛けたら夜には巻き上げて片付けるのが本当です。旅館ホテルではその会社の方針に従うとよいでしょう。掛けたら必ず一度座ってみて、ゆがみがないかを確かめます。湿度や温度で変形することもあり、よく注意しましょう。
・花
床の間に花が生けてあると、部屋が華やぎます。季節の花材を選びます。床の間の大きさに対してバランスをとることが重要です。掛け軸の内容とかち合わないようにし、花器と花材の組み合わせにも気を配ることが大切です。掛け軸の正面をふさがないように、床の間の下座、3分の1のところに置きます。
●座布団
畳の室内では座布団は必需品です。これには表と裏があります。表には座布団の中央の綴(と)じの部分に糸で房がついているのでわかります。また、前後の別もあります。座布団の側面で一辺が「わ」になっている、つまり縫い目のないほうが前に当たり、座る人の膝側にきます。
●上座と下座
和室には上座と下座があります。上座へいくほど身分の高い人、下座はその逆です。入り口から遠いほうが上座で、これは洋室でも和室でも同じです。西洋のプロトコール(国際儀礼)では、右を上位とするため、部屋の右奥を上座とする風潮がありますが、本来日本では左手が上座で、これは中国の考え方からきています。床の間のある和室では、床の間に最も近い席がその部屋の上座になります。
* *
■日本ホテルレストラン経営研究所=ホスピタリティ業界(旅館、ホテル、レストラン、ブライダル、観光、介護)の人材育成と国際交流へ貢献することを目的とするNPO法人。同研究所の大谷晃理事長、鈴木はるみ上席研究員が監修する書籍「『旅館ホテル』のおもてなし」が星雲社から発売中。問い合わせは同社TEL03(3868)3275。