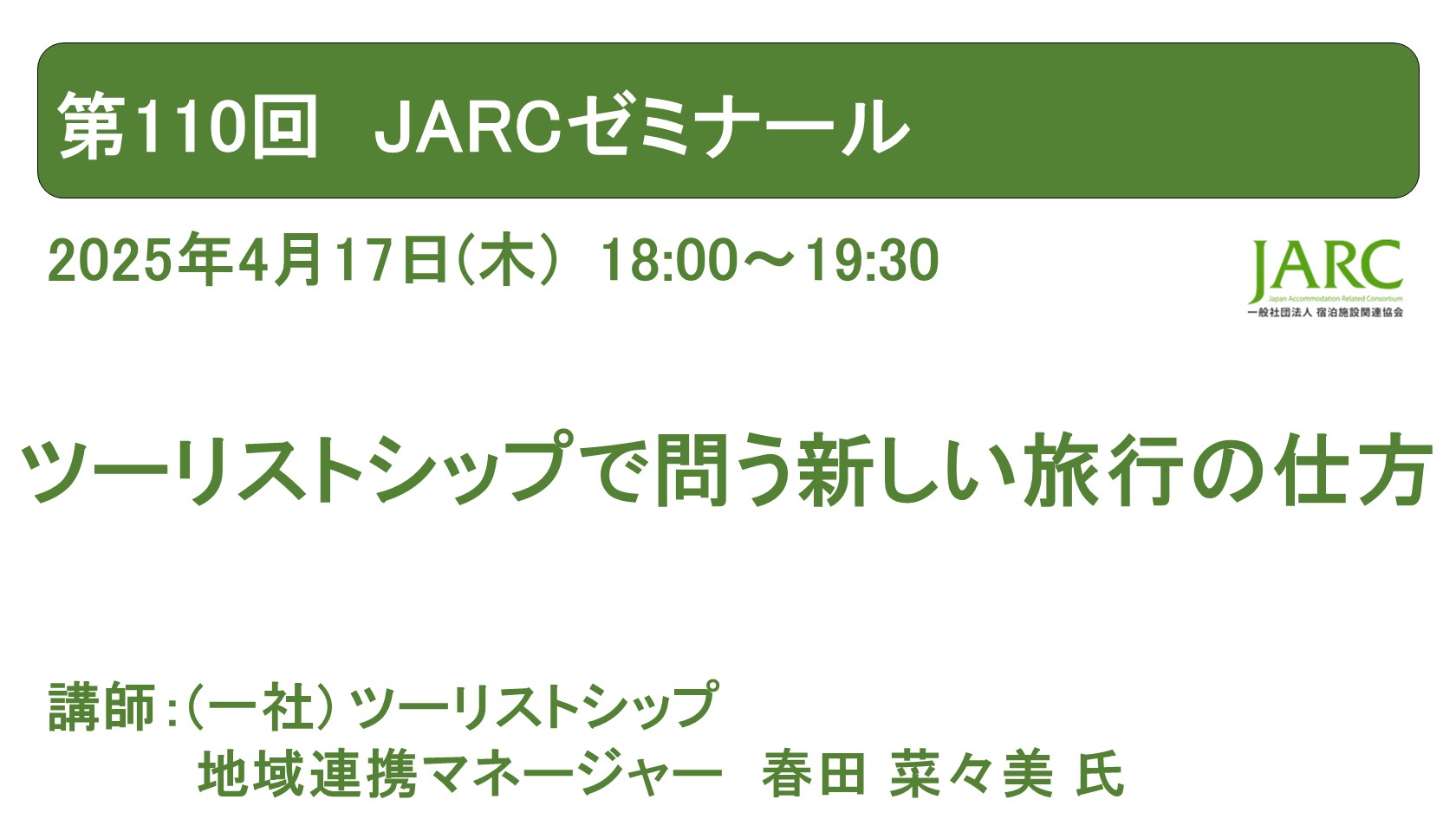ある2代目社長との会話。「社長、決算書を拝見すると3期前から同じ会社に対する同じ金額の売掛金がありますね。請求作業は間違いなく行われていますか?」。
別の会社の従業員との面談。「あなたが保証している保証債務、いつからのものですか? 本人は今まで一度も払ってないんですね」。会社や個人は債権者にも債務者にも簡単になり得るが、事の重大性を意識していないケースが多くあるのも事実だ。そのような時に「時効」を知っていて損はない。かくいう私も消滅時効を知っていてよかったという経験がある。
時効とは、ある事実状態が一定の期間継続した場合に、権利の取得・喪失という法律効果を認める制度で取得時効と消滅時効がある。一般的には、あることの効力が一定の時間を経過したために無効となることを言う。
一般の生活を営む個人においてもさまざまな時効がかかわっている。ましてや企業経営においては多くの時効が存在する。
事業を営んでいるとさまざまな債権や債務があることに気付く。決算書の貸借対照表を見ると売掛金や受取手形、貸付金などの債権と、買掛金や未払い金、借入金などの債務が存在することがわかる。債権は請求することによって効力が発生し回収することができる。しかし、請求することなく一定の期間を経過すると時効となって消滅する。
ただし、時効はそのことによって利益を受ける者(債務者)が時効を主張すること(時効の援用)によって成立する。単純に時効の期間が過ぎたことによってだけでは債権は消滅しない。したがって債権の請求は可能だが、債務者が時効の援用を行えば債権は消滅する。
サービス業においてもさまざまな債権が存在する。主な債権の消滅時効の期間について知っておくことは重要だ。2020年4月1日の民法改正以前と以降で若干の違いはあるが、発生時期が現在であれば、
6カ月 小切手債権
3年 給料・賞与債権、不法行為に基づく損害賠償請求権、手形債権
5年 旅館ホテル・飲食店の債権、工事業者の債権
5年 退職金、銀行・信販会社・消費者金融の債権
5年 個人からの借金、信用金庫の債権
繰り返すが、個人・法人にかかわらず債権者にも債務者にもなり得る。時効を意識すると、債権者の場合は時効の中断(改正民法では更新という)が重要で、債務者の場合は時効の援用が重要となることに気付く。時効を中断させる主な方法は(1)請求(裁判上の請求、裁判外の請求)(2)差し押さえ・仮差し押さえ・仮処分(3)債務者の承認だ(ただし、内容証明郵便などによる裁判外の請求は時効の完成を6カ月遅らせる効果しかないので注意が必要)。つまり、時効の中断には、債務者による一部支払いや支払覚書等の署名などにより債務の存在を認めさせるか、裁判手続きによるしかない。
時効の援用のためには、時効期間経過後に消滅時効の援用をする旨の内容を記載した書面を内容証明郵便で郵送しなければならない。内容証明郵便は個人でも作成可能ではあるが、安全・確実を期するためには法律の専門家に相談することをお勧めしたい。
(EHS研究所会長)

(観光経済新聞2025年4月7日号掲載コラム)