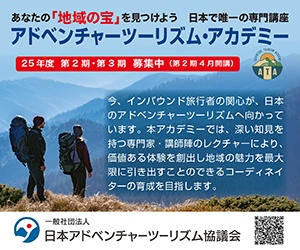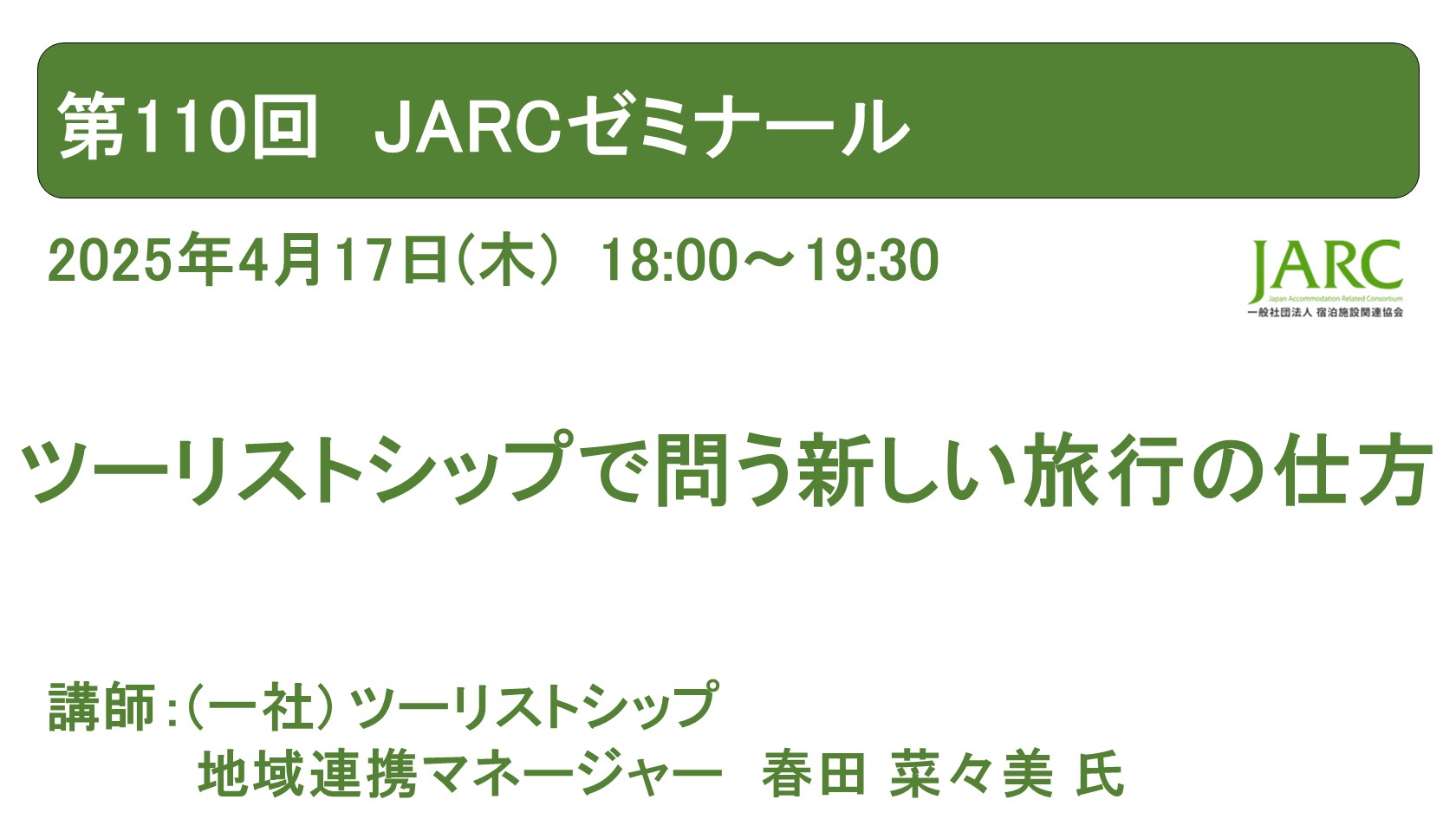政府観光局は2月の訪日外国人旅行者が325万人で過去最多を記録と公表した。中国の春節(旧正月)の休暇が初旬まで続いたことやスキーなど冬のスポーツ需要が押し上げ要因となった。石破茂首相は3月に開催された観光立国推進閣僚会議で26~30年度の次期「観光立国推進基本計画」を来年3月までに策定するように指示した。政府は既に30年に訪日客6千万人、訪日消費額15兆円の目標を決めており、それらの実現に向けた具体的施策の策定が焦点になる。
政府で観光政策を所管する中野洋昌国土交通相は、新年インタビューで「観光は成長戦略の柱、地方創生の切り札であり、観光産業は重要な担い手。しかし収益性や賃金水準の低さ、人手不足といった構造的課題が顕在化しており、稼げる産業への変革を推進するための支援が必要」と表明しており、「稼ぐ観光」推進の可能性が大である。
新自由主義経済の下で「稼ぐ観光」路線が自明の理とみなされている中、私は流通経済大の福井一喜氏が提唱している「無理しない観光」路線を高く評価している(福井著『「無理しない」観光:価値と多様性の再発見』ミネルヴァ書房)。
福井氏は観光立国の必要性を認めつつも、人口減少時代の成長戦略の柱として観光に重責を負わせ過ぎていることを危惧している。「観光は雇用を生みだす」と言われているが、大都市圏とは異なり、地方では観光関連で非正規雇用化が進み、離職率が高くなっている。富裕層は観光を楽しんでいるが、地方の庶民は富裕層のために不安定な雇用条件の下でエッセンシャルワークを強いられている。観光に伴う仕事の厳しさ・空しさは若い世代に広く知られており、観光産業における人手不足は極めて深刻化している。その上に外国人労働者の奪い合いが激化しており、観光産業の持続可能性が困難になっている。
観光庁は「観光で稼げ」と地方をあおり、成功事例を過剰に持ち上げ、補助金をぶら下げて、地域間競争を激化させている。地方には観光事業を成功に導く人材が乏しいにもかかわらず、うまくいかなければ地方の努力不足とみなされる。
そもそも今日における地方の疲弊の根本原因は長年にわたる政府の経済政策の失政によるものだ。日本で長らく地域経済に安定成長や雇用をもたらしてきた製造業が衰退したのに、政府は製造業に代わる安定した成長産業を見いだすことができないまま、観光に代表されるサービス業を地域の基幹産業とみなすようになった。本来であれば、資本主義の行き詰まりや経済構造の変化に対応した税制改革や再分配が必要不可欠であったにもかかわらず、政府の失政の穴埋めを地方に安直に押し付けたのは中央政治・行政の無責任そのものだ。
福井氏は観光が地域の歴史文化を尊重し、地域のさまざまな資源の保存・活用を促し、地域の暮らしを守ることに貢献している点を評価している。どこかをまねるのではなく、個々の地域資源を有効活用しながら、それぞれの地域の個性を最大限に生かして「無理しない観光」をそれぞれの地域なりに目指していくことが大切という福井氏の主張は注目に値する。私たちが03年に提唱した「住んでよし、訪れてよしの国づくり」という観光立国の根幹に合致する重要な提唱である。
(北海道大学観光学高等研究センター特別招聘教授)

(観光経済新聞2025年3月31日号掲載コラム)