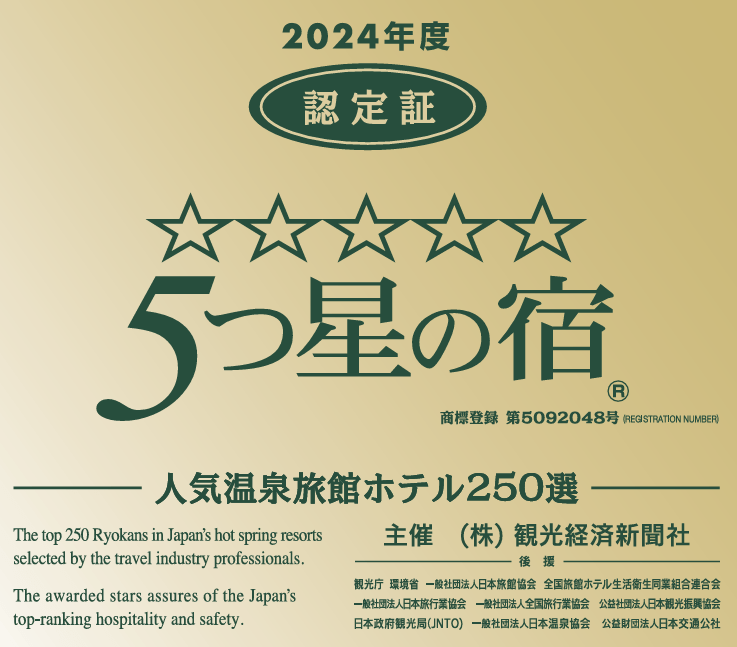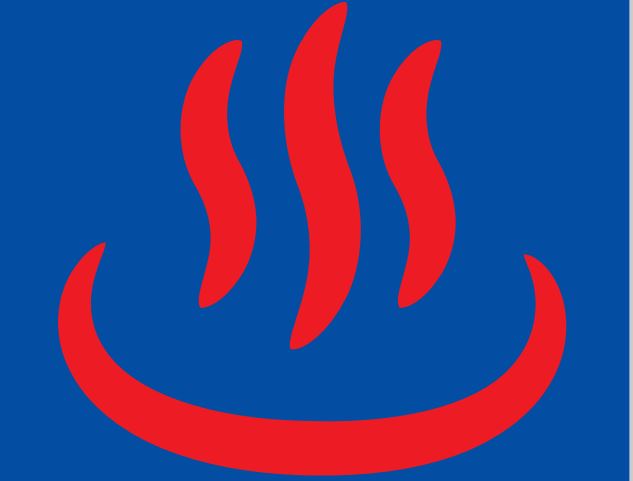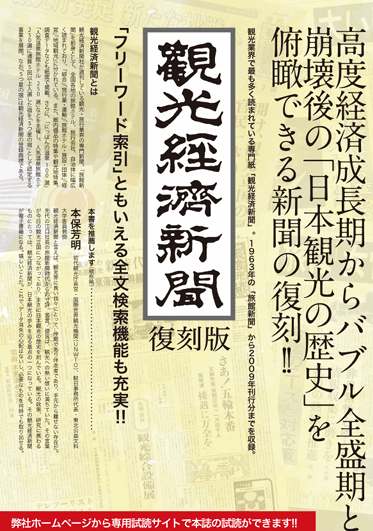「旅館こうろ」でいただいた、京料理の3回目。
「炊き合せ」は「坊ちゃん南京釜盛り」。くり抜いた手のひらサイズのカボチャに、車エビと夏野菜が盛られ、べっ甲あめがかかったもの。
野菜の一つは、賀茂茄子(なす)。風味の素晴らしさが江戸時代の記録にも残されている「京の伝統野菜」だ。平成元年にスタートした「京のブランド産品」に最初に認定された7品目に入っており、京都市が上賀茂地区の農家に種子の保存を委託している重要な品種。
真ん丸の球形で直径12~15センチメートルと大型。身が詰まってずっしりと重く、皮も軟らかい。その美しさとおいしさから、日本に180品種以上あるといわれるナスの中で女王と称される。
もう一つの万願寺甘とうも平成元年に「京のブランド産品」に選ばれている。歴史は比較的新しく、大正末期ごろ、伏見とうがらしと外来の大型唐辛子が交雑してできたと考えられているため、「明治以前に導入されたもの」という「京の伝統野菜」の定義には当たらず、「京の伝統野菜に準じるもの」に分類される。
大きく肉厚で軟らかく、甘味があるのが特徴。だが、「万願寺唐辛子」は辛くないと思って食べて、たまに「当たり」に出くわしてヒーヒー言ってしまうことがある。それは舞鶴市万願寺付近で栽培される正真正銘の「万願寺甘とう」ではないから。ホンモノは、京都府農林センターが品種改良を重ね、辛味遺伝子を完璧に取り除いているから、辛いワケがないのだ。
「こうろ」のコース料理に戻ろう。続いて「鱧(はも)しゃぶ」が登場。鱧は京の夏に欠かせない食材だ。「鱧は梅雨の雨を飲んでうまくなる」といわれ、ちょうど梅雨の明ける祇園祭のころ旬を迎える。古くから京都では、この時期鱧料理で客人をもてなす習慣があったそうで、祇園祭のことを「鱧祭り」とも呼ぶそうだ。でも、なぜ京都で鱧なのか?
かつて若狭湾から海産物を都へ運んだ「鯖(さば)街道」は有名だが、瀬戸内海からも魚が運ばれた。夏の暑い時期、生きたまま到着したのは鱧だけだったそうだ。鰻同様、生命力の強い魚を食べると精が付くと考えられていた上、京の人々にとって夏場の貴重な海の幸でもあった鱧が、好んで食されたのは当然だ。
骨切りした鱧をさっと湯にくぐらせ、花を咲かせるタイプのしゃぶしゃぶがほとんどだが、「こうろ」では驚きの鱧が登場した。黒い皿が透けて見え、薄造りのようになっていたのだ。通常の大きさで約3500本もあるという鱧の骨をよけてこういう状態にできるのは、よほど熟練の料理人でないと難しいらしい。
湯葉や豆腐とともに添えられた京水菜は、「京の伝統野菜」かつ「京のブランド産品」。江戸時代以前から栽培され、魚や肉の臭みを取る働きがあるそうだ。
伝統と技術に裏打ちされた口福の提供には、料理長の力量も必要だが、経営者の料理やもてなしに対する哲学によるところが大きい。北原会長、達馬社長、ごちそうさまでした!
※宿泊料飲施設ジャーナリスト。数多くの取材経験を生かし、旅館・ホテル、レストランのプロデュースやメニュー開発、ホスピタリティ研修なども手掛ける。