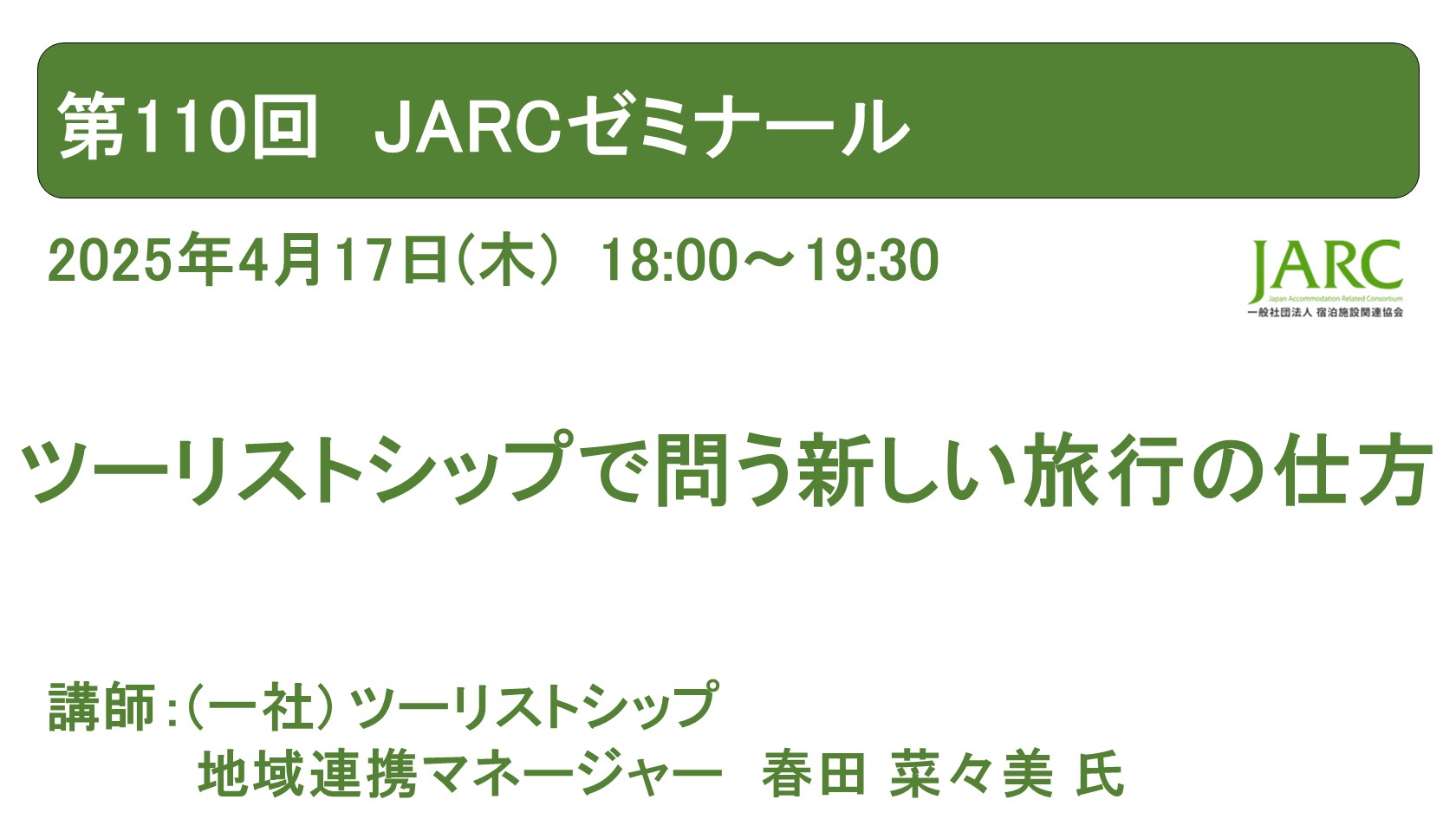観光経済新聞社が主催、旅行会社やOTAの社員など「旅のプロ」の投票によって選ばれる「にっぽんの温泉100選」は、1987年の第1回開催以降、38年間にわたり毎年絶えることなく継続してきた。改めて振り返ってみると、時代ごとの温泉地に関する様相や、志向性の変容を把握することができる。そこで今回は、温泉観光学を専門とする杏林大学外国語学部観光交流文化学科の小堀貴亮教授に、調査開始以降の温泉地を取り巻く社会的背景を考察した上で、第1回~第38回までのランキング結果について時代ごとに振り返っていただいた。
温泉地および温泉旅行を取り巻く社会的背景
にっぽんの温泉100選のランキング結果を分析する前に、本調査開始から現在に至るまでの温泉地を取り巻く社会的背景について概観したい。まず、開始初年度の1987年から約10年間は、いわゆるバブル時代からその終えんを迎えたころであり、温泉旅行を含む国民の観光志向性に顕著な変容が生じた時期である。飛行機・新幹線・高速道路などの高速交通網は、全国各地に張り巡らされ、遠隔地の温泉地へ格安で行ける機会が増すとともに、自家用車での遠出がしやすくなり、家族連れや友人連れ、あるいは個人で気軽に温泉旅行を楽しむようになってきた。また、大都市周辺地域を中心に、都市住民の日帰り観光圏が各地で放射状に拡大し、多様かつ広範囲な日帰り観光が可能となってきた。ここに、個人レベルでの温泉志向性が多様化し、共同浴場や露天風呂のある個性的な温泉地や交通便利な日帰り温泉地などが、多くの客を集める傾向が出てきた。このような背景の中で、88年の「ふるさと創生1億円事業」では多くの自治体で温泉開発が行われ、今まで温泉資源とは疎遠であった地域においても特色ある温泉地の誕生が相次いだ。当時、地下1千メートルを超える大深度掘削が可能となった温泉掘削技術の導入により、第3セクター方式による日帰り温泉施設が急増し、宿泊・日帰り問わず過当競争ともいえる状況になりつつあった。こうした温泉施設の増加は、温泉旅行の行動形態を大きく変えることになり、既存温泉観光地に対してもプラスとマイナスの両面から多大の影響を与えてきた。
こうした中で、その伝統性ゆえに旅館や各種温泉施設などの老朽化が著しく、寂れた温泉地というイメージが強かった湯治場は、従来の固定化した湯治客が近くの日帰り温泉施設などへ流出して経営が苦しくなるところも増えつつあった。さらに湯治場を特色付ける自炊施設は閉鎖され、低料金で長期滞在可能な自炊湯治は急減した。そして、賄い付きの旅館部に宿泊する湯治客も、長期の宿泊形態から短期の保養・観光的温泉利用へと変化してきた。
一方では、温泉地に対する目の肥えたニーズの増加や国民の健康志向性の高まりなどもあり、地域性豊かな湯治場や保養温泉地が高く評価されるようになる中で、いわゆる「現代的湯治場」を目指した新しい保養温泉地の在り方が模索されるようになった。さまざまな側面から観光志向性の変化が生じる中で、温泉地においても本来の在り方が見直されるようになり、かつて観光地化に遅れをとった療養・保養型の小規模な温泉地が、逆にニーズの脚光を浴び始めたのである。
国民の温泉旅行人気は昔も今も変わることはないが、先述したような旅行形態の変化とともにその志向性も多様化してきた。また、近年では温泉旅行の目的として観光から保養への志向性がますます強まりつつあり、温泉地選定の際の理由も性別・年齢に関係なく「温泉資源」「温泉情緒」「自然環境」が主たるものとなっている。すなわち、温泉地に望む施設も露天風呂をはじめ、自然景観・郷土料理・外湯・歴史的町並みなど、温泉地を特色付ける地域性の高い施設や保全された地域環境が求められるとともに、癒やしやストレス解消がなにより期待されている。天与の恵みたる豊かな温泉資源に加えて、優れた地域環境を有する現代版湯治場は、まさにこうした健康志向型の保養温泉地として最適であり、実際に湯治効果も期待されよう。
このような中、環境省において2017年に「自然等の地域資源を生かした温泉地の活性化に関する有識者会議」の中で「新・湯治」という概念が提唱された。それは現代のライフスタイルにあった温泉地の過ごし方、すなわち、温泉地周辺の地域資源を多くの人が楽しみ、温泉地に滞在することを通じて心身ともにリフレッシュすること、そして温泉地を多くの人が訪れることで、温泉地自身のにぎわいを生み出していくことを目指して提案されたものである。有識者会議では、新・湯治を提供する場としての温泉地をつくるプランとして、新・湯治推進プランが提案され、全国の温泉地においてさまざまな取り組みが実施されるとともに、その効果と意義が検証されている。
しかし、20年より発生した全世界における新型コロナウイルスの感染拡大が、観光産業全体に多大なダメージと低迷をもたらすことになり、温泉地では宿泊者の減少や宿泊施設の廃業に陥る大惨事となった。あれから5年を経て、温泉地をはじめとする観光地域や観光産業は急速な復興を遂げ、新しい日常を迎えるとともに、温泉地の過ごし方においてもより健康志向の高まりがみられるようになった。いわゆる「ウェルネスツーリズム」の舞台としても日本の温泉地は国内外から注目されるようになり、今や世界中からのインバウンド客を受け入れる観光大国・日本において、唯一無二の独自性を有する温泉文化の魅力は世界に広がりつつある。
各時期におけるベスト10の推移と地域的特性
ここでは、第1回から第38回までを大きく四つの時期(第1期:1987~99年、第2期:2000~09年、第3期:10~19年、第4期:20~24年)に区分し、それぞれの時期ごとに点数化を施し、上位温泉地を概観する。その際、これまで一度もランク外を経験しない温泉地を対象とし、各回での順位をそのまま得点化(ランキング1位は1点、以下同様に得点を与え、10位であれば10点)、合計点の少ない順に上位とする。なお、1991年に第2位、翌92年に第1位になって以後2001年まで10年間第1位を独占、02年以後は名誉入選扱いとなった古牧温泉は、他の温泉地と同様に取り扱いがたいことから、ここでの分析では除外した。
では、第1期にあたる1987~99年を代表する人気温泉地について概観しよう。ランキング上位順からベスト10をあげると、和倉・雲仙・登別・山代・銀山・こんぴら・指宿・道後・秋保・あつみとなる。中でもこの時期に卓越した人気を集めたのが和倉である。開始年から5年連続第1位となり、その後も常にベスト10を維持している。そのほか、この期間一度も10位以下を経験していない雲仙をはじめ、指宿・登別・別府・玉造・山代・道後・下呂等の温泉地が時期を通して10位以内の常連となっており、比較的規模が大きい歴史的名湯が名を連ねている。なお、この時期の最終年である99年には、その後上位を独占する草津が第9位にランクインしている。
続いて第2期にあたる2000~09年のランキングを概観しよう。この時期を代表する人気温泉地についてランキング上位順からベスト10を挙げると、草津・登別・由布院・指宿・和倉・下呂・道後・黒川・別府・有馬となる。この時期におけるランキング上位には大きな変化がみられ、先述した草津が00年に3位、01年と02年には2位と急上昇し、03年に初の1位となってからはその地位を一度も譲らず今日に至っている。また、由布院・黒川という九州を代表する人気温泉地がこの時期にランクインし、以降は常に上位を維持することになる。そのほかのランキングにはさほど大きな変化はなく、この期間に1度もベスト10から落ちていない登別をはじめ、指宿・和倉・下呂・道後・有馬等の各温泉地が時期を通してベスト10の常連となっている。
さらに第3期にあたる10~19年のランキングをみると、第1位の草津をはじめ、由布院・別府・下呂・登別・指宿・有馬・道後・黒川・城崎など、ランキング上位に大きな変化はみられない。なお、01年に初めてベスト10入りして以来、度々その地位を維持してきた歴史的名湯・城崎が第10位にランクインしている。温泉資源そのものの価値がますます重視されるようになり、草津温泉のような質・量ともに極めて高い温泉資源性を誇る温泉地がトップの地位を不動のものとしている。由布院温泉は、田園景観を基調とした美しい地域環境が高く評価されており、黒川温泉も自然豊かで閑静な山間部の温泉地という地域性が、都市住民を中心に人気を博している。温泉旅行の実態と温泉地に対する志向性をみると、心身の疲れを癒やすためにふさわしい環境が整った本格的な保養温泉地を求める傾向がみられるようである。
そして20年、すなわち新型コロナウイルス感染拡大以降を第4期として、最新5年間のランキングをみると、コロナ禍前後においても上位のランキング自体には大きな変化がなく、草津・下呂・別府・道後・有馬・登別・指宿・城崎・由布院はランクインを維持しているが、ここで世界に名だたる国際的温泉地・箱根が初めてベスト10入り(8位)している。なお、箱根は意外なことに本調査開始以来なかなかベスト10に入ることがなく、13年に1度9位にランクインしたものの、その後はしばらくベスト10から外れた時期が続いた。しかし19年に再び9位にランクインしてからは急上昇し、常にベスト10を維持している。
このようにランキングを時系列に分析すると、温泉地の人気の推移や変化が明らかになってくる。最後に、上述した時期別ベスト10を作成したのと同様の方法により、第1回から第38回までの総合点により、総合ランキング・ベスト10をみよう。
総合順位の第1位は登別で、これまで38年間にわたり常に上位にランクインし続けてきた安定感は卓越しており、その結果が示された。以下、指宿・和倉・道後・草津・下呂・別府・由布院・雲仙・有馬となっており、各時期において上位にランクインしてきた人気温泉地が名を連ねている。さらにベスト20まで見渡してみると、一時期あるいは数年間かなり高い評価を得ている温泉地がかなりみられる。長年にわたり一定以上の高い評価を得ていることは、それぞれの時代背景やニーズの志向性にうまく適合させながらも、各地域の有する豊かな温泉資源はもとより、貴重な歴史文化や美しい自然環境などの地域的特性を十分に生かした温泉地域づくりが積み重ねられてきたことの証であるといえよう。
今後も温泉地域の様相や温泉旅行の動向は、時代ごとにさまざまな変容が想定されるが、引き続きにっぽんの温泉100選の結果を追い続けていきながらその傾向を把握していき、人気温泉地たる魅力とその秘訣を探っていきたい。

小堀貴亮氏(こぼり・たかあき)
千葉大学大学院修了、現在は杏林大学外国語学部観光交流文化学科教授、博士(学術)。中央温泉研究所理事、日本温泉協会学術部委員も務める。主著に「観光地理学―観光地域の形成と課題―」(同文舘出版)など。