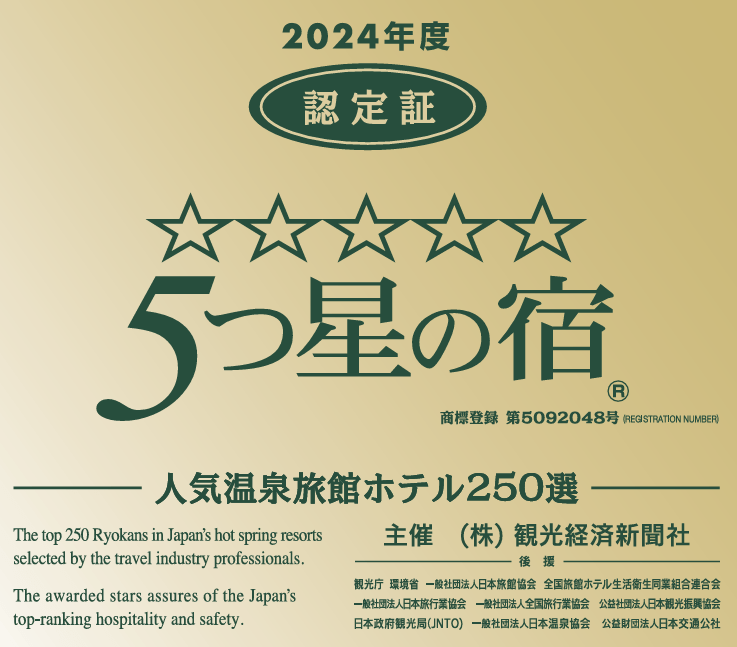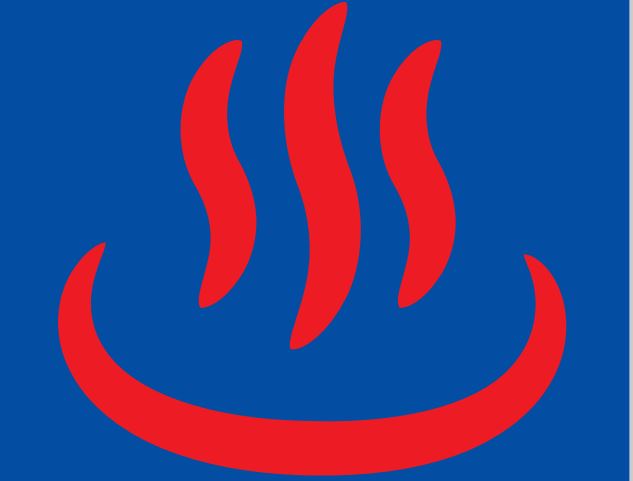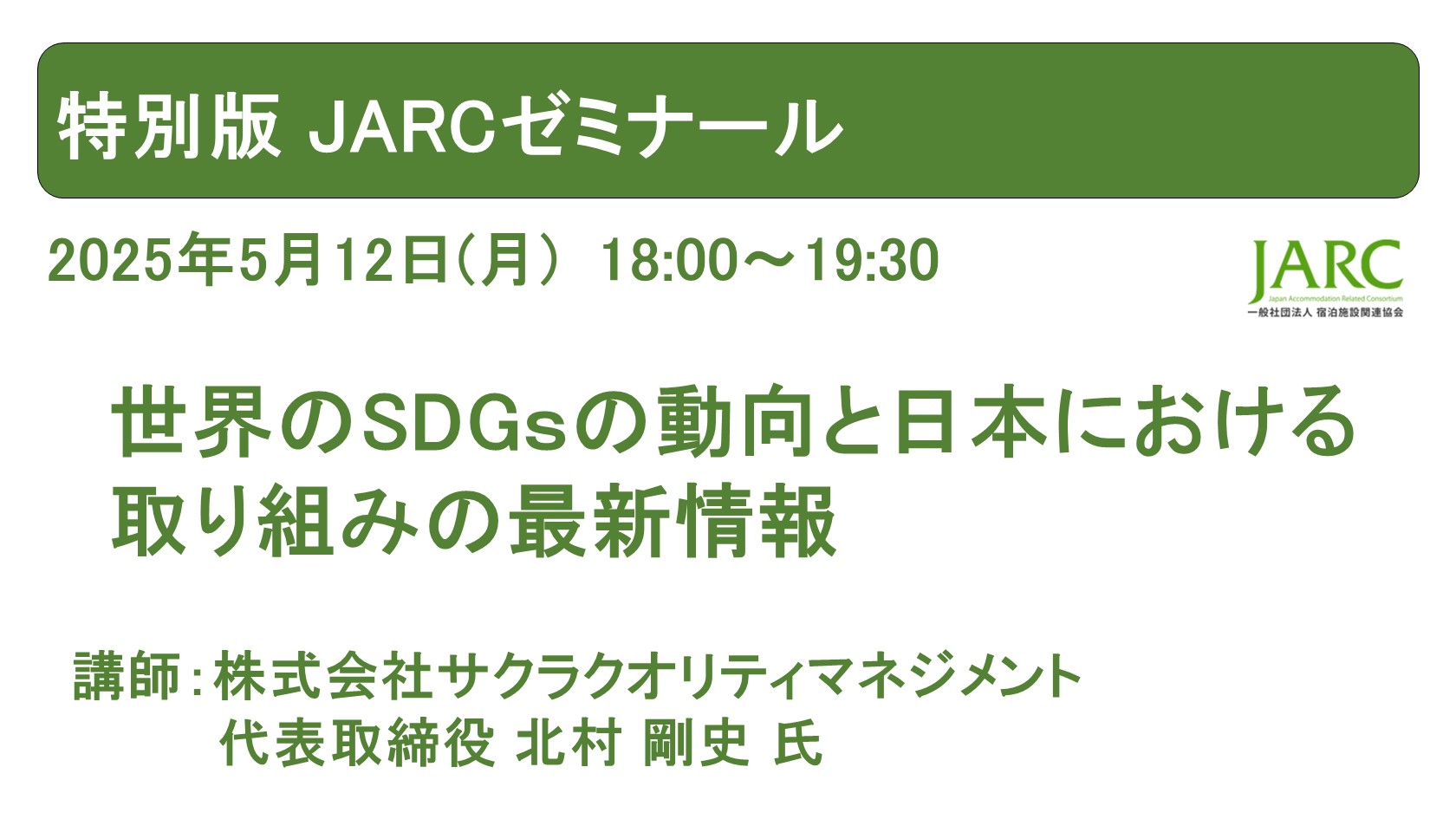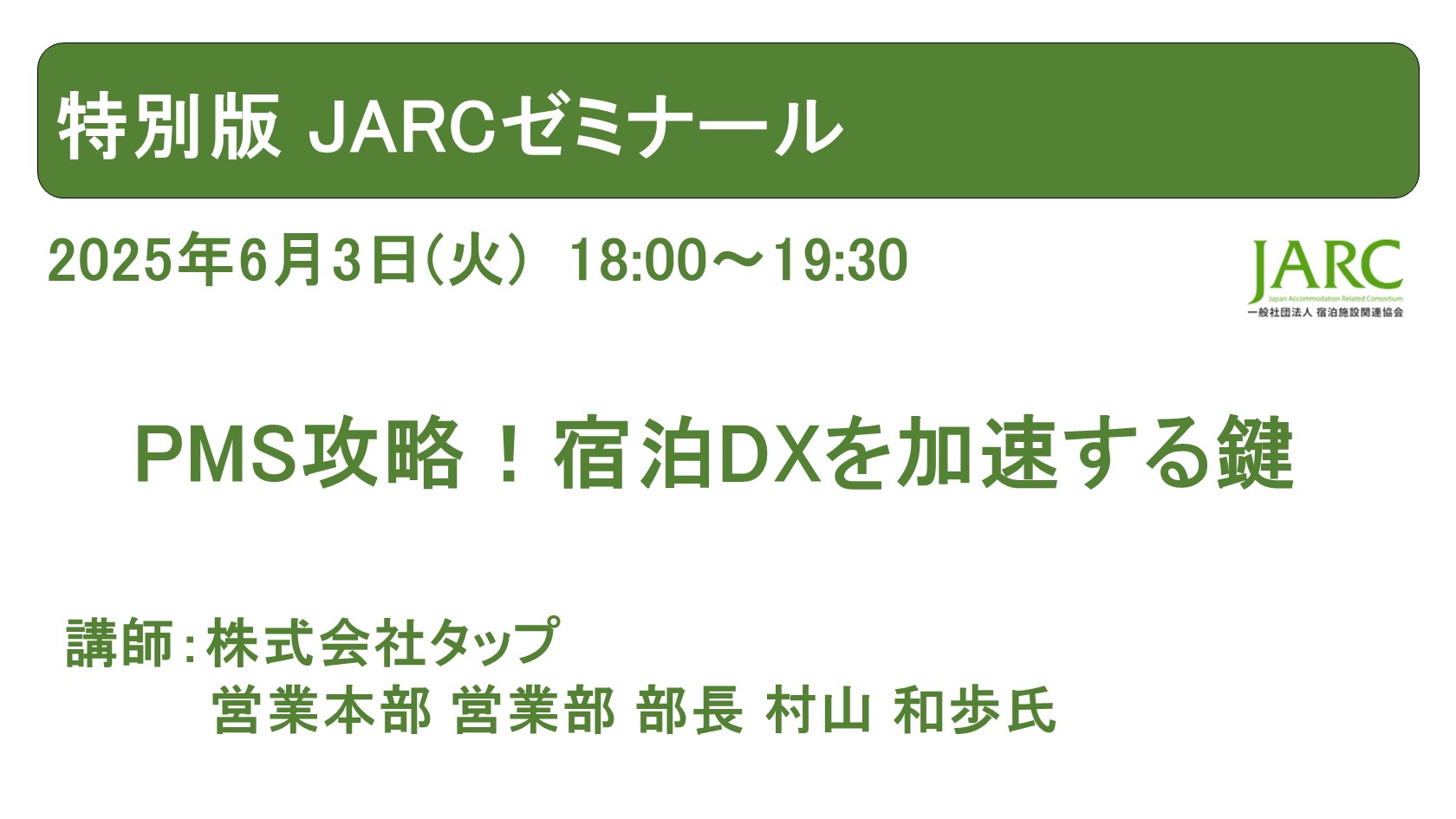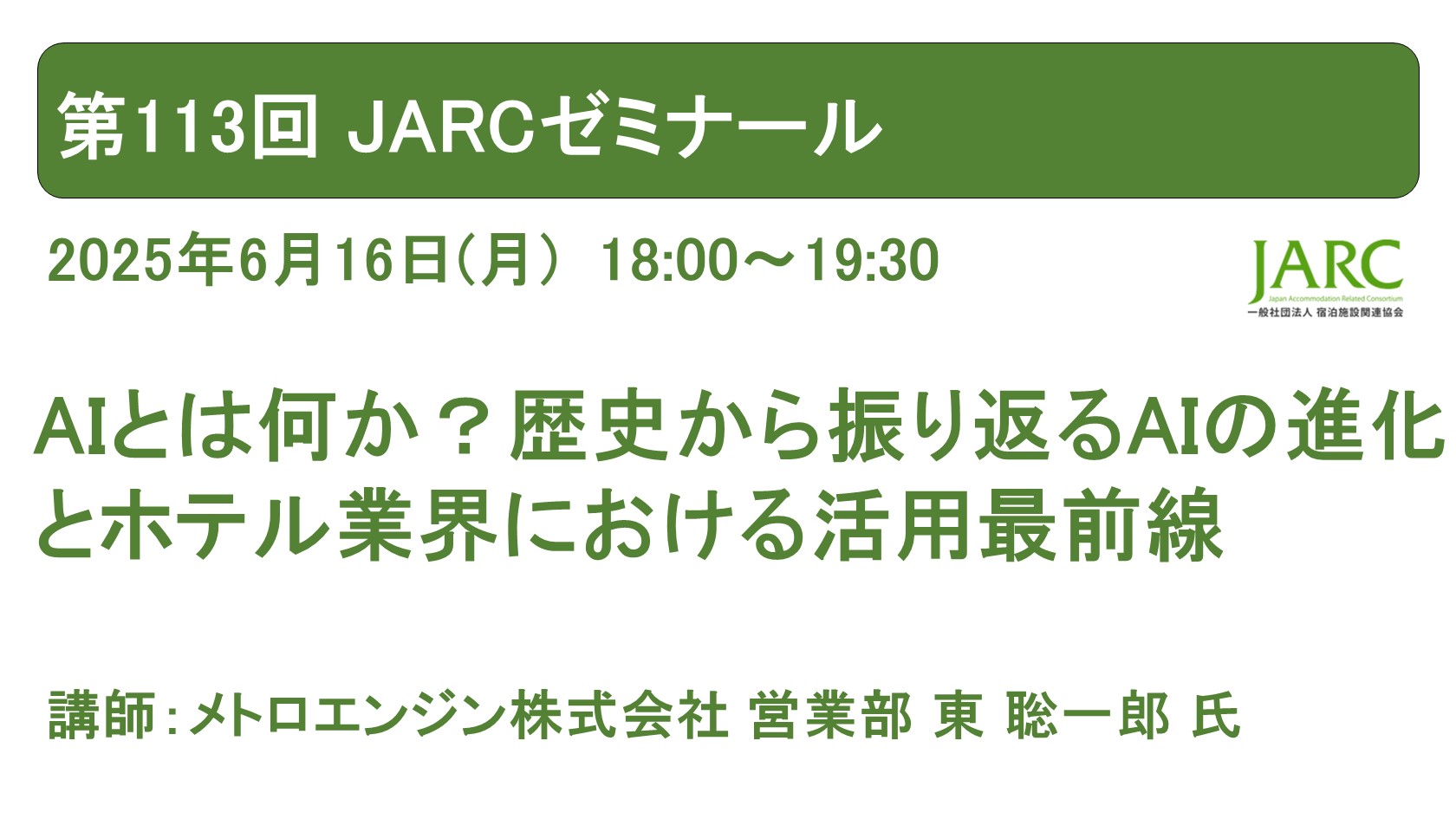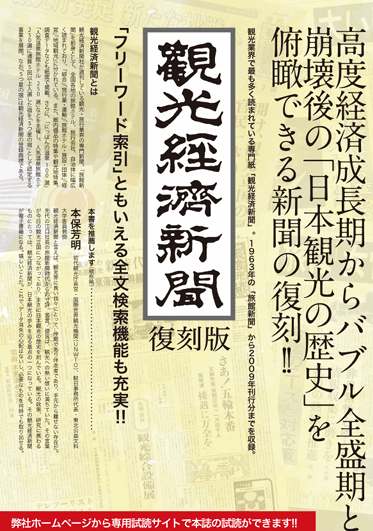近所のコンビニエンスストアでの話。その店の女性スタッフは、おつりを渡すときに必ず客の手を軽く握る。年の頃は30歳前後、色白で小太りの女性は笑顔もなく、ぶっきらぼうに右手でつり銭を握り、つり銭を客の手のひらに乗せるときに添えた左手を客の手の甲にグイッと押し付けるのだ。湿り気を帯びたジトリとした感触が背筋を凍らせる。
接客時の身体接触は、風俗営業は別としても、場合によっては顧客満足度を向上させる効果がある。たとえば、バーやスナックで、女性スタッフが男性客の膝上あたりにそっと手をおけば、男性客は特別感を覚える。カラオケスナックで、男性客が顔を近づけてデュエットをするのも、「そういうことが許される店」と一般的に認識されているからだろう。
だが、最近では、店の女性スタッフが自発的に行う接触行為は許されても、男性客が女性スタッフに対し必要以上に触れたり、人格を傷付けるような暴言を吐いたりすることはハラスメントに当たると、指摘する声もある。
「接客業を生業とする女性は、触れられてもいいと思っているんじゃないの」、あるいは「そういう店なのだから、ある程度の言葉遊びはするでしょう」といった考えは危うい。そもそもバーやスナックは、会話を楽しむ店であり、「そういうことが許される店」ではないのだ。
旅館の接客係も然り。以前は旅館の仲居に身体的接触を求める輩も少なくなかった。昭和時代、仲居の給料は男性客が個別に支払うチップ(奉仕料)によって賄われていた。当時の宿泊客は全員が男性で、女性客が主流になったのはバブル経済以降である。
奉仕料制と呼ばれる仲居の報酬システムは欧米のチップ制同様、雇い主(旅館)から月給のようにあらかじめ決められた金額が支払われることは一切なかった。仲居の日々の暮らしは、客からのチップと飲料売り上げ等のバックマージンによって補われていた。そのため収入は、仲居(北陸地方では接待さんとも呼ぶ)個人の力量や接客した客筋によっても変わり、生活は安定しなかった。
そこで、旅館業界は経営の健全化に乗り出し、働く女性の人権を守るため奉仕料制を廃止し、月ごとに賃金を支払う月給制を導入したのである。
このとき「仲居」の呼称を変更し、新しい時代にふさわしい名称に変更しようとする動きが生まれた。全国的には定着しなかったが新潟の温泉地等で使用されている「アスティ」という名称もこの時期に誕生したものだ。
しかし、ここにきてテレビドラマや旅番組等で「仲居」の呼び名が頻繁に使われるせいか、「仲居」に対する抵抗感はかなり薄れてきているようだ。背景には「仲居は酌婦ではない」と仲居自身が毅然とした態度で接してきたことも「仲居」の呼び名が市民権を得た理由とも言えるだろう。
たかが呼称、されど呼称。指導している旅館のサービススタッフを「仲居」と呼ぶかどうかは悩ましいところだ。