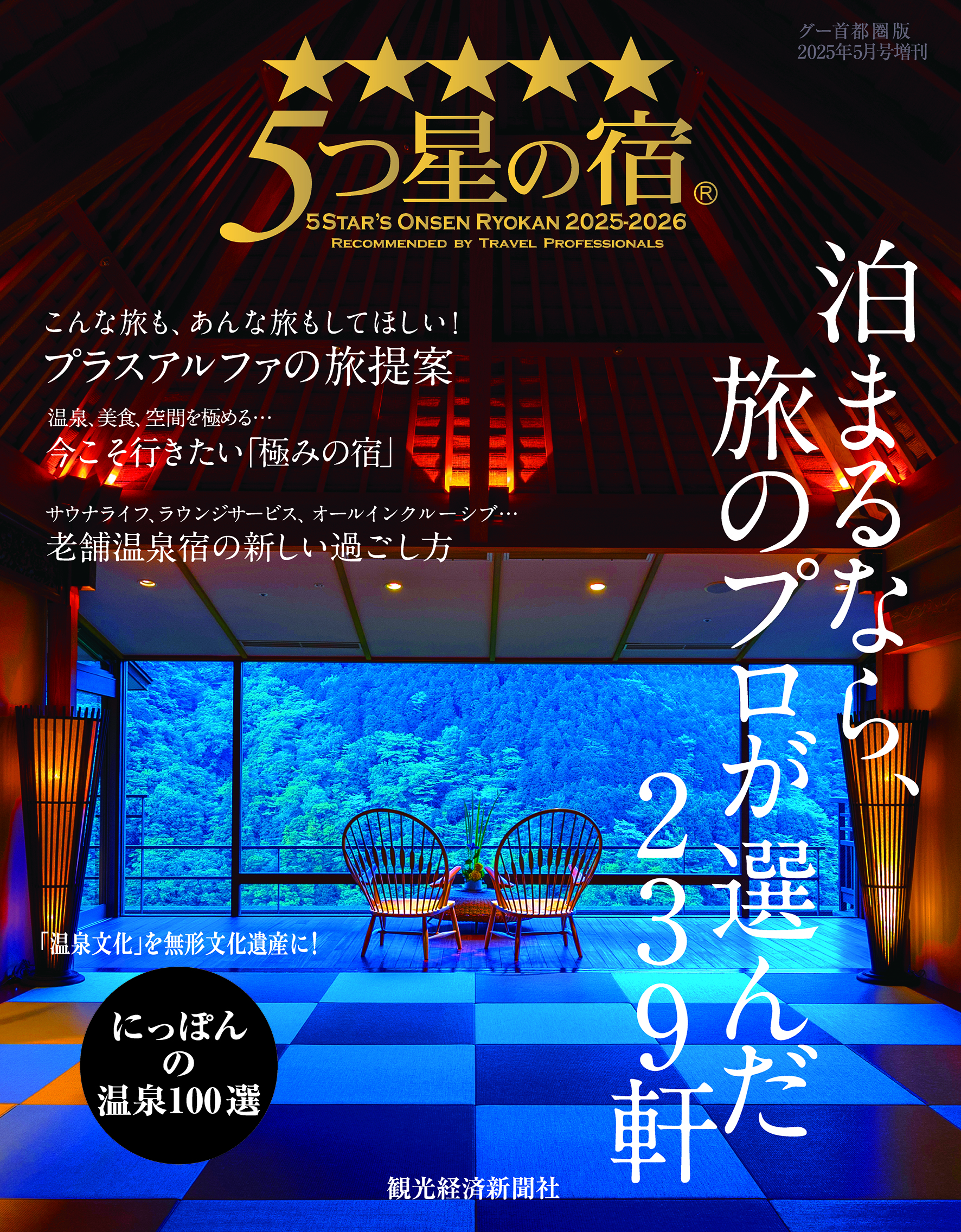JTB社長 山北栄二郎氏(左)とJTB協定旅館ホテル連盟会長 宮﨑光彦氏
JTB協定旅館ホテル連盟の2024年度通常総会が6月5日に東京都新宿区の京王プラザホテルで開催される。この総会に向けて今年もJTBの山北栄二郎社長とJTB旅ホ連の宮﨑光彦会長が対談。宿泊増売やサステナビリティ推進などを目的とする相互協力「戦略的パートナーシップ」について活発な意見交換が行われた。
――(司会・編集部 板津昌義)まずは23年度の国内旅行の市場動向についてお聞きしたい。
山北 この1年間で国内旅行は大きな回復を見せた。国内宿泊環境はコロナ前を超え堅調に推移したと言えるだろう。その前の年までは全国旅行支援など政府の支援に基づいた回復が大きかったが、昨年は第1四半期こそ旅行支援の反動減や、8月は台風の影響でやや減少したが、夏場から回復基調になり、インバウンドの回復効果の追い風と、団体がかなり伸びたのが特徴だ。延べ宿泊者数(全体)は、5億9275万人泊、そのうち日本人延べ宿泊者数は4億7842万人泊、外国人の延べ宿泊者数は1億1434万人泊と、外国人が非常に伸びてきたことも昨年の特徴と言える。
また外国人宿泊者数を19年度と比較したところ、三大都市圏(東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫の8都府県)で13・6%増、一方、地方部(三大都市圏以外の道県)は25・9%減、三大都市圏と地方の差が顕著に出た。地方でも人気を博したところはたくさんあるが、全体で見ると都市圏の伸びの方が大きかった。

JTB社長 山北栄二郎氏(左)とJTB協定旅館ホテル連盟会長 宮﨑光彦氏
宮﨑 昨年5月にコロナが5類感染症に移行となって、徐々に19年度の実績に近い形になってきた。エリアによっては既にコロナ前を超える宿泊者数まで増加している。従来はマイクロツーリズムが主体だったが、県をまたがるアプローチ付きのロング商品の販売が伸び、個人旅行が増えてきたと旅行会社からも聞いている。いよいよ人流が戻ってきた。
訪日インバウンドは10月以降、19年度を超えるような数字となっている。地方においても国際路線が復活してきたことが一つの理由だ。一方、団体旅行は従来の期待している数字にはまだ及んでいないが、教育旅行は完全に回復したことを実感している。
コロナ禍によってこの3年間は、宿泊業界では大変なことが起こった。宿泊需要の消失を経験した一方で、企業維持のために借入金は増えてきた。ゼロゼロ融資が終わって返済の時期になってきているが、廃業や倒産が後を絶たないという悲しい事実もある。さらに、人手不足問題も継続して残っている。

JTB協定旅館ホテル連盟会長 宮﨑光彦氏
――旅行需要が回復してきた23年度、JTBの国内旅行販売の状況は。
山北 マーケットの伸びに応じてJTBも大きく数字を伸ばしてきた。お客さまの傾向としてWebへのシフトがかなり進んだ。店舗に来られるお客さまも減ってはいないが、OMOの取り組みの成果もあり、Webの数字がリアルよりも大きく伸びた。
また、教育旅行においても、コロナ禍にさまざまな学校とのお付き合いを深め、体験型コンテンツを拡充、提案を続けたことで、従来は行かなかった地域への訪問を増やすことができた。さらに販売も伸ばすことができた。
個人のマーケットにおいては、全国各地を対象としたキャンペーンなど一般的なプロモーションに加えて、DX化の推進と着地に根差した観光地開発を続けてきたことが結果につながり数字が伸びた。旅ホ連の皆さまと一緒になって「戦略的パートナーシップ」という言い方をしているが、「新・4つのお願い」などを通して地域行政とのつながりを深めたり、地域コンテンツを一緒に開発し、またその発信にも直接関わっていただいた。旅ホ連会員の皆さまによるこうした取り組みの積み重ねのおかげで、19年度実績を超え、宿泊販売目標を達成できたのは非常に大きかった。改めて御礼を申し上げたい。
――宮﨑会長にとって昨年度は会長就任1年目だった。
宮﨑 重責を痛感している。JTBの多岐にわたる先進的な取り組みに対し、旅ホ連会員の多様な声や思いが反映されるよう努めたい。2年目も宿泊増売をともに伸ばし、人財育成や経営基盤強化につながる事業も着実に進めていきたい。
――23年度、旅ホ連ではどういった協業施策を行ったか。
宮﨑 JTBと旅ホ連会員との距離をもっと近くすることが、宿泊販売を伸ばす一番の近道だ。「JTBの商品作りに旅ホ連会員も一緒に参画しよう」と取り組んできた。私は「送客」ではなく、お客さまをつくる「創客」という意識を旅ホ連や地域の行政にもっと持ってもらいたいと考えている。地方は人口減少や超高齢化社会という問題を抱え、このままでは今後、地域は立ち行かない。それを下支えするのは、間違いなく観光だ。
前年度に続いて、「47DMC支店や各地の仕入販売部との連携強化」や「行政とJTBとの橋渡し」「地域のユニークな素材や取り組みの情報提供」「オンライン説明会や旅行先店舗での旅行相談への参画」というJTBからの「新・4つのお願い」に協力してきた。さらなる成果を期待したい。
――24年度は国内旅行の市場がどう動くと予測しているか。
山北 国内旅行の販売額は、引き続き上昇傾向となる一方で、昨年と比較すると微増にとどまる予測だ。一方、国内旅行の質は、大きく変わってくるだろう。一つは、インバウンドの増加だ。円安が続いている状況の中で、中国などの大きなマーケットが徐々に回復してくる。インバウンドを合わせた中で国内旅行をどうしていくかを考えなくてはいけない。
トピックスについては、今年は非常にたくさんある。北陸新幹線敦賀駅までの延伸が一つ。これにより人の流れが福井の方に行くため、ルートの開発にも一つ足掛かりができた。インバウンドも含めて北陸への流れを作っていく。そのほか東北や四国、九州などでのルート作りによって、地域分散型の旅行を推進したい。
来年度以降に黒部宇奈月キャニオンルートができることを想定して、地域の魅力を生かしたコンテンツ開発を今進めている。こういう形で地域ごとにオリジナルコンテンツを開発することで、消費単価のアップや滞在時間の増加などの方向に持っていきたい。
まだ、海外旅行に行きやすい環境下になりきっていないことが課題だ。国際交流がもっと双方向に動かないと本当の意味でインバウンドも良くなっていかない。
宮﨑 コロナが収束し人流制限が解除され、旅に出たいというニーズがどんどん高まり、実際に動いている。一方で、受け入れ側として一番の課題は人手不足対策だ。100%の受け入れをしたいが、対応できずに制限している施設もある。外食ができないエリアでは、地域全体として受け入れが伸びないということも大きな問題だ。会員に向けて、労働環境の整備などの面でも、旅ホ連としてさまざまなサポートをしていきたい。高付加価値化と生産性を向上して給与アップなどの待遇を改善していくか、また、いかにして働いて良かったという労働環境を作っていくかなどは、「働き方改革」と「働きがい改革」の二つの改革をしないといけない。それを強力に支援するのは観光業界のDX化だ。また、旅行者がストレスなく移動できる手段や、地域を楽しむ観光コンテンツの提供など、分野を広げたDX化が必要だ。
幸いJTBには「データコネクトHUB」や「Kotozna In―room」「JTB BOKUN」など、気軽に利用できる仕組みがあるので、それをもっと周知、かつ活用していきたい。生産性の向上のみならず、旅行者の利便性の向上も図りたい。
インバウンドについては確実に増えていく。地域づくりの視点としては、インバウンドのお客さまにも来てもらえる魅力のある地域づくりや、交通網などのインフラ整備が今後ますます必要だ。これは行政と一体となって開発をすることが極めて重要だ。
――訪日インバウンドも含めてJTBでは24年度の国内旅行販売にどう取り組むのか。
山北 インバウンドについては、たくさんのお客さまに日本に来てもらうことに加え、より長く滞在して、たくさん消費をしてもらうのが一番のポイントだ。そのためには、周遊するルーティングが大事だということで、先ほどルートづくりの話をした。また、消費単価が倍ぐらいあるという「アドベンチャーツーリズム」については、昨年度下期に「日本の旬」キャンペーンを実施してきたが、このキャンペーンを引き継いで各地域でアドベンチャーツーリズムのコンテンツ開発などを今進めている。
さらにインバウンド向けに進めなければならないのは、ナイトアクティビティの充実化を図ることだ。そのために地域開発自体にももっと関わっていきたい。地域開発を行うにあたっては大きな資本が必要になるため、観光立国ファンドや再生のファンドにも参画する。さまざまな形で私たちが観光を振興するという観点でしっかり関わってコンテンツの開発と滞在が充実するための開発に力を入れていきたい。
プロモーションは国内旅行の活性化に向けた日本の旬を継続して実施している。今年の上期は「北陸」をしっかりと推進し、復興にも寄与できる取り組みをJTB全体として行っていく。また、大阪・関西万博の機運醸成に向けたプロモーション強化も進めていきたい。
少し長い目で見ると、人々がサステナビリティに非常に関心を示しており、インバウンドの受け入れではサステナビリティへの取り組みが必須だ。隣国の韓国などでもかなり意識が高まってきているので、インバウンドの受け入れ競争ではサステナビリティ対応がしっかりできていることをどうアピールしていけるかどうかが重要だ。脱炭素の問題だけでなく、人権や生物多様性の問題などSDGsのゴールに含まれていることに関する意識が非常に高まっているので、そういった意識を業界全体で少しずつ高めていかないと国際競争力を失っていくかもしれない。
JTBのサステナブルツーリズムの取り組みの一環として、旅ホ連会員の皆さまと協力して「サステナブルな日本の観光」をしっかりとアピールできる体制にしていきたい。それを目指す「サステナブルツーリズムパートナーシップ協働宣言」を策定した。ぜひご支援いただきたい。
人権に関しては、JTBは「違いを価値に、世界をつなぐ。」というテーマで「DEIB」という多様性の取り組みに本腰を入れて強化している。LGBTQを含めて多様性への対応についても取り組んでいきたい。
――宿泊販売についてはどう伸ばすのか。
山北 地域の開発やWeb販売の強化といった、今、話してきたことを通じて宿泊販売を伸ばしていく。前年度目標比105・3%の宿泊販売目標を掲げたので、これを必ず達成する。全国均一での仕入営業のさらなる強化を実現するためにコンピテンシーモデルの構築と浸透に取り組む。個人、団体、Web、インバウンドの情報一元化による地域別、施設別ソリューション営業の具現化を図るとともに、仕入営業時間拡大のための後方支援体制の整備も行っていく。
――旅ホ連では24年度にJTBとの協業施策をどう進めていくのか。
宮﨑 前年度は宿泊販売目標をクリアしていただいたが、山北社長から先ほど24年度も前年度目標比105.3%の必達という力強いお言葉をいただいた。会員を代表して感謝申し上げたい。
24年度の旅ホ連の事業計画は「JTBとの戦略的パートナーシップによる宿泊増売と会員経営基盤の強化」を基本テーマとして掲げた。昨年のパートナーシップの強化をもう一歩踏み込んだ形で進めていくとの意味合いだが、その背景にあるのは、昨年12月に導入された新しい国内客室管理ツールだ。これを私は「令和の大改革」と言っているが、電算客室提供システムが半世紀ぶりに抜本的に改革された。「売れるときに売る」という販売価格をフレキシブルにする仕組みになった。宿泊施設もこれを生かして積極的に販売していこうという姿勢に変わってきているが、より以上に変わらないといけない。この「令和の大改革」がお客さまにとっても、宿泊施設にとっても、JTBにとっても、加えて地域にとっても良かったという”四方良し”につながり、この改革は大成功だったと言われるようにしたい。
そしてこれを進めるための「JTBとの相互取り組み」として、五つの依頼事項をいただいている。具体的には「早期施策の効果的展開に向けた提供客室数の維持、拡大」や「料金リバイスの徹底」「お客さまのニーズに合致した高額、高品質な未提供客室の提供」「訪日インバウンド販売拡大への協力」「法人団体販売に向けた品ぞろえと客室管理」だ。「新・4つのお願い」とともに、最大限協力していきたい。
――今年の元日に能登半島地震が起きた。この被災地に対するJTBの支援策は。
山北 心よりお見舞いを申し上げます。能登半島の地震は、観光産業全体に非常に大きなインパクトがあった。何とか全面的に支援をしていきたい。和倉から北部エリアはまだ復興途上で観光客を完全に受け入れられる状態にないが、それ以外の北陸地域で大きく風評被害が出た地域を盛り立てていくことが間接的に能登の復興につながっていく。上期は、北陸3県のキャンペーンを実施しているので全面的に盛り上げていきたい。「日本の旬」などのキャンペーンの中で地域のモビリティやコンテンツなどの開発、DXへの取り組み、ルートの開発などさまざまな取り組みが行われている。
それから事業パートナーの皆さまとの協業の動きも今できつつある。そういうことが必ず能登の日常が戻ってきた段階での復興につながるので、取り組みを強化、加速していきたい。
直接的な支援は正月明けからすぐに取り組み、5千万円を超える義援金を贈った。トラベルメンバーのトラベルポイントの還元によるお客さまからの寄付もいただいており、これも引き続き実施していきたい。
宮﨑 旅ホ連としても、中部支部連合会を中心に各所と連携を図り、義援金の募集などいろいろなサポートを行っている。各地の復旧、復興状況を見極めながら、全国各支部による持ち出し会議や研修旅行などもどんどん展開していく。
一方で、地震などの災害はいつどこで起こるか分からない中、旅ホ連ネット「やどこむ」では、例えば防災の方法や過去の事例など、役立つ情報の紹介をしている。東日本大震災や熊本地震の時に各会員や地域がどのように対応したのか、日頃どんなことをしておくべきか、ということの周知を図っている。
また昨年、日本旅行業協会(JATA)の「観光産業共通プラットフォーム」が立ち上がり、災害情報以外にも、いろいろな情報をこのサイトで共有できるようになった。まだ登録していない会員の皆さまにはぜひ登録をお願いしたい。JTBと協力して、また、行政とも連携して、企業自身のBCP(事業継続計画)と地域全体のBCPの推進を、今後も更新を図っていきたい。
――先ほど山北社長からサステナビリティの取り組みが重要という発言があった。この話をさらに深掘りしたい。JTBの取り組みをもう少し具体的に教えてほしい。
山北 これは地球規模でやっていくというグローバルでの取り組みだ。JTBはGSTC(グローバル・サステナブル・ツーリズム協議会)に理事として参加しており、GSTCの基準に基づいてさまざまな研修をこの1年間実施してきた。仕入部門の中でどういう取り組みを具体的にしていけばいいのかとか、どういうことが本当に環境に貢献できるのかなど、たくさんの学びがあったので、旅ホ連の皆さまとも一緒に取り組みを進めていきたい。
また、観光地のクリーンアップから始まった「地球いきいきプロジェクト」は、元気な未来を創造していく活動として、今は海外でも展開している。そこで旅行者の方に参加していただくというのが一つのポイントだ。そのような旅をする人を巻き込んだ取り組みも行っている。
具体的な目標を掲げることが非常に大事なため、スコープ1、2、3の目標値を定めている。スコープ1、2では2030年までに自社とそれに関連する部分のカーボンニュートラルを、スコープ3では50年までにサプライチェーンまでも含めたカーボンニュートラルを実現する計画だ。
また、「CO2ゼロMICE」や「CO2ゼロ旅行」という形でいろいろなツアーでカーボンオフセットの取り組みをやってきているが、これをより実質的にできるように進化させていきたい。非常に深いテーマであり、実際の事業に直接関わるところもたくさん出てくるため、しっかり具体的に話を進めていきたい。
宮﨑 旅ホ連のサステナビリティ推進の取り組みについては、まずは個々の会員施設がSDGsの認証を取るなど、しっかりと具体的な取り組みをしていこう、というのが一つだ。二つ目は、各地域の行政と連携した取り組みと考えている。例えば、愛媛県大洲市は国際認証「世界の持続可能な観光地」の「文化・伝統保存部門」で世界ナンバーワンを獲得したが、これは行政との連携の成果と言える。
そして三つ目としては、行政との取り組みと併せて、先ほど山北社長が話されたJTBの取り組みを一緒になって進めていく、ということだと考えている。これまでも、着地型の観光開発を各支部、各エリアで取り組んできたが、今後は「サステナブルな旅」をテーマとする取り組みへの支援を強化していきたい。「サステナブルな旅」は法人向けも含め商品としては作られているが、それをいかにマーケットに訴求させ、お客さまに利用してもらえるようにするかが課題だ。そのような取り組みを旅ホ連では引き続いてやっていきたい。
サステナビリティは「思いをいかに形にするか」ということが重要だ。個々の旅館ではフードロスも含め、いろいろ細かな取り組み指標を設けているが、それをクリアしていくことを支援するような形にしていきたい。
――旅館・ホテルでのサステナビリティ推進に対する意識は、実際のところ高まっているのか。
宮﨑 かなり高まってきている。サステナビリティの意識があるかないかで、仕事の仕方が全然違ってくる。一例だが、宴会でフードロスをなくすにはどうしたらいいかを常に意識をするようになっている。サステナビリティの取り組みを発信すると、それに賛同していただけるお客さまもお越しいただける。それはすなわち経済や経営の面以外に、価値向上の面でもメリットがあるんだ、という意識を持ち始めてきた、ということだ。以前とはステージが変わってきた。
山北 フードロスのほか、燃料の問題などもある。サステナビリティの意識は本当に旅館・ホテルの中でも高まってきている。それが先ほどのみんなで協力して体制を作っていくことにつながっている。一緒になってやっていくことがすごく大事だ。
――まずは民間から進めていく。それとも国が主導で進めていく。どちらがいいだろうか。
山北 両方だ。民間だけでできないもの、例えば燃料に問題があるとされると、宿泊施設のボイラーに問題があると捉えがちだが、航空燃料に関する問題の方が非常に大きな問題で、施策を本格的に導入するためにある程度の国の動きがないと難しい。そういうことはどんどん国も取り掛かってほしい。一つ一つの取り組みは民間から起きていかなくてはいけないということで、JTBも「サステナビリティ委員会」を作って各部門の人たちと常にディスカッションをしている。こういうことをすればできるよねとか、こうすればお客さまが共感してくださるよね、というようなことを具体的にたくさん作っていって、アクションにつなげていくことが大事だ。
宮﨑 日本はもともと大昔からサステナブルな取り組みをしてきた。「もったいない」という意識がそれだ。例えば、旅館・ホテルでは地産地消は当たり前のことなのだが、地域で採れたものをそこで上手に利用する、あるいは提供することで、物流の「2024年問題」もかなり解決できそうだ。地元の文化をいかに発信するかということも重要だ。国の数値目標はあるが、各旅館・ホテルで取り組めるものがたくさんあるので、それを分かりやすくメニュー化して実現できるような形に旅ホ連としてなんとかもっていきたい。
――総会を前に旅ホ連会員に向けてメッセージを。
山北 「戦略的パートナーシップ」ということで、これから旅ホ連会員の皆さまとのパートナーシップをより強化していく。コミュニケーションをより密にすることで共に考えていく。そのことをさらに強めていきたい。具体的には新・4つのお願いをはじめとして、DXをどうするか、人財の問題をどうするか、このような議論を本当に腹を割って話し合っていけるような関係にしていきたいので、引き続きよろしくお願いいたします。
宮﨑 戦略的パートナーシップという表現は外交ではよく使われるが、実はビジネスにおいても使われることが多い。それは双方の持っている資源をいかに生かしていくかということだが、旅ホ連とJTBが宿泊増売という共通の目標に向かって関係を進化させていけば、例えば、新しい商品ができる、そしてマーケットが広がる可能性がある。そういう強い関係性を今年度は再構築していきたい。結果的に、お客さま、JTB、旅ホ連、そして地域が良くなる”四方良し”の道筋を、旅ホ連の今回の総会を通じて示したい。