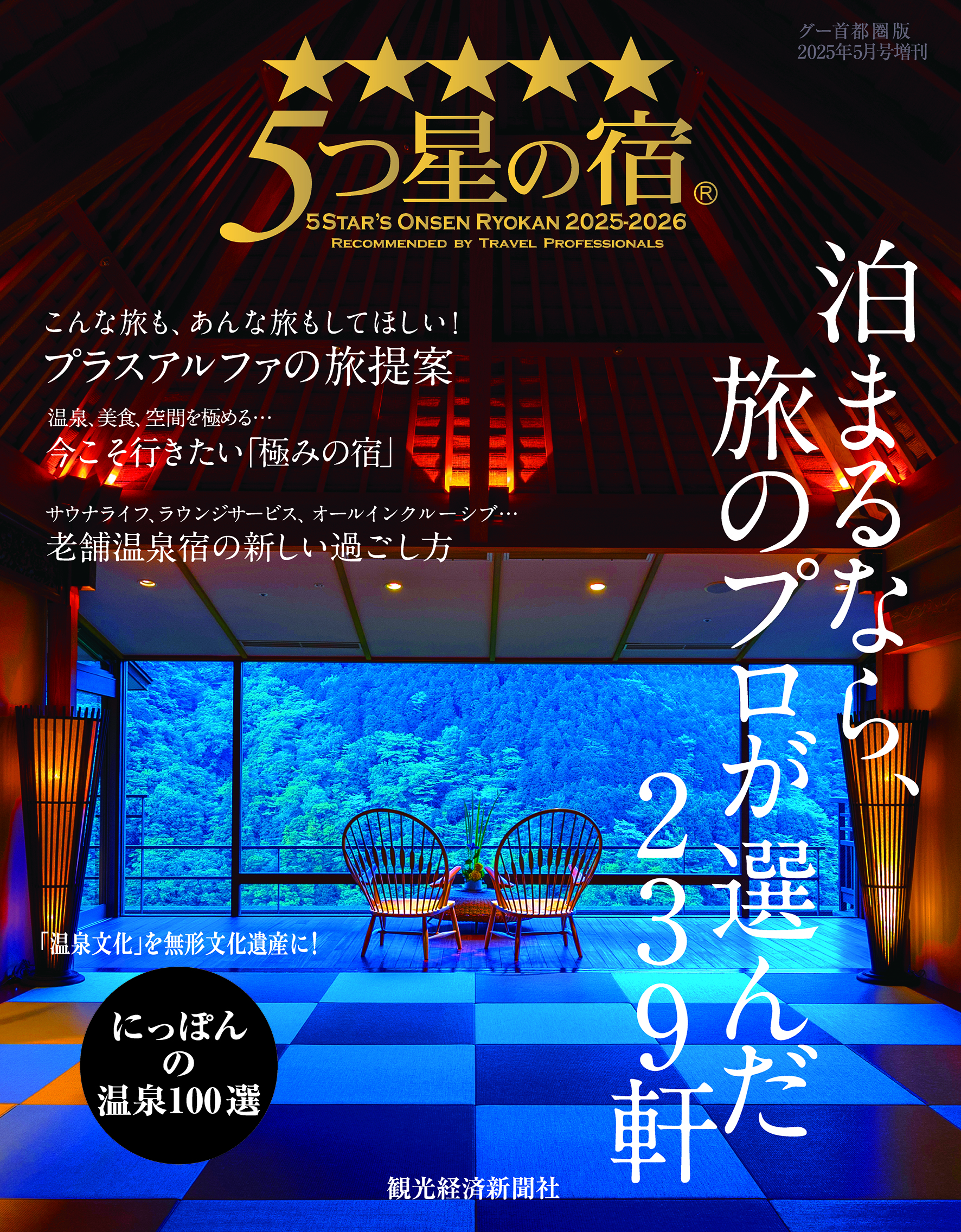玉川大学名誉教授・名桜大学特任教授 寺本潔氏
子ども時代からの観光人材育成を
宿泊税を徴収する自治体が増えてきている。財源が心もとない地方にとり、観光振興こそが起死回生の策であり、喜ばしい政策である。問題はその使途だ。観光客の利便性向上につながる多言語看板や公衆トイレ、駐車場整備など、あったら便利なインフラ整備に使いたくなるものだが、ずっと後回しになってきた地方の人材育成に大胆な使途を構想してほしい。
日本が観光先進国と呼ばれるためには、多岐にわたる観光の仕事や地域の発展につながる観光事象を肯定的に捉え、観光振興による地域活性化の学びを通して自己の考えを深める教育(観光教育)が必要だからだ。
人口減少と超高齢化に悩む地方においては、地域の魅力を価値に変える発想が特に重要で、子ども時代からの観光の学びにより、周囲の大人たちと協働して地域磨きに寄与できる人材の輩出が期待される。
筆者は最近、「観光市民」という造語を用いて、地域を元気にするために自分は何ができるのかを考える、いわば市民的資質(シチズンシップ)を指す人材育成を提起した(拙著「観光市民のつくり方」日本橋出版)。若者の大都市圏への流出を防ぎ地元への定着を促すためにも、シビック・プライドという誇りの醸成が期待される。
観光教育は従来のバスガイドやホテル、飲食、土産店に従事する実務者向けから、観光振興に関わる多様な職種の資質養成にかじが切られている。観光庁は観光地経営人材と観光産業人材の二種に分けて捉えているが、前者は地域のいわば観光応援団であり一般市民も含まれる。後者には、6次産業化が求められる1次、2次産業に従事する仕事も関連する。
筆者は北海道や高知、沖縄、新潟、長崎各県の観光地に立地する小中高校で観光の出前授業を過去10年展開してきたが、児童・生徒の親の職業が旅館業や土産物店経営、タクシー会社、農協・漁協であった場合が多かった。筆者の授業を通して観光振興に関わる親の仕事を広い視点から理解してもらう機会ともなった。
観光業が製造業と並んで基幹産業と呼ばれるためにも公教育における観光教育を開始しなくてはならない。指導者育成や教材開発、子どもガイド指導、観光スポット見学、各種プレゼンに要する消耗品等、それなりに費用がかかる。自宿泊税の数パーセントでよいから、観光教育の推進費として使わせてほしい。観光振興を支える人づくりこそ、実は地域の観光基本計画の軸に据えられるべき課題なのだ。

玉川大学名誉教授・名桜大学特任教授 寺本潔氏