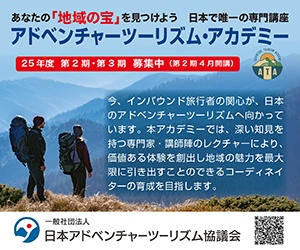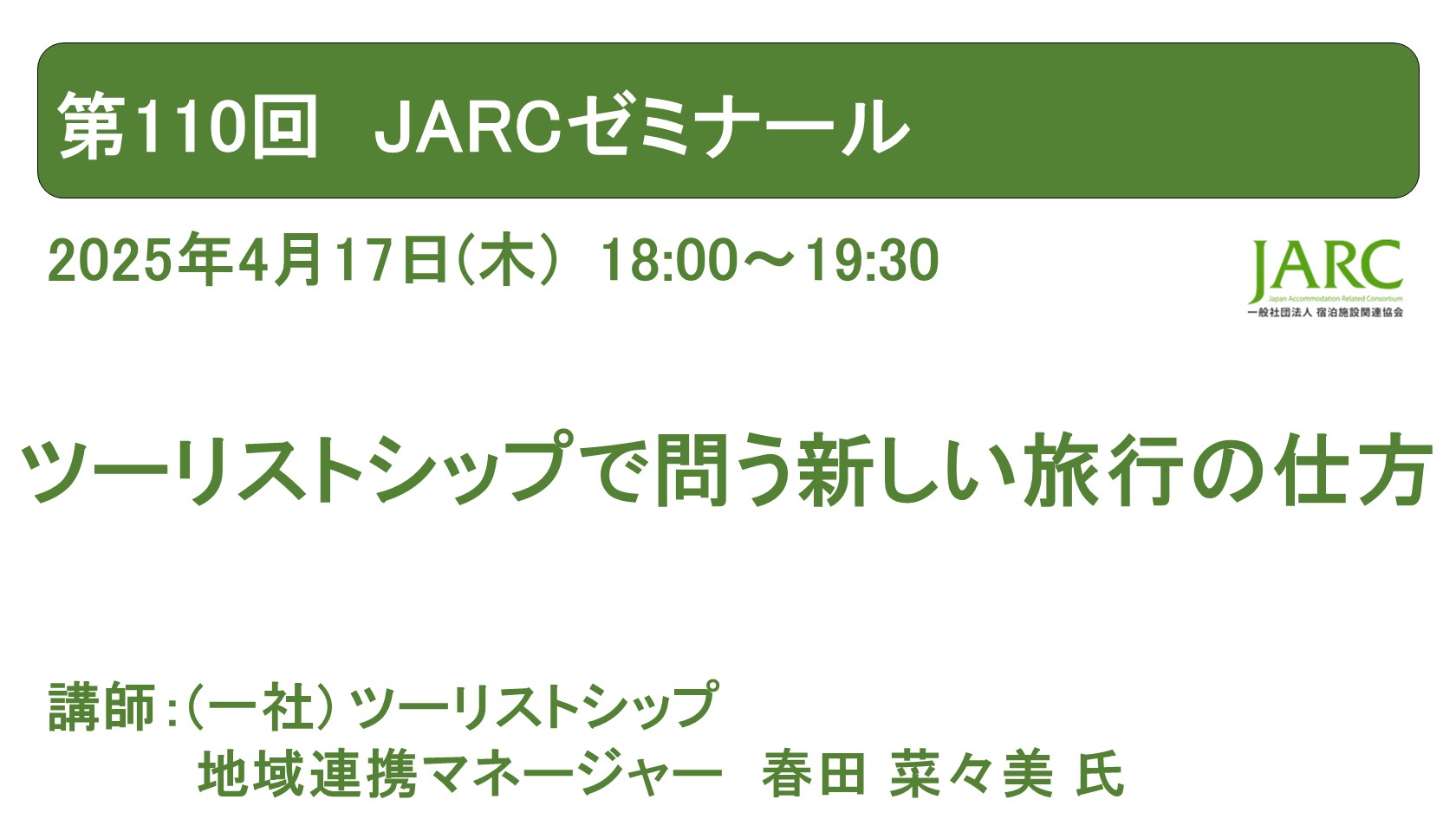(左から)星、山口、石坂各氏
CBT移行で受験者大幅増加 求人と就労の増が今後の課題
宿泊業界の人手不足解消に向けた外国人材の受け入れについて、宿泊4団体の役員らが尽力している。日本旅館協会労務委員会の山口敦史委員長(山形県天童温泉・ほほえみの宿滝の湯社長)、宿泊業技能試験センターの星永重監事(福島県湯野上温泉・藤龍館社長)、同センターの石坂亮介事務局長に話を伺った。
――これまでの活動について。
山口 人手不足解消のため、業界がまず議論したのが生産性の向上。問題を自らの手で解決しようとの取り組みだった。
しかしそれだけで解決は難しく、状況はさらに切迫してきた。そして対策として打ち出されたのが外国人材の活用だ。
われわれ宿泊業が受け入れ可能な外国人の在留資格は、以前は「技人国」(技術・人文知識・国際業務)。しかし技人国は通訳業務、マネジメントなどしかできず、一般的な接客やバックヤードなどの業務はできない。
そのため新たな資格を作ろうとの動きが2016年ころから始まり、宿泊分野での「技能実習」、そして「特定技能」がほぼ同時に制定された。
特定技能は19年4月に制度が始まり、われわれはこれを機に海外に出向いての外国人材とのマッチング事業を始めた。そしていよいよ人材が来るという時期にコロナ禍になってしまった。出鼻をくじかれ、そこから2~3年、何もできなくなってしまった。
コロナ禍が明けて、事業を復活させたが、われわれ宿泊業界は、人が欲しいと言う割には、外食や介護などほかの業種に比べて受け入れの数が今でも圧倒的に少ない。
現在、宿と就労者とのマッチングイベントを海外で引き続き行ったり、外国人材受け入れについての啓蒙活動を国内で行ったりしている。
星 私が外国人材の業務に関わったのが、全旅連青年部長の任期が終わった23年6月から。宿泊業技能試験センターの理事に就任させていただいた。
コロナ禍が明けて、海外の人たちが日本に来られるようになっても、宿泊業での就労になかなか結び付かない。一方で、他の業種でどんどん就労するなど、宿泊業よりも一歩進んだ状況となっていた。
原因を考えた時、特定技能の在留資格を得る試験の回数が他の業種に比べて圧倒的に少ないことが分かった。増やさなければと、まずは試験の方法を変えた。従来の紙ベースから、コンピューターベースのCBT(Computer Based Testing)形式に変えた。世界で試験運営を手掛け、世界の各都市に試験会場を持つプロメトリック社と提携して、同形式による試験を行うこととした。
試験問題もバージョンアップするべく、所管の観光庁と連携を密に取り組んだ。
23年度内のスタートを目標とした。ハードな作業が多く、年度内に間に合わないのではとの場面がかなりあったが、24年2月24日になんとか最初のCBTによる試験を行うことができた。
一方、行っていく過程の中で、課題も見えてきた。プロメトリックの会場がない地域でどうするか。
日本の宿泊業で働きたいという意思を持つ人たちが学ぶ専門学校がある地域でも、プロメトリックの会場がないところがある。例えばインドネシアはバリやジャカルタ以外に会場がなく、そこ以外にいる人たちは会場がある都市まで移動をする必要がある。しかし、移動にはお金がかかり、金銭的に余裕がない人たちは試験を受けられない。
ただ、プロメトリックではない、紙の試験もできるように要項を当局に変更していただいた。プロメトリックの試験ができない地域でも試験ができるという点は当業種の強みの一つといえ、その点の訴求を今後していきたい。
石坂 私がセンターの事務局長に着任したのが、既にCBTへの移行が済んで、その運用が始まった時期。受験者数と合格者が少ない点について、CBTに移行したことでだいぶ解消された。
CBTに移行した24年、特定技能1号の受験者数が1~10月で前年比406%の8091人。紙試験と並行して行っているが、前年のおよそ4倍だ。そのうち合格者数が6307人、前年比597%。
19年からの累計は、受験者数1万8422人、合格者数1万1524人。合格率62・6%となっている。
国籍別では、CBTに移行してからの24年はミャンマーが突出して多い。受験者数5493人で合格者数4849人。2番目がインドネシア。852人が受験し、440人が合格している。以下、ネパール、ベトナムの順。
累計の受験者数はミャンマー、ネパール、ベトナム、インドネシアの順で多い。
今後の課題は、就業者数が他の業種に比べて極端に少ないこと。24年6月末の速報値で492人と、500人に達していない。向こう5年間の見込み数として2万3千という数字があるが、それに到底達しない水準だ。
2万3千という数字の算出の根拠は、向こう5年間で見込まれる人手不足から、生産性向上で不足が解消された分を差し引いた数字。
試験に合格した人々に対しては、申請に基づき、われわれが合格証明書を発行する。実際に企業で働くというステータスになった時に合格証明書を発行するのだが、これが累計で1261人。やっと4桁になったところ。
累計の合格者が1万1千人ぐらいいるのに、マッチング数が1261人。10.9%だ。
受験者数と合格者数が少ないという問題はCBT移行で解消されたが、次はここが問題。この問題にリーチをしていかないと、人材不足の解消には至らない。
――今後について。
星 海外に行くと、日本の宿泊業について、知識が全くないという人たちがたくさんいる。私はもっと知っていると思い込んでいて、そこが一番ギャップを感じたところだ。
ただ、知識はなくても、働きたいという人が同様に多い。現地に行って、われわれの存在について浸透をさせる必要性を感じるし、現地の人たちの考え方をこちらも理解をする必要がある。
そして現地で得た情報を業界に広くアウトプットする必要があるが、そこに公的な予算があるわけではない。しっかりと予算組みをした上で臨んでいけるような仕組みが作れれば、他業種に負けない競争力を持てると感じる。
山口 外国人材の受け入れについて、特に小規模旅館から、どこに依頼をしたらよいのか分からないという声をよく聞く。電話やファクスやメールで業者からたくさん案内が来るが、これらが信頼のおけるものなのか分からない。
石坂 特定技能の試験に合格した人たちからも、就職先をあっせんしてくださいと、試験センターに問い合わせが来る。
どこに相談したらいいのか分からないという声が受験者からあるし、施設側からもあるのであれば、これらの情報を集約したプラットフォームがあればいい。
山口 試験の新たな仕組みを作るときに、宿泊4団体の選抜メンバーで何度も会議を重ねた。
結果、試験が紙ベースからCBTに変わり、受験者が大幅に増えた。
1人でも多くの外国人材に宿泊業界で働いてもらいたいという思いがあるのだが、新たな制度を作って受験者が増えて合格者が増えても、肝心の求人や就労がなかなか増えない。そのギャップというかジレンマがある。
せっかくの制度。多くの方々に利用していただきたい。
【聞き手=森田淳】

(左から)星、山口、石坂各氏