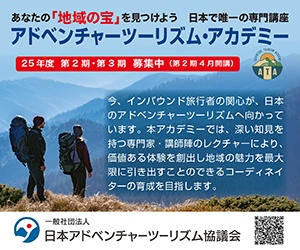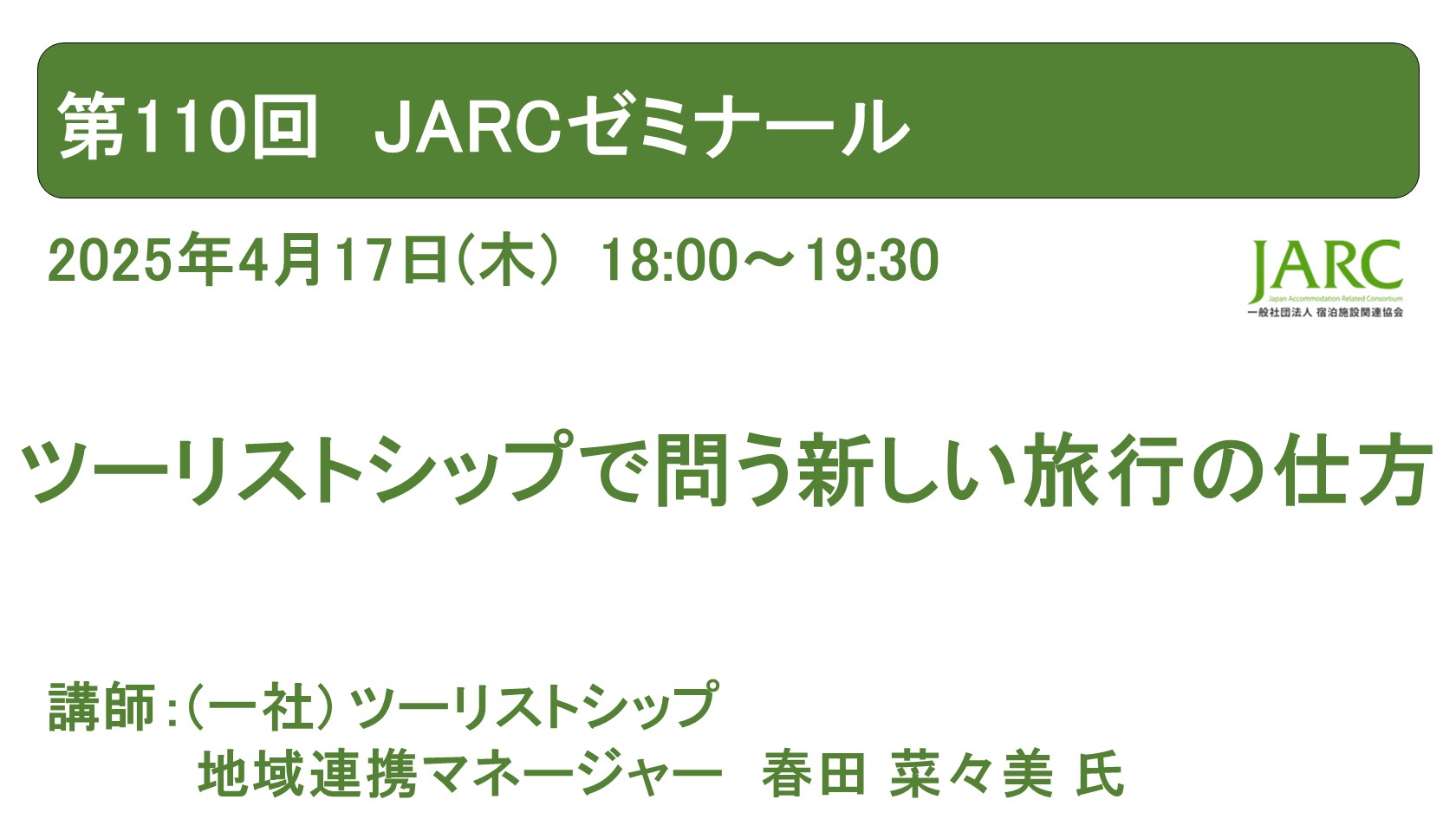松尾一郎氏
災害を知る、情報を共有する、計画通り行動する
観光経済新聞社が1月15日に東京都内で開催した2024年度「人気温泉旅館ホテル250選認定証授与式」で、東京大学大学院情報学環総合防災研究センターの松尾一郎客員教授が、「災害多発国日本!命を守る観光事業者の役割とは?」と題して講演した。講演の主な内容を紹介する。
日ごろ、観光事業者の皆さまが防災・災害のお話をされることは、あまりない機会だと思います。今、大学で客員教授という立場でありながらも学生さんに講義をしながら、能登半島の地震・水害・複合災害、九州の熊本・球磨川で発生した水害の調査、あるいはその後の復旧・復興における観光復興という取り組みもさせていただきました。観光事業者として、「防災」をどういうふうに捉えればいいのか、お話させていただきます。
今、アメリカのカリフォルニア州が山火事で大変な状況となっています。毎年のように山火事が起こっていますが、なぜこの場所で起こるのか。カリフォルニアは暖かい土地で非常に乾燥しています。今、地球温暖化で地球全体の気温や海面水温が上がっています。海面の気候状況から見たとき、そこは乾燥した暖かい空気が入っていく環境で、カリフォルニアはある特定の時期以外雨が降りません。通常は乾燥していて、少し火がついただけで、すぐに延焼していく。これがもう毎年起こっています。地球の変化、自然の変化に私たちも少しずつ変化しないと、もう太刀打ちできないことになっている。「目を覚まそう」、これが最初のメッセージです。
◆ ◆
今では、だいたい5、6年のサイクルでマグニチュード6~7クラスの大きな地震が発生しています。能登半島地震も東日本大震災も「国難級」の災害です。災害が起き、少子高齢化で復旧復興に向けた投資もできなくなると、そこに住み続けるのが難しくなる。水害も地震災害も、過去の調査では3割程度人口が減ります。復興街づくりが進んでも空き地が目立つ。そうした中でも、当然観光事業者の皆さまはそこで事業を営んでいくという選択をするでしょう。被災地域であっても、安心・安全な観光地であることを世の中に伝えていき、これまで以上の取り組みをしていくことが必要です。
基本的に、災害は国全体ではなく地域で起きます。そうなると、命を守るために、地域に暮らす私たち住民はもちろん、行政、警察、消防、それぞれが役割を持つことが重要です。そのためには、少なくとも災害が発生するときにどんなことが起きるか、起こったとき自分たちにどのような被害が生じるのか、施設の利用者の人たちへ影響がないか、その影響を最小限にするためにはどんな対策が必要なのか。災害をよく理解していれば整備ができます。だから、「まず危機感を持てるか」「被害を軽減するためにどんな行動をすべきか」「その行動のためにそれぞれがどう役割を持って行動するか」が重要です。
日本の災害対策基本法では、基本的に地域住民にも観光客にも「逃げてください」と指示するのは市町村長で、それは責務です。だから利用者の皆さまを預かっていながら、その方々の命を守るとき、基本は行政と連携した上で、各市町村が伝えていることをうまく利用者に伝えることが必要になります。そこにはさまざまな困難があると思います。何が起こるか、そこでどんなことが起こるか、少なくとも利用者の方々の安全を守るためにはどうするかということを、日ごろから考えることになります。
◆ ◆
近年、わずか13年間で多くの災害が起こっています。
能登半島地震の死者数の最新値は508名ですが、発災から日数がたつほど、後から増えていくのは災害関連死です。能登半島地震の直接災害で亡くなった方は228人で、これは変わりません。避難所生活が大変で、そこで亡くなった方もいるのです。熊本地震は直接被害で亡くなった方の約2倍から3倍近くに、能登半島地震は2倍強でした。私も能登半島地震の被災地に入りましたが、今の被災状況と復旧・復興状況は非常に厳しい状態だと感じております。
球磨川氾濫では「線状降水帯」がよくテレビで聞かれました。当時人吉の河川で何が起こったかというと、約7時間で300から400ミリの大雨が降りました。これはどこの川であっても水があふれる量です。こうした事例が今増えています。水害の場合、少なくとも行政が発表しているハザードマップでどれだけ浸水するかという情報が公表されていますから、施設の周りとか、利用者の方が比較的よく行かれる観光スポット等でどれぐらいの浸水があるかが確認できます。少なくとも行政が発行しているハザードマップを見た上で、施設の利用者へどのように行動するかを伝えることが必要です。
ここから私が今、人吉の観光事業者の皆さんと一緒に取り組んでいる「リバーミュージアム構想」という話をしたいと思います。
球磨川の水害は2020年、ちょうどコロナ禍に発生しました。熊本県が公表している観光入込客数とその増減を示したグラフでは、2020年に25万人近く減っています。この原因はコロナも要因ですが、7月の豪雨災害も影響が大きいです。当然、観光地・球磨川も被災し、肥薩線をはじめとする交通手段がなかったということは大きいと思います。被災路線も含めて復旧復興には10年近くかかります。だけど地域・観光事業者としては待てない。
そこで「球磨川の防災と観光復興 災害に強いまち・ひとを目指す」ということで、球磨川の流域12市町村を結びつけ、自然のままを観光客に見せていく、そのためのさまざまな整備、インフラ整備、駐車場とかさまざまな整備をしていくエコミュージアム構想に取り組んでいます。熊本県では、知事の公約にも組み込まれました。おそらく、これから2、3年かけて形を作って実験的なツアーを企画し、取り組んでいくのだろうと思います。
近年の地震については、西暦1600年前後に起こったことの繰り返しではないかと考えています。地震は、地球のプレートのひずみで起きています。ひずみがある以上、地震は確実に繰り返すのです。海で起こる地震というのは、100年から200年単位で、内陸で起こる地震は千年から2千年以上の間隔で起こります。能登半島地震は、前回は千年前です。東日本大震災も、500年前の出来事が繰り返されて起きたことです。南海トラフも大体100年から200年単位で起こる。1600年前後に起きた災害と近年の災害、比較してみると発生した地名が似ていることに気づくと思います。今、日本全体がそういう時期に差し掛かっているのです。
大震災が起こるとき、大きな揺れと水害に加え、停電や断水もあります。地震だと、停電期間が非常に長いです。そういうことが起こったとき、どのようにお客さんの命を守るべきか。やはり受け入れ施設としては日ごろ考えておくべきものだと私は思っています。
火山についても同様です。火山周辺には観光地が当然多いです。火山が噴火したときにはそれなりに規制が入るし、行政も入るから、情報が必要になります。アンケートを実施したところ、やはり利用者は安心情報を提供してほしいとの声が多かった。火山が今活動しているかどうか、これだけでも、例えばフロントでお伝えするとか、掲示板で山の様子を伝えるとか、伝え方があるだろうと思います。それをきちんとやっているのがニュージーランドです。日本でこれを積極的にやっているところは意外と少ないと思います。観光協会と地元行政機関との連携が必要だと思います。
◆ ◆
観光事業者が大規模災害の対応で混乱するのは、経験のないことが起こったとき。それは市町村もそうです。それぞれのリスクをきちんと知っておく、あるいは事前に防災計画を作っておく。これが重要。インバウンドの観光客も、日本を旅行するときの最大の不安について調査をすると、やはり4分の1は災害だった。
大規模災害から利用者の命をどのように守るか。それは「知る」「共有する」「行動する」。施設の安全対策は施設管理者としての対応が必要になります。では施設内にいるときにどう行動すればいいかについては、利用客を災害から守るためにどんなことをするべきかイメージした「事前防災行動計画(タイムライン)」があります。
100年以上前に書かれた災害調査の報告書には、「用意周到」「沈着機敏」「臨機応変」と書かれています。この三つの言葉を皆さんにお渡しして、私の話を終わらせていただきたいと思います。

松尾一郎氏