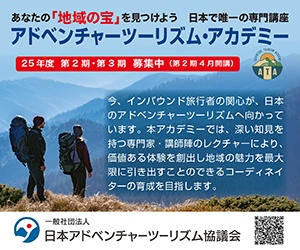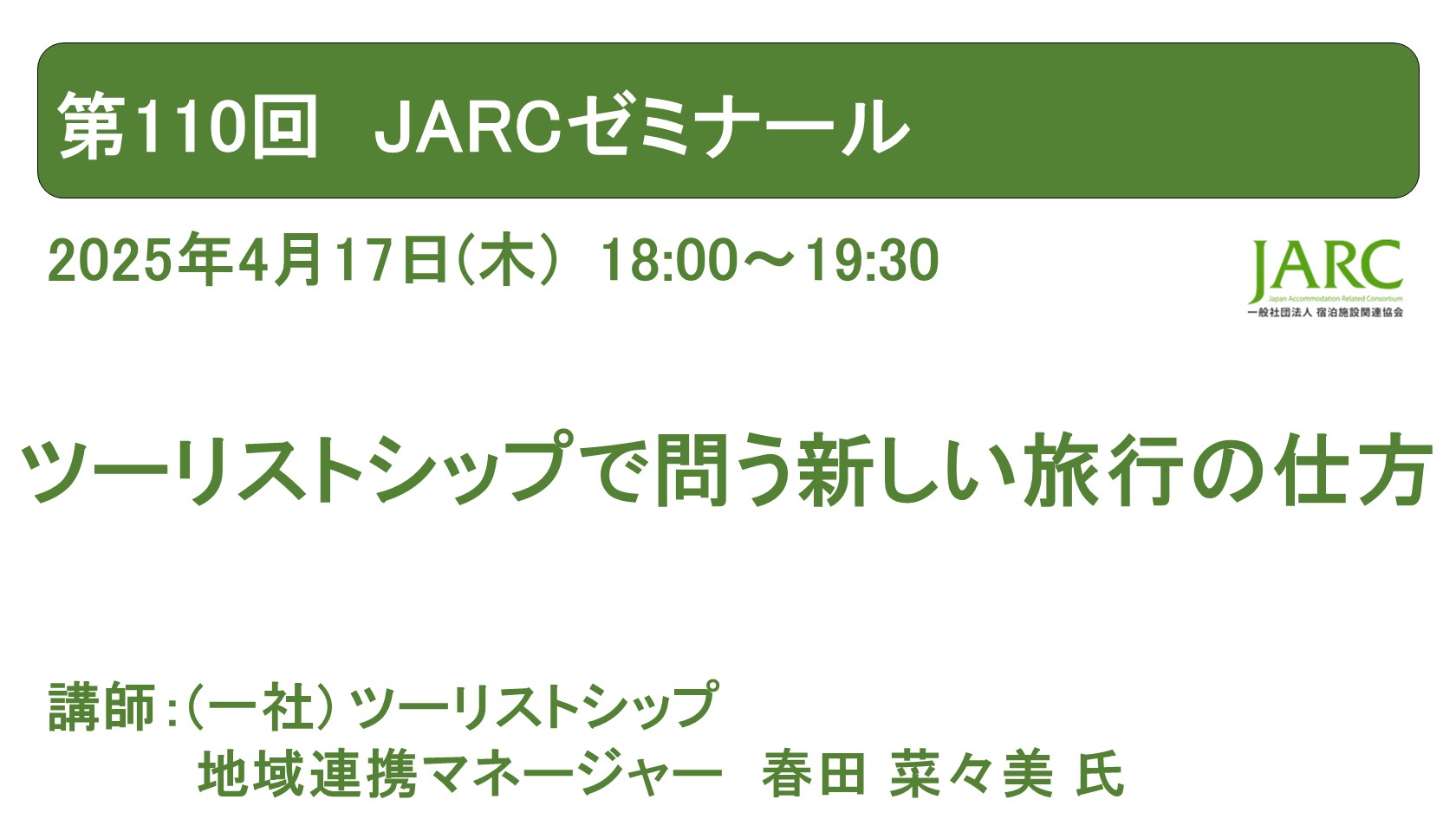防災・減災加速化対策 災害に強い観光地へ
観光経済新聞、東京交通新聞、塗料報知、農村ニュース、ハウジング・トリビューンの専門5紙誌では、防災・復興をテーマとした連携企画「地域が創る復興・活性化の未来図~大災害の教訓から」を展開中です。今回、2016年4月14日の「熊本地震」を取り上げ、各紙・誌による被災当時の状況や最新の動きをレポートします。併せて、2021年度からの国が推進する「防災・減災、国土強靱(きょうじん)化のための5カ年加速化対策」が最終年度である2025年度を迎えるに当たり、内閣官房国土強靱化推進室企画官の髙木繁光氏に話を聞きました。
――今回テーマとして、防災・減災、国土強靱化の取り組みの推進ということで、その現状を探るとして、加速化対策の最終年度を迎え、成果等はどうか。
最終年度を迎えての成果だが、5カ年加速化対策自体の取り組みはしっかり推進している。予算の関係では令和6年度補正予算が昨年成立しているが、資材価格の高騰を踏まえ、5カ年加速化対策の関連予算と緊急防災枠という予算枠を合わせて約1・7兆円という規模の予算措置がされて、来年度は着実に取り組みを推進する状況になっている。
これまでの取り組みでは、例えば河川の治水対策では、実施前と同じ程度の大雨が降っても浸水被害を防止する、あるいは被害を大きく軽減する事例が見られている。
道路関係でも、道路ネットワークの機能強化対策は大雨で通行止めになった国道があるが、整備した高規格道路が迂回(うかい)路として活用された事例もある。
近年は、線状降水帯が問題として浮上しているが、令和6年5月から地方単位を県単位にさらに絞って、呼び掛けを実施して早期の防災対応を行う取り組みも始まっている。このように、さまざまなハード・ソフト両面における効果が全国で積み上がっている状況である。
最近の事例では、令和6年能登半島地震について、七尾港で耐震強化岸壁が過去に整備されていて、そこでは損傷が軽微にとどまり、被災直後から物資輸送などにも貢献したということがあった。また、珠洲市役所では太陽光発電の設備や蓄電池が整備されていて、災害対応業務の継続にも貢献したという報告を受けている。甚大な被害が生じた中でも、被害者支援や復旧につながった事例が見られたという成果が出ている。
一方で、自然災害が激甚化並びに頻発化しており、大規模災害の恐れも切迫しており、引き続き事前防災対策を推進していきたいというのが現在の考え方である。
――宮崎で大きな地震が起きたり、また初めて「南海トラフ地震臨時情報」が発信されたりしたが、こういったことについて具体策を緊急で盛り込むなどの動きはあるのか。
5カ年加速化対策自体は、令和2年12月に閣議決定され、その対策に沿って推進しており、急に対策項目が増えたということはないが、5カ年加速化対策自体でもさまざまな耐震対策が盛り込まれている。豪雨災害にしても、地震災害にしても、国土強靱化を図ってきているところである。
――現在、インバウンドで観光関係が盛況である。一方で観光地が災害に見舞われると、観光客の被害や観光資産の損失が懸念される。災害に強い観光地として取り組み施策には何が挙げられるか。
国土強靱化において、5カ年加速化対策としては、文部科学省では国指定等の文化財についての防火対策、耐震対策、あるいは天然記念物の保全整備に取り組んでいる。また、環境省では、自然公園の緊急避難場所の改修を5カ年加速化対策の中で推進している。
文化財の保護においては、実際にその作業に携わる経験豊富な人や、学識経験者の知見など、多くの関係者が共同して取り組みを進める必要があると考える。
国土強靱化は政府において基本計画を策定しており、自治体においては地域計画を策定して協調しながら取り組みを進めている。民間部門についてもBCP策定の推進や取り組み事例集の情報発信などに取り組んでいる。国・自治体・民間と国土強靱化を図っていく体制を構築していて、引き続き取り組みを推進していきたい。
――個々の対策については計画内の事例が参考になるといえるか。
ターゲットによって変わってくると思う。例えば、文化財の保護関係なら文部科学省、自然公園なら環境省と支援体制がそれぞれある。それらを踏まえて取り組みを広げていくということになると思う。
実際、文化財や天然記念物の保全整備を進めている取り組み事例も、強靱化として情報発信しており、参考にしていただけるとありがたい。
国・自治体・民間で継続推進
――南海トラフ地震など今後、地球温暖化で水害などが予測される中で、早急に注力すべき事項というのは何か。
5カ年加速化対策の全てが早急に手を打つべきことだと考えている。総括的な話としては、5カ年加速化対策自体は令和3年度から7年度の5年間で来年度は最終年度となる。予算措置でいうと令和6年度補正予算が5年目の予算措置になっており、予算自体は5年目が措置されたということになっている。
引き続き、継続的に必要な事業が実施していけるように、5カ年加速化対策の次の実施中期計画の検討を進めている。1月の石破総理の施政方針の中では6月をめどに策定するという言及がされた。しっかり検討を進めている状況である。
国土強靱化については、国土政策や産業政策などさまざまな分野の対応が必要で、ハード・ソフト両面からの取り組みが必要である。
加えて、単に国の政策だけではなく、都道府県、市町村、民間も広く関わるような内容になってくるので、さまざまな方々の協力を得ながら、確実に進めていきたいと考えている。
――最終年度を迎えて、成果が上げられた部分、また一方で未達成部分は何か。
河川のしゅんせつ対策では、実際の取り組みによって被害が軽減された実例はある。その一方で、対策を今後進めていかなければならない部分も残っている。老朽化対策については、進む老朽化に対して着実に手を打たないといけないという状態が、まだまだ続くと見ている。防災減災に関わる対策や、予防保全型メンテナンスへの転換など、そのような取り組みは確実に継続していく必要がある。