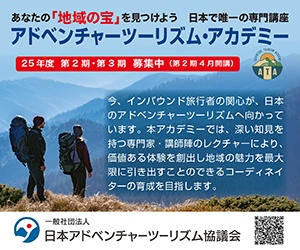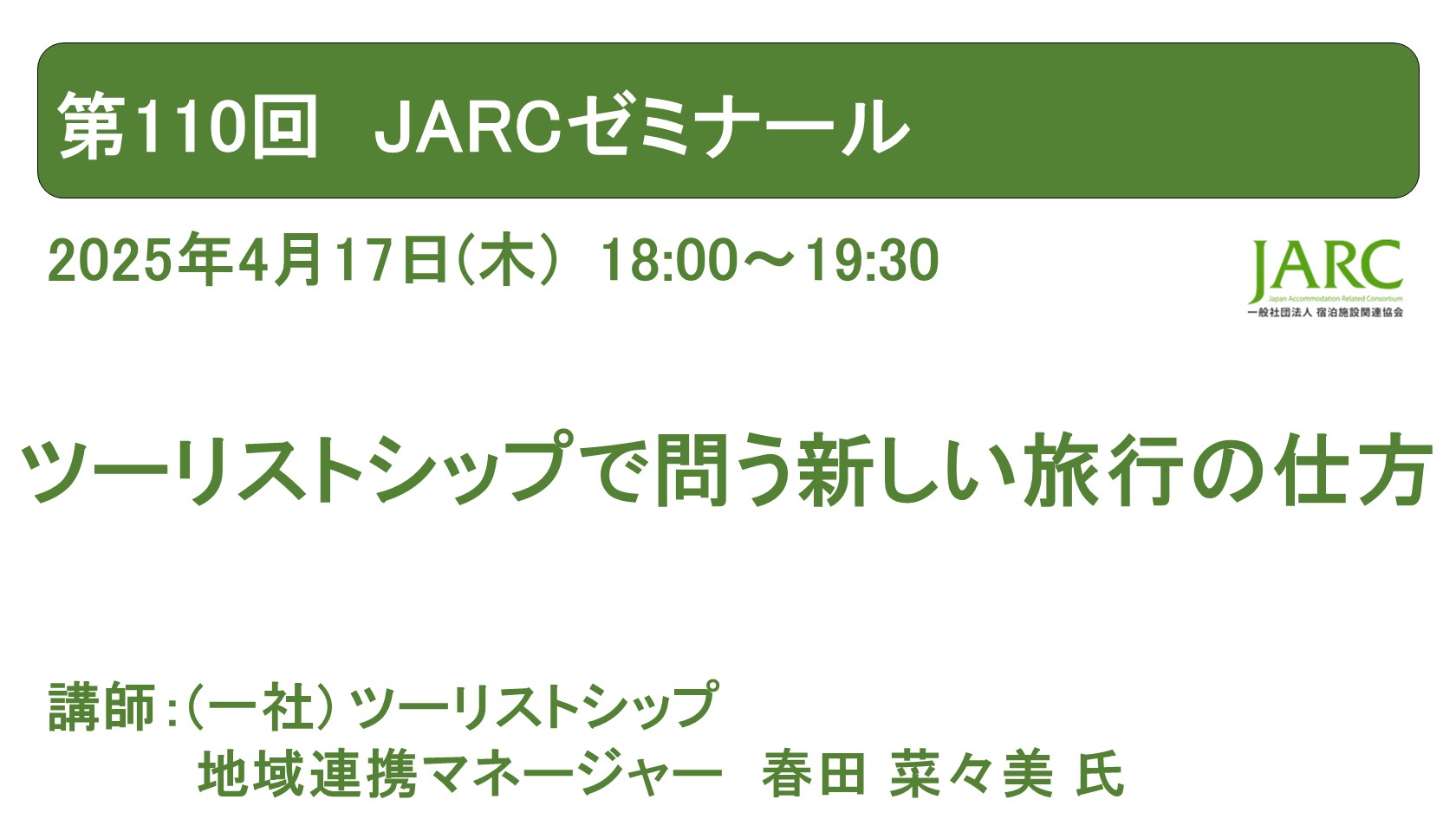観光振興財源としての宿泊税の必要性を強調
宿泊税導入で観光振興財源の確保を
経済同友会の観光戦略委員会(伊達美和子委員長=森トラスト代表取締役社長)は2月14日、「観光振興の鍵、宿泊税の導入と活用」と題したシンポジウムを東京・港区の明治記念館で開催した。、宿泊税の導入と効果的な活用について、第一線で活躍する専門家や自治体首長らが議論を交わした。
経済同友会副代表幹事・観光戦略委員会共同委員長の伊達美和子氏は開会挨拶で、「観光振興の財源として宿泊税の導入が必要」強調。「昨年、自立した地域の観光経営の実現に向けた宿泊税の拡大と活用について提言を行った。主な内容は、自治体負担となる宿泊税を全国的に導入すること、物価変動に柔軟に対応できる定率制を採用すること、そして自立的な組織づくりのために使途や人を明確にすることだ」と説明した。
その上で「近年、全国各地で宿泊税の導入が検討され、その機運は高まっている。しかし、宿泊税という言葉や手続き、徴収することが先行しているように感じる。地域の関係者とともに、何のために課税を行うのか、どのような形の課税が望ましいのか、徴収した税金をどのように活用すべきか、どんな体制で運用していくのか、そうした本質的な議論が十分されていないまま今日に至っているのではないかと危機感を感じている」と課題を指摘した。

あいさつする伊達委員長
第1セッション「観光予算を取り巻く状況と観光振興財源の必要性について」
パネリスト:下地芳郎氏(沖縄観光コンベンションビューロー会長)、鈴木貴典氏(観光庁審議官)、原忠之氏(セントラルフロリダ大学ローゼンホスピタリティ経営学部テニュア付准教授)
モデレーター: 長嶋由紀子氏(経済同友会観光戦略委員会副委員長/リクルートホールディングス常勤監査役)

左から長嶋氏、原氏(オンライン登壇)、鈴木氏、下地氏
宿泊税導入の背景にある観光の現状
長嶋 まず観光を取り巻く現状について、下地さんからお話しいただけますか。
下地 沖縄の観光の特徴は、人口33万人のところに年間300万人が宿泊する街だということです。コロナ前は1000万人近くまで伸びていましたが、現在は9割以上回復しています。私は常に観光は投資産業であると言っています。つまり投資をし続けなければならない。今ある観光コンテンツに磨きをし続けなければならない産業であり、そのためには財源が必要ということです。
長島 鈴木さん、国の立場から見た観光の現状はいかがでしょうか。
鈴木 国の観光施策の流れを簡単に説明しますと、2003年に小泉政権下でビジットジャパンキャンペーンが始まりました。当時のインバウンドは500万人程度でした。2010年までに1000万人を目指しましたが、実際に達成したのは2013年でした。その後、安倍政権下で2020年に4000万人、2030年に6000万人という目標を設定しました。現在の目標は2030年に6000万人、消費額15兆円、1人当たり25万円です。これは人口減少に対応し、地方の観光地や観光施設を維持・発展させるための戦略です。
長嶋 原さん、アメリカの事例から見た日本の観光の現状はどうでしょうか。
原 日本の観光予算の財源比率を見ると、沖縄県の観光消費額8000億円に対して一般財源50億円で0.6%、観光庁は30兆円に対して500億円で0.25%程度です。一方、アメリカのフロリダ州では消費額2兆円に対して観光財源が538億円で2.6%、ハワイ州では消費額2.2兆円に対して宿泊税が13%で3000億円程度の観光財源があります。日本は観光投資財源が圧倒的に少ないことが分かります。
宿泊税導入の意義と課題
長嶋 宿泊税導入の意義について、それぞれのお立場からお聞かせください。
下地 沖縄県では宿泊税の導入を決定し、2025年4月から実施する予定です。税率は2%で、上限額は2000円です。年間約78億円の税収を見込んでいます。この財源を活用して、花火大会やMICE施設の整備、移動手段の改善などを行う計画です。また、DMO(観光地域づくり法人)の運営にも活用する予定です。
鈴木 国では2019年1月から国際観光旅客税、いわゆる出国税を導入しました。1回の出国につき1000円をいただいています。この財源を活用して、ストレスフリーで快適に旅行できる環境整備や、文化財・国立公園の活用、プロモーションの強化などを行っています。令和7年度予算では490億円の税収を見込んでいます。
原 アメリカのオーランドの事例を紹介します。オーランドは人口140万人のところに年間7400万人の観光客が訪れます。宿泊税は1978年に2%で導入され、現在は6%まで引き上げられています。2023年の税収は538億円(150円換算)です。この財源を活用して、観光施設の整備やプロモーション、地域住民への還元などを行っています。
長嶋 宿泊税導入における課題はどのようなものがありますか。
下地 沖縄の場合、146の有人島があり、離島住民への配慮が必要です。また、宿泊事業者の理解を得ることも重要です。税収の使途を明確にし、観光振興に確実に活用されることを示す必要があります。
鈴木 国際観光旅客税の導入時には、航空会社や旅行会社など関係業界から様々な意見がありました。使途を明確にし、観光振興に確実に活用されることを示すことで理解を得ました。
原 アメリカの場合、宿泊税の財源は主に観光振興に使われていることが明確です。DMOの運営費用も宿泊税から賄われています。日本でも使途を明確にし、観光振興に確実に活用されることを示す必要があります。
宿泊税の効果的な活用方法
長嶋 宿泊税をどのように活用すれば効果的でしょうか。
下地 沖縄では、観光客の満足度向上と地域住民の生活の質向上の両立を目指しています。具体的には、観光施設の整備、イベントの開催、交通インフラの改善などを計画しています。また、DMOの運営にも活用し、戦略的な観光振興を行います。
鈴木 国際観光旅客税の活用事例としては、空港の顔認証ゲートの導入、多言語対応の強化、文化財や国立公園の観光活用などがあります。これらの取り組みにより、インバウンド受入環境の整備が進んでいます。
原 アメリカの事例では、宿泊税を活用して観光施設の整備やプロモーション、地域住民への還元などを行っています。特に重要なのは、地域住民に対して観光産業の重要性を説明し、理解を得ることです。オーランドでは、観光客が支払う税金のおかげで住民の所得税がゼロになっているなど、具体的な恩恵を示しています。
長嶋 宿泊税の導入と活用について、それぞれ最後に一言お願いします。
下地 宿泊税は観光振興のための投資財源です。これを活用して、観光地としての魅力を高め、持続可能な観光を実現していきたいと思います。
鈴木 国際観光旅客税の導入により、観光予算が大幅に拡大しました。国としては、これを効果的に活用し、日本の観光産業の発展につなげていきたいと思います。
原 宿泊税は地域の観光振興に不可欠な財源です。日本でも積極的に導入し、効果的に活用することで、観光立国の実現につながると確信しています。
第2セッション「観光復興財源の効果的な使途の考え方について」
パネリスト: デービッド・アトキンソン氏(小西美術工藝社代表取締役社長)、高島宗一郎氏(福岡市長)、斉藤栄氏(熱海市長)
モデレーター: 杉田浩章氏(経済同友会観光戦略委員会副委員長/ボストンコンサルティンググループ・シニアアドバイザー)

左から杉田氏、斉藤氏(オンライン登壇)、高島氏、アトキンソン氏
宿泊税の効果と使途を検証
杉田 宿泊税の具体的な使途について、それぞれの立場からお聞かせください。
アトキンソン 宿泊税の本質は、観光地の問題解決のための投資財源です。日本の観光地では、何十年も前から指摘されている問題が放置されています。例えば、日光のピーク時の渋滞問題や京都の清水寺の混雑問題などです。宿泊税を取って別のことに使うのではなく、こうした放置されてきた問題を解決することが重要です。
高島 福岡市では2020年4月から宿泊税を導入しています。税率は宿泊料金2万円未満が200円、2万円以上が500円の2段階制です。税収は導入当初の6.9億円から、2025年度予算では31.7億円まで増加する見込みです。使途としては、九州のゲートウェイ都市機能の強化、MICE都市としてのプレゼンス向上、地域や市民生活と調和した持続可能な観光振興の推進の3つを柱としています。
斉藤 熱海市では2025年4月から宿泊税を導入する予定です。税率は1人1泊200円の定額制です。年間約7億円の税収を見込んでいます。使途としては、観光施設の整備、イベントの開催、花火大会の運営、MICE施設の整備、移動手段の改善などを計画しています。また、DMOの運営にも活用する予定です。
杉田 宿泊税の効果をどのように検証していますか。
高島 福岡市では、定期的な評価と見直しを行っています。宿泊事業者へのアンケートでは、6割以上から評価できるという回答を得ています。また、宿泊税の活用事例を分かりやすく紹介する冊子を作成し、宿泊事業者に配布しています。
斉藤 熱海市では、DMOを中心に宿泊税の使途と効果を検証する予定です。具体的には、白書を作成し、財源の使途と効果を明確に示していきます。
アトキンソン 効果の検証には、観光客数と消費額、そして観光産業従事者の所得という3つの指標が重要です。特に、観光産業従事者の所得を上げることが、地域経済の活性化につながります。
DMOの役割と宿泊税の関係
杉田 DMOの役割と宿泊税の関係についてどうお考えですか。
斉藤 熱海市では、宿泊税を財源としたDMOの設立を計画しています。DMOには観光のプロを配置し、行政も参画します。DMOが宿泊税の使途を決定し、効果を検証する役割を担います。
高島 福岡市では、DMOと行政が連携して観光振興に取り組んでいます。宿泊税を活用して、DMOの機能強化や事業の拡充を図っています。
アトキンソン DMOは本来、マーケティングだけでなく、観光地のマネジメントを担う組織です。宿泊税を財源として、DMOが地域の課題解決や投資判断を行うことが重要です。
宿泊税導入の課題と展望
杉田 宿泊税導入における課題と今後の展望についてお聞かせください。
アトキンソン 日本の観光産業は、人口減少対策として非常に重要です。2024年の出生数は67万人で、ピーク時の4分の1以下です。観光産業を発展させることで、地方の衰退を防ぎ、経済を活性化させることができます。宿泊税は、そのための重要な財源です。
高島 宿泊税の導入には、様々なステークホルダーの理解を得ることが重要です。福岡市では、観光振興条例を制定し、その上で宿泊税条例を制定するという手順を踏みました。また、税収の使途を明確にし、宿泊事業者や市民にも恩恵があることを示すことで、理解を得ています。
斉藤 熱海市では、宿泊税の導入を7年前から検討してきました。事業者や議会の理解を得るのに時間がかかりましたが、丁寧な説明を重ねてきました。宿泊税は観光振興のための投資財源であり、この財源を活用して観光地としての魅力を高めていきたいと考えています。
山野智久経済同友会観光戦略委員会委員長(=アソビュー代表執行役員CEO)は閉会の挨拶で、「日本の観光財源比率は海外に比べて圧倒的に少ない。宿泊税の導入と効果的な活用が、持続可能な観光振興には不可欠だ。今回のシンポジウムの議論が、各地での宿泊税導入の参考になることを期待している」と締めくくった。