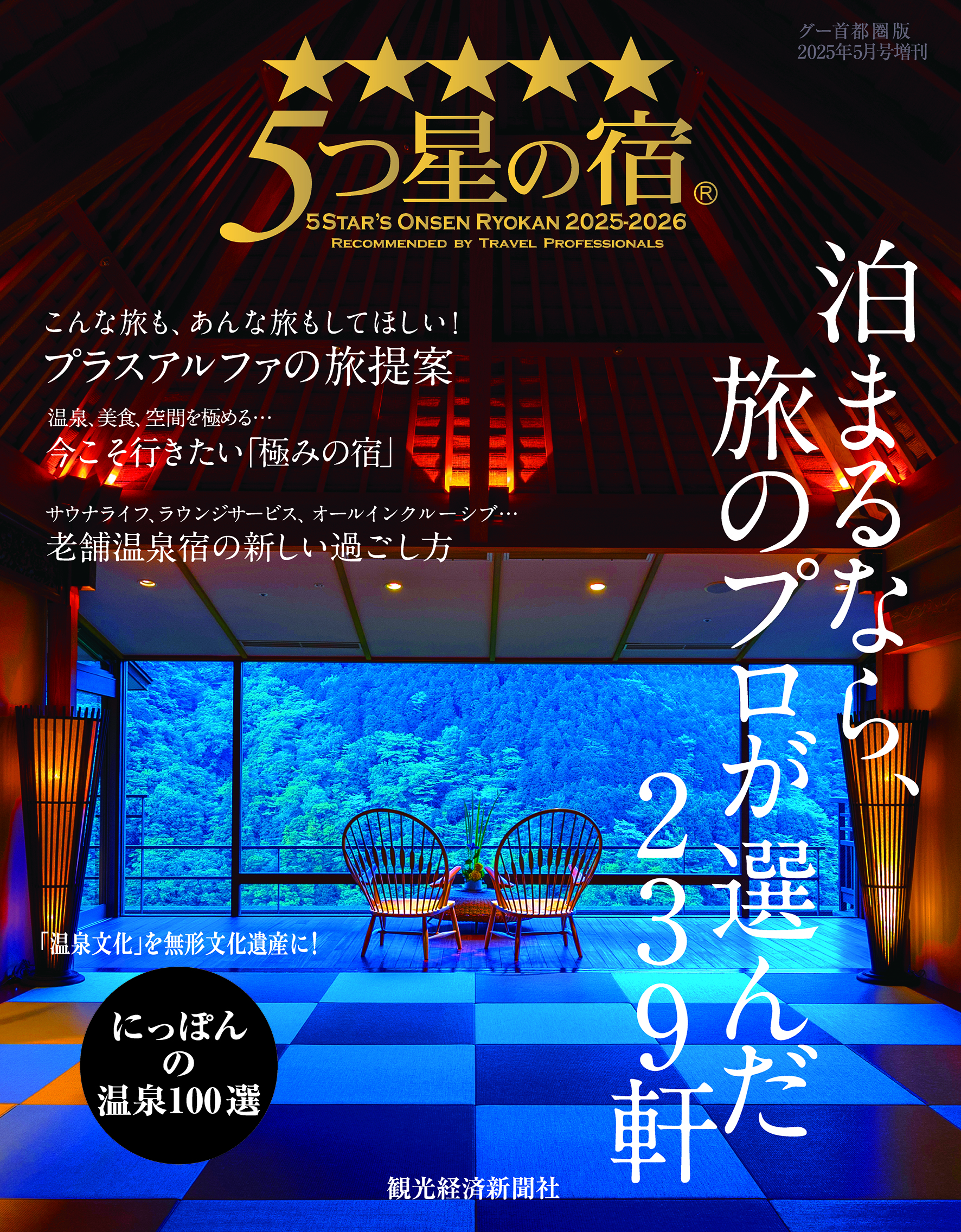交通、観光事業者らが、それぞれの取り組みを紹介した
近畿運輸局は7日、大阪市のグランヴィア大阪で「『ジェンダー主流化』の取り組みに関する座談会」を開いた。男女共同参画などの専門家による講演を行ったほか、運輸、交通、観光分野の事業者がそれぞれ事例報告を実施。就業時間や安全面の確保など、女性活用のネックになっている事象などについて意見を交わした。
講演では、追手門学院大学経済学部の長町理恵子准教授がジェンダー主流化や女性活躍、交通分野の現状と課題について講演。ジェンダー主流化を「あらゆる分野、あらゆるレベルでの立法、政策、プログラムを含む計画措置が、異なるジェンダーに与える影響を評価するプロセス」などとした上で、少子高齢化による生産年齢人口の減少や人手不足、女子の大学進学率の上昇などの経済・社会的変化や男女別の就業率、昇進意欲などをデータを示しつつ解説。交通分野での現状と課題についても、産業別の就業者性差や交通分野の仕事の特性などを説明した上で、「性別にかかわらない取り組みやジェンダー主流化のメリットの認識などが必要。女性、高齢者、障がい者など地域の潜在的な労働力を生かすことが交通分野の活性化につながる」と指摘した。
 会員向け記事です。
会員向け記事です。