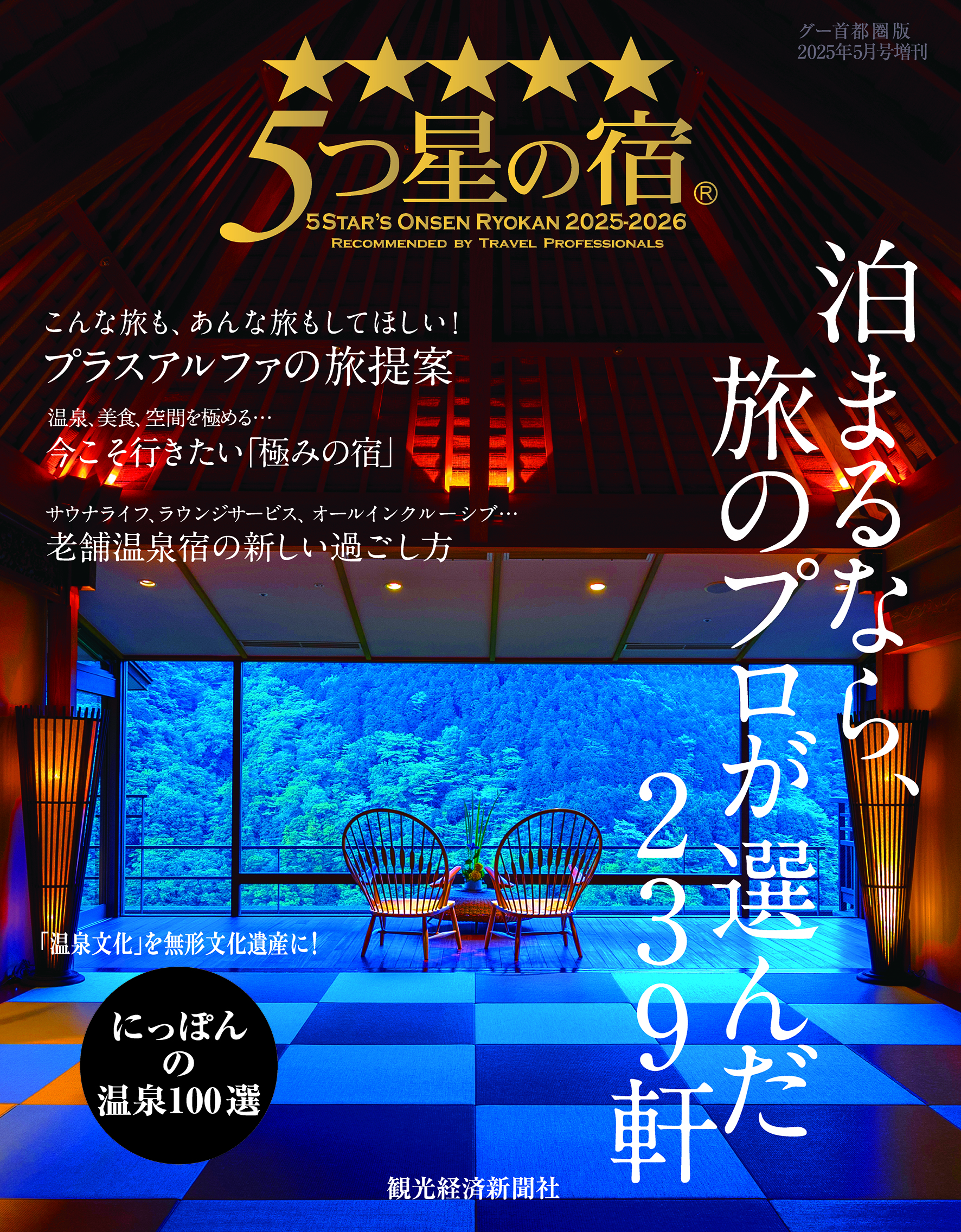佐藤市長
栃木県宇都宮市に次世代型路面電車「芳賀・宇都宮LRT(ライトライン)」が開業(2023年8月26日)して、およそ1年半が経過した。想定を超える利用者があり、将来的には同市が観光の目玉として期待する大谷観光地付近までを延伸の検討区間としている。佐藤栄一市長にライトラインの開業・延伸を踏まえた同市の交流人口拡大を含めたまちづくりの施策を聞いた。
土日祝日の利用者が当初予測の2倍 将来は大谷地区に延伸へ
――ライトラインが開業しておよそ1年半が経過。多くのお客さんに利用されているようだ。
想定以上にご利用いただいている。特に土、日、祝日。通勤客がある平日以外は営業上弱いといわれていたが、1日当たりおよそ1万人。当初予測の2倍となっている。買い物などの日常生活の足として定着するとともに、ライトラインに乗ることを目的に、市外から多くのお客さんも来ているようだ。
当市は定住人口とともに、交流人口の拡大を大きなテーマとしている。バスケットボール3X3(スリーエックススリー)の国際大会や、自転車レース「ジャパンカップサイクルロードレース」など、イベント開催の仕掛けもしているが、恒常的に拡大するには観光業を育てなければならない。
当市は大谷石を観光の目玉に育てようとしている。大谷石採掘の歴史や本市独自の「大谷石文化」が文化庁から「日本遺産」に認定された。その大谷地区は年間78万人ほどの来場者数があるが、日本遺産に認定された2018年、その数を120万人にする目標を掲げた。
ライトラインを、将来、この大谷地区まで延伸したい。現在はJR宇都宮駅の東口から工業団地がある芳賀町までの14・6キロだが、これを駅西口の市内中心部、さらには郊外の大谷方面へ延伸する。
まずは駅の西口からまっすぐ西へ「栃木県教育会館」や「コンセーレ」付近までの約5キロを整備する予定だ。今年度中に、軌道事業の特許取得に必要な「軌道運送高度化実施計画」を国に提出し、2030年の開業を目指す。
宇都宮は二荒山神社を中心に栄えてきたまちだ。神社がある駅の西側はまちの基盤が古くから出来上がっていたが、それゆえに古くなった大きな建物がたくさんある。建て替えの時期なのだが、現状、地元のオーナーさんの力だけではなかなか難しく、外からの資本が必要になっている。
ライトライン延伸の構想が上がってからは、止まっていた再開発の事業に外からのオファーが来だした。地元のオーナーと外からの大きな資本が一体になった事業がこれから増えるだろう。
さらに将来的にはそこから先の大谷地区に路線が延伸すれば、アクセスが便利になり、さらに多くの誘客が実現できるだろう。
ただ、観光客、特に長期滞在のお客さんを増やすためには、市内に限らず、日光や那須、益子など、県内の周辺市町との連携が必要だ。日光市とは既に海外の国際MICE事業者を招いたモニターツアーを催行するなどしており、今後さらに連携を深めていきたい。
――LRT導入に当たり、他の都市で参考としたものは。
市長に就任する前に視察をしたのが沖縄のモノレール。市長に就任してからはフランスのストラスブールを視察した。ここでは交通環境税という税金を使い、LRTを建設したという。CO2の削減に貢献する公共交通機関に投資をするとの名目で、運賃に頼らない方式だった。当市でまねはできないが、これらを参考にして、それぞれの地域の歴史や実情を踏まえてオーダーメイドでつくらなければいけないと結論付けてさまざまな選択肢がある中でLRTの導入に至った。
――「住みやすいまち」と評価が上がっているようだ。
開業が呼び水となり、沿線の人口が事業化が確実となった平成25年と比較して8%増えた。地価は商業地が6%、住宅地が11%上がった。
新たな公共交通機関ができたことで、市民の外出の頻度が高まったとのデータもある。結果、域内での消費が拡大するとともに、1日の平均歩数が増えたことによる医療費抑制効果は、年間で2億9千万円から3億3千万円との試算もある。
――LRTは環境面でもいい。
電気で走るのでCO2をほとんど出さない。その電気も家庭ごみの焼却や家庭用太陽光等により発電された再生可能エネルギーだ。再生可能エネルギー100%で走る世界で初めてのLRTとなっている。
路線バスについても、関東自動車株式会社が市内を走行する大型バスの約7割、158台を2030年までにEV化する予定であり、既にEV化された5台が先行して走行している。
佐藤 栄一氏(さとう・えいいち)1961年10月5日生。北関東観光開発代表取締役、宇都宮青年会議所理事長などを歴任し、2004年宇都宮市長に初当選。現在6期目。

佐藤市長
【聞き手・観光経済新聞編集長 森田淳】